3103キロ
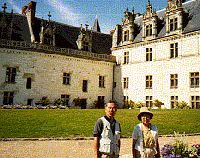 ヨーロッパ諸国のように国土が地続きで、争いが絶えず、必然的に人や文化の交流が盛んだったところはその痕跡も多く残されていて、そこを訪れる旅人をその昔へ連れていってくれる。しかし、この右の写真、静かに流れるロワール河を見下ろす美しいアンボワーズ城を見ていると、16世紀には血なまぐさい陰謀や権力争いを見てきて、一時jはこのバルコニーから抵抗した新教徒の生け贄が何体も釣り下げられた場所だとはなかなか信じがたい。
ヨーロッパ諸国のように国土が地続きで、争いが絶えず、必然的に人や文化の交流が盛んだったところはその痕跡も多く残されていて、そこを訪れる旅人をその昔へ連れていってくれる。しかし、この右の写真、静かに流れるロワール河を見下ろす美しいアンボワーズ城を見ていると、16世紀には血なまぐさい陰謀や権力争いを見てきて、一時jはこのバルコニーから抵抗した新教徒の生け贄が何体も釣り下げられた場所だとはなかなか信じがたい。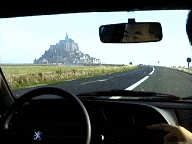 フランス西北部の海に突きだした小さな島全体が1つの修道院であったモンサンミシェルが目の前に迫ってくる。朝9時前の到着で1番乗りのつもりが、もうかなりの賑わい。でもパリの細い路地裏を思い起こさせる狭くて暗い石畳の登り道や階段を昇るにつれて、中世の城壁の向こうにイギリス海峡やノルマンディーの海岸がパッと目の前に開ける一瞬がある。この周囲900メートルのちっぽけな陸続きの「島」に年間250万人が世界から訪れ、入場料45フラン(900円)を払うだけで、年に22億円が入るのかと凡人の頭は変な方にめぐる。
フランス西北部の海に突きだした小さな島全体が1つの修道院であったモンサンミシェルが目の前に迫ってくる。朝9時前の到着で1番乗りのつもりが、もうかなりの賑わい。でもパリの細い路地裏を思い起こさせる狭くて暗い石畳の登り道や階段を昇るにつれて、中世の城壁の向こうにイギリス海峡やノルマンディーの海岸がパッと目の前に開ける一瞬がある。この周囲900メートルのちっぽけな陸続きの「島」に年間250万人が世界から訪れ、入場料45フラン(900円)を払うだけで、年に22億円が入るのかと凡人の頭は変な方にめぐる。前夜は、すぐ近くまで来たときに道ばたで見つけた下のRelai du Mont(MSミシェルへの中継点)というひなびたホテルに泊まった。飲み物やフルコースのディナーと朝食付きで一人税込6000円ちょっとであった。
 寝室の窓からは遠くにモンサンミシェルがかすかに見え、どこまで続いているのか分からないほどの庭には色とりどりのバラや山のようなアジサイが満開で、朝夕の涼しい空気の中を散歩していると独特の旅情を感じさせる。いわゆるヨーロッパのcontinental
breakfastというのは、イギリスやアメリカと違ってパンにバターとジャムをぬりコーヒーやジュースで流し込むだけの簡素なものだが、
寝室の窓からは遠くにモンサンミシェルがかすかに見え、どこまで続いているのか分からないほどの庭には色とりどりのバラや山のようなアジサイが満開で、朝夕の涼しい空気の中を散歩していると独特の旅情を感じさせる。いわゆるヨーロッパのcontinental
breakfastというのは、イギリスやアメリカと違ってパンにバターとジャムをぬりコーヒーやジュースで流し込むだけの簡素なものだが、 それは当然という気もする。ワインなどで満腹感を麻痺させて、これでもかこれでもかと次々に現れるフルコースのフランス料理それもゴッテリした自慢のチーズやアップルパイなどのデザートまでたいらげたあとで、翌日の朝まで重い朝食をとる元気はさすがフランス人にもないのだろう。でも美しい庭の花々に囲まれて、優雅で粋な雰囲気の中で、田舎の素朴な手作りの料理をどんどん出されると知らず知らずに満腹を通り越して食べてしまう。
それは当然という気もする。ワインなどで満腹感を麻痺させて、これでもかこれでもかと次々に現れるフルコースのフランス料理それもゴッテリした自慢のチーズやアップルパイなどのデザートまでたいらげたあとで、翌日の朝まで重い朝食をとる元気はさすがフランス人にもないのだろう。でも美しい庭の花々に囲まれて、優雅で粋な雰囲気の中で、田舎の素朴な手作りの料理をどんどん出されると知らず知らずに満腹を通り越して食べてしまう。ロワール河の夕日をAmboiseのお城(1番上の写真)のすぐ近くのホテルのベランダから撮ったのがこの写真
 である。この日はフランス北西部の海岸から、フランス中部のAmboiseまで500キロくらい進んで、6時頃やっと着いてすぐにお城を見学して、ホテル探しを始めたが、河をさかのぼって少しでも次のお城の近くに...と思ったのが間違いで、なかなか見つからず、月曜日なのにどこへ行ってもcomplet(空き室なし)と言われたり、書いてあったりで困ってしまった。このあたりはcaveという看板が目につくのだが、どうも葡萄酒の蔵元が、森の中の別荘のようなホテルを経営していて、フランス人には人気があるらしい。仕方がないのでまたAmboiseまで戻って、お城の近くをあたったら、いいところが見つかった。ホッとした。朝食付きで一人3300円程度であった。
である。この日はフランス北西部の海岸から、フランス中部のAmboiseまで500キロくらい進んで、6時頃やっと着いてすぐにお城を見学して、ホテル探しを始めたが、河をさかのぼって少しでも次のお城の近くに...と思ったのが間違いで、なかなか見つからず、月曜日なのにどこへ行ってもcomplet(空き室なし)と言われたり、書いてあったりで困ってしまった。このあたりはcaveという看板が目につくのだが、どうも葡萄酒の蔵元が、森の中の別荘のようなホテルを経営していて、フランス人には人気があるらしい。仕方がないのでまたAmboiseまで戻って、お城の近くをあたったら、いいところが見つかった。ホッとした。朝食付きで一人3300円程度であった。それにしても、フランスをドライブしていると、砂漠のような荒れた土地にオリーブの木しか育たないスペイン
 の中部などと比べて、フランスの国土は何と豊かなのかと思う。ほとんど全土が金色の麦か、緑のとおもろこし、そうでなかったら一面のヒマワリ畑。ときどき牧草地が現れて、刈りとっとものを大きなロール状にして置いてある。悦子がMake
hay while the sun shines.だね...と言う。Herzで借
の中部などと比べて、フランスの国土は何と豊かなのかと思う。ほとんど全土が金色の麦か、緑のとおもろこし、そうでなかったら一面のヒマワリ畑。ときどき牧草地が現れて、刈りとっとものを大きなロール状にして置いてある。悦子がMake
hay while the sun shines.だね...と言う。Herzで借 りたこのフランス製のプジョーはまだ2000キロしか走っていない新車で、マニュアル車ではあるけどヨーロッパ車にはめずらしく冷房付きで、とても調子がいい。でも暑いなあと思っていると上の写真のようなきれいな並木道が自然に現れて木陰を提供してくれ、日本では考えられないような牧歌的なドライブが続く。ただここは高速道路ではない普通の道なので、時速制限は110キロ。慣れない右側通行もそろそろ身についてきた。しかし交差点のロータリー(rondpoint)(写真)だけはイギリスなどのroundaboutと同じで
りたこのフランス製のプジョーはまだ2000キロしか走っていない新車で、マニュアル車ではあるけどヨーロッパ車にはめずらしく冷房付きで、とても調子がいい。でも暑いなあと思っていると上の写真のようなきれいな並木道が自然に現れて木陰を提供してくれ、日本では考えられないような牧歌的なドライブが続く。ただここは高速道路ではない普通の道なので、時速制限は110キロ。慣れない右側通行もそろそろ身についてきた。しかし交差点のロータリー(rondpoint)(写真)だけはイギリスなどのroundaboutと同じで 、気を使う。下の写真のようにかなり大きな築山の周りを、(右側通行だから)時計と反対の方向にまわり、もし左から車が来れば譲りながら、どこかで右に折れる。ここで間違えて曲がると、またUターンしてきて、同じことを繰り返すことになる。rondpointの標識が前もって出てきたときに、いくつ目で右折するかを見ておいて、数えていくわけだし、写真のように行き先を書いた標識がたく
さん並んでいる場合が多いのだが、スピードとの兼ね合いで、素早く確認して安全に曲がる必要がある。この点でも浩がそばで地図を見ながらナビゲーターになってくれたのは大いに助かった。一人で運転しながら地理を考え、左右の車に気を使い、慣れない言葉の標識を確かめながら、素早く行動するのは大変だからだ。
、気を使う。下の写真のようにかなり大きな築山の周りを、(右側通行だから)時計と反対の方向にまわり、もし左から車が来れば譲りながら、どこかで右に折れる。ここで間違えて曲がると、またUターンしてきて、同じことを繰り返すことになる。rondpointの標識が前もって出てきたときに、いくつ目で右折するかを見ておいて、数えていくわけだし、写真のように行き先を書いた標識がたく
さん並んでいる場合が多いのだが、スピードとの兼ね合いで、素早く確認して安全に曲がる必要がある。この点でも浩がそばで地図を見ながらナビゲーターになってくれたのは大いに助かった。一人で運転しながら地理を考え、左右の車に気を使い、慣れない言葉の標識を確かめながら、素早く行動するのは大変だからだ。ガソリン(essence)を自分で入れるのもすっかり身につけた。sans plomb(無鉛《unleadedという英語の表示はない》)と書かれた標識を確かめて、ノズルを車に突っ込み、引き金を押さえながら自動的に止まるのを待ち、給油の機械の番号を覚えておいてcashier(仏caissier)で払うのだが、フランス人は人を信用するというのか
 、おそろしく商売気がないようにも見える。払わずに行ってしまっても分からないような感じの応対ぶりである。これは高速道路のサービスエリア(写真)のカフェテリア式スナックでもそうで、日本なら品物と交換に支払う癖がついているものだが、渡された料理を、伝票も持たずにゆっくりと席へ持っていって食べ、支払いの列を作って、そこで口で申告したものを払って去る。こういう場合でもフランス語が出来ないので、英語で通すわけだが、愛想良く応対してくれて、特に不便さは感じない。
、おそろしく商売気がないようにも見える。払わずに行ってしまっても分からないような感じの応対ぶりである。これは高速道路のサービスエリア(写真)のカフェテリア式スナックでもそうで、日本なら品物と交換に支払う癖がついているものだが、渡された料理を、伝票も持たずにゆっくりと席へ持っていって食べ、支払いの列を作って、そこで口で申告したものを払って去る。こういう場合でもフランス語が出来ないので、英語で通すわけだが、愛想良く応対してくれて、特に不便さは感じない。 城は、普通山や丘の上にあり、周りからの侵入を防ぐが、シノンソー(Chenonceaux)城は河の真ん中に建てられて両岸への橋を跳ね橋にして自分を守るように作られているので、水
城は、普通山や丘の上にあり、周りからの侵入を防ぐが、シノンソー(Chenonceaux)城は河の真ん中に建てられて両岸への橋を跳ね橋にして自分を守るように作られているので、水 に映る姿が美しい。ゴシックとは違うルネッサンス風の柔らかい明るい雰囲気を持つ上に、平地に作られているので、両岸の庭が広く、幾何学模様のきちんとした線を基調として鮮やかな色の花々を緑の背景の中に配置してあり、女性的な優雅な城である。ママが浩に「新婚旅行ではここに来なさいよ」とさかんに勧めていた。 この城への入り口の長い並木道が印象的だ。映画「第三の男」のラストシーンを思い出させるので、つい一人でトボトボと歩きたくなったママ、やはり途中でわれに返って振り向いてしまった。《右の上につづく》←ここをクリック
に映る姿が美しい。ゴシックとは違うルネッサンス風の柔らかい明るい雰囲気を持つ上に、平地に作られているので、両岸の庭が広く、幾何学模様のきちんとした線を基調として鮮やかな色の花々を緑の背景の中に配置してあり、女性的な優雅な城である。ママが浩に「新婚旅行ではここに来なさいよ」とさかんに勧めていた。 この城への入り口の長い並木道が印象的だ。映画「第三の男」のラストシーンを思い出させるので、つい一人でトボトボと歩きたくなったママ、やはり途中でわれに返って振り向いてしまった。《右の上につづく》←ここをクリック《クレイム・コラム》
アエロ・フロート: 安さの秘密?
いったんロビーに出ても、その時の係員が指示した範囲だけしか動くことを許されない。今回は土産物屋が並ぶ一角だけが行動範囲に指示された。その意図は見え見えだが、誰も土産など買わない。そこで帰りの飛行機便のコンファームするために、してされていない方向にあるアエロフロートのカウンターへ行こうとしたら、つかまった。押し問答の末、係りの女性が付き添ってカウンターまで来たが、ここでまた面倒がられて拒否された。同じことを前回試みて、その時は問題なくできているのである。つまり、係りの人の気まぐれに、お客は振り回されるというのが今までのロシアの体制であって、この子役人根性がロシアをつぶしたのではないかと思いたくなる。
帰りの便でモスクワを出たのは夜の8時頃だったかと思うけど、飛行機が上昇すると、まもなく日暮れのような感じになった。しかし夏の北半球の北方ではずっと日が沈まず、写真の夕焼けのような状態がほとんど一晩中続き、これが結構きれいに見えた。。
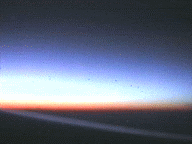 しかし夕食が終わると消灯になり、飛行機の電気は一斉に消えた。これと同時に窓のシャッターは一応下ろすようアナウンスはあった。だが、夕焼けがめずらしくきれいなので人の迷惑にならない程度に少しシャッターを細く開けて眺めていると、アエロフロートのスチュワデスはつかつかと近づいてものも言わずにいきなり人の前に手を出してガチャと閉めて行ってしまった。英語も一応しゃべれるのに、ひとことが出ない。これがロシアの客扱いの基本なのだろう。そしてそのために他の航空会社の半額程度の運賃に下げても十分お客が集まらず、機内食のメニューばかりきれいに印刷したり、機内スリッパを配ったりしてみても帳消しになり、その事情を知っていて、それを不愉快には思ってはいても、安さを評価して利用する我々のような人間だけのための航空会社にな
っているのだろう。
しかし夕食が終わると消灯になり、飛行機の電気は一斉に消えた。これと同時に窓のシャッターは一応下ろすようアナウンスはあった。だが、夕焼けがめずらしくきれいなので人の迷惑にならない程度に少しシャッターを細く開けて眺めていると、アエロフロートのスチュワデスはつかつかと近づいてものも言わずにいきなり人の前に手を出してガチャと閉めて行ってしまった。英語も一応しゃべれるのに、ひとことが出ない。これがロシアの客扱いの基本なのだろう。そしてそのために他の航空会社の半額程度の運賃に下げても十分お客が集まらず、機内食のメニューばかりきれいに印刷したり、機内スリッパを配ったりしてみても帳消しになり、その事情を知っていて、それを不愉快には思ってはいても、安さを評価して利用する我々のような人間だけのための航空会社にな
っているのだろう。スイスからイタリアへ
 快適そのものだった。スイスへの国境もお金を替えて"Japonais?"と聞かれるだけの簡単なもの。ただ、99年度中有効な有料道路通行証のようなものを全面ガラスに貼られて4000円くらい取られる。2,3日しか道路を利用しないのに1年分取られるのは分が悪いと思いつつも、安いのに驚く。ジュネーブからレマン湖で一休みしてローザンヌを見て、スイス南西部の町シオン(Sion)へ行く。緑の山の斜面全体に色とりどりのきれいな家が点在し、スイスらしい風景が続く。
快適そのものだった。スイスへの国境もお金を替えて"Japonais?"と聞かれるだけの簡単なもの。ただ、99年度中有効な有料道路通行証のようなものを全面ガラスに貼られて4000円くらい取られる。2,3日しか道路を利用しないのに1年分取られるのは分が悪いと思いつつも、安いのに驚く。ジュネーブからレマン湖で一休みしてローザンヌを見て、スイス南西部の町シオン(Sion)へ行く。緑の山の斜面全体に色とりどりのきれいな家が点在し、スイスらしい風景が続く。シオンはローザンヌからアルプスのシンプロン峠を越えてイタリアのミラノを結ぶ鉄道と道路の中間点でアルプスの麓のローヌ河に沿った山の中の町だ。実は我々はレマン湖沿いにあるはずのシヨン城(Seyon)に行こうとして、スイスで道を聞いたらシオンを間違えて教えられて、うかつにもそこへ来てしまったことに、あとになって気づいたという始末。
 でも来てみたら町の入り口の見上げるような崖っぷちに廃墟のような城がそびえ立ち、登ってみると13世紀頃の僧侶の信仰の中心であった素朴な聖堂がその頂上にあった。上からはシオンの町が緑の山々に囲まれて眼下に広がり、スイスらしい風景を堪能することができた。この写真はその聖堂のそばにあった小さなチャペル。背景には煉瓦の城壁の残りが山全体を貫くように走り、陸続きの国の厳しさを示しているようだ。
でも来てみたら町の入り口の見上げるような崖っぷちに廃墟のような城がそびえ立ち、登ってみると13世紀頃の僧侶の信仰の中心であった素朴な聖堂がその頂上にあった。上からはシオンの町が緑の山々に囲まれて眼下に広がり、スイスらしい風景を堪能することができた。この写真はその聖堂のそばにあった小さなチャペル。背景には煉瓦の城壁の残りが山全体を貫くように走り、陸続きの国の厳しさを示しているようだ。アルプス越えはシンプロン峠を越えてミラノへの道を取った。急勾配のヘアピンカーブの連続でさすがのプジョーの
 新車もセカンドまで落としてあえぎあえぎ登っていく瞬間もあった。標高も2006mになり、周りは霧で見通しが立たない中で、霧の中に、すぐそばの残雪が見え隠れする。かと思えばすぐにトンネルに突っ込む。前をのろのろと進むトラックを追い抜くほどの巾はない。途中、ものすごい岩盤が垂直にそそり立つ峡谷に記念碑が建っていて、ここを切り開いた先駆者の功績を讃えていた。
新車もセカンドまで落としてあえぎあえぎ登っていく瞬間もあった。標高も2006mになり、周りは霧で見通しが立たない中で、霧の中に、すぐそばの残雪が見え隠れする。かと思えばすぐにトンネルに突っ込む。前をのろのろと進むトラックを追い抜くほどの巾はない。途中、ものすごい岩盤が垂直にそそり立つ峡谷に記念碑が建っていて、ここを切り開いた先駆者の功績を讃えていた。 毎年10月から4月までは雪のため通行不能で、下を20キロにわたって貫く鉄道のシンプロントンネルで車を運ぶという。だから山小屋のようなイタリアの国境が見えたときはホッとした。そしてイタリアに入ったとたん空が真っ青になり太陽が照りつけ始めた。さすが地中海の国だ。
毎年10月から4月までは雪のため通行不能で、下を20キロにわたって貫く鉄道のシンプロントンネルで車を運ぶという。だから山小屋のようなイタリアの国境が見えたときはホッとした。そしてイタリアに入ったとたん空が真っ青になり太陽が照りつけ始めた。さすが地中海の国だ。ミラノ市街に入ったとたん車の運転に自身がなくなった。乱暴な運転の車の間をぬって、なんとか駐車して、中国料理店に入った。久しぶりに白い
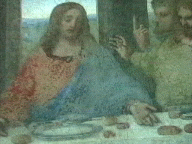 ご飯とシーフードにありついた。そして「最後の晩餐」を見た。ホテルのオヤジは「予約してなきゃ無理だよ」というのをおしてサンタマリア・デル・グラッツェ教会についたのは午後6時ちょっと前。うまい具合に10人くらいが列を作っているだけ。15分くらい待っただけでなんとか、修復後公開されてまだ2ヶ月の名画に接することができた。この写真はビデオでキリストの部分を拡大して写したものだが、ここからも分かるように、全体として教科書などに出ているものより大きいし明るい絵だという感じがする。絵の保存のため1回に入れる人数を20人くらいに制限しているけど、フラッシュをたかなければ、カメラもOKだった。
ご飯とシーフードにありついた。そして「最後の晩餐」を見た。ホテルのオヤジは「予約してなきゃ無理だよ」というのをおしてサンタマリア・デル・グラッツェ教会についたのは午後6時ちょっと前。うまい具合に10人くらいが列を作っているだけ。15分くらい待っただけでなんとか、修復後公開されてまだ2ヶ月の名画に接することができた。この写真はビデオでキリストの部分を拡大して写したものだが、ここからも分かるように、全体として教科書などに出ているものより大きいし明るい絵だという感じがする。絵の保存のため1回に入れる人数を20人くらいに制限しているけど、フラッシュをたかなければ、カメラもOKだった。ヴェネチアは全体が文化財のような小さな島なので、島の入り口に写真のような
 巨大な駐車ビルがあって、島を出て行くまで預かるように出来ている。そこからは約1000円払うと24時間何回でも乗れる水上バスの切符を買い、ダウンタウンへと向かう。船と足以外は一切使えない世界なので平和である。骨董品のようなカラフルな名建築の
巨大な駐車ビルがあって、島を出て行くまで預かるように出来ている。そこからは約1000円払うと24時間何回でも乗れる水上バスの切符を買い、ダウンタウンへと向かう。船と足以外は一切使えない世界なので平和である。骨董品のようなカラフルな名建築の 中を船でゆっくり進むと思わずうっとりしてしまう。水上バスは、この黄色い2本の線のある船のような駅をうまくつないでいく。小さな水路はゴンドラで行くしかないが、値段が高いので敬遠した。しかし路地から見ていると、ゴンドラもいろいろ工夫されていて、この写
中を船でゆっくり進むと思わずうっとりしてしまう。水上バスは、この黄色い2本の線のある船のような駅をうまくつないでいく。小さな水路はゴンドラで行くしかないが、値段が高いので敬遠した。しかし路地から見ていると、ゴンドラもいろいろ工夫されていて、この写 真のようにアコーディオンでイタリア民謡を奏でながら、ムードを作っているものもあった。アカデミア美術館を出たところで、その晩のバロック音楽会の切符を売っていたので一人2000円前後で買った。中世の建築群の醸し出す雰囲気の中で、18世紀の衣装に身を包んだ演奏
者達が18世紀の音楽を奏でれば、そこにいる人は、身も心もその世界へと誘われていく。Rondo
Venezianoという楽団だったが、モーツァアルトの歌劇のアリアやヴィヴァルディを1時間以上以上にわたって演じてくれた。イムジチなどの名楽団を生み出したお国柄だけあってすばらしいひとときを楽しませてくれた。
真のようにアコーディオンでイタリア民謡を奏でながら、ムードを作っているものもあった。アカデミア美術館を出たところで、その晩のバロック音楽会の切符を売っていたので一人2000円前後で買った。中世の建築群の醸し出す雰囲気の中で、18世紀の衣装に身を包んだ演奏
者達が18世紀の音楽を奏でれば、そこにいる人は、身も心もその世界へと誘われていく。Rondo
Venezianoという楽団だったが、モーツァアルトの歌劇のアリアやヴィヴァルディを1時間以上以上にわたって演じてくれた。イムジチなどの名楽団を生み出したお国柄だけあってすばらしいひとときを楽しませてくれた。フィレンツェはたまたま日曜日であった。私たちはキリスト教徒ではないが、好奇心から、ドウォモと呼ばれる13世紀の
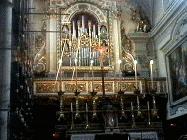 大聖堂で行われたミサに最初から最後まで参加してみた。内部で高くそびえるアーチの天井を支える大理石の巨大な柱、薄暗い堂の中にステンドグラスからまばゆいばかりの彩り豊かな光が差し込む中に、荘厳な音楽が流れ、舞台装置は満点だ。イタリア語ですべてが進められるので内容を
大聖堂で行われたミサに最初から最後まで参加してみた。内部で高くそびえるアーチの天井を支える大理石の巨大な柱、薄暗い堂の中にステンドグラスからまばゆいばかりの彩り豊かな光が差し込む中に、荘厳な音楽が流れ、舞台装置は満点だ。イタリア語ですべてが進められるので内容を 具体的につかむことは難しいが、お説教だと内容は変わりばえがしないことだろう。牧師の説教と手元に配られている楽譜を見ながら賛美歌の斉唱を2,3回繰り返した後で、参列者の中から一人の老紳士が説教台に向かい、何か体験談のようなものを語り始めた様子だった。するとまた別の参列者の女性が甲高い声で自分の意見か、経験を語っているようで一般の人も次々に発言できる和やかなミサであった。型どおりお布施の入れ物がまわってきたので我々も少額のお金を入れた。そのあとで突然周りの人たちが私たちに握手を求めてきたので、いろ
いろな人と握手を交わすことになった。見るとまわり中でお互いに同胞であ
具体的につかむことは難しいが、お説教だと内容は変わりばえがしないことだろう。牧師の説教と手元に配られている楽譜を見ながら賛美歌の斉唱を2,3回繰り返した後で、参列者の中から一人の老紳士が説教台に向かい、何か体験談のようなものを語り始めた様子だった。するとまた別の参列者の女性が甲高い声で自分の意見か、経験を語っているようで一般の人も次々に発言できる和やかなミサであった。型どおりお布施の入れ物がまわってきたので我々も少額のお金を入れた。そのあとで突然周りの人たちが私たちに握手を求めてきたので、いろ
いろな人と握手を交わすことになった。見るとまわり中でお互いに同胞であ ることを再確認するかのように、笑顔で手を取り合っていた。この骨董品で出来たような町の人たちと何か気持ちが通い合ったような感じがした瞬間であった。外へ出てみると牧師が町の人と気軽に話している場面にぶっつかった。やはり教会はまだ大切な機能を果たしているのかもしれない。でも、参列者の中に若者は少なかった。
ることを再確認するかのように、笑顔で手を取り合っていた。この骨董品で出来たような町の人たちと何か気持ちが通い合ったような感じがした瞬間であった。外へ出てみると牧師が町の人と気軽に話している場面にぶっつかった。やはり教会はまだ大切な機能を果たしているのかもしれない。でも、参列者の中に若者は少なかった。また、下右の写真はミケランジェロのダビデ像の前で男前を張り合っている(?)浩君だが、
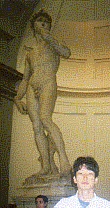 このアカデミア美術館のあるフィレンツェは町全体が美術館みたいで重々しい雰囲気を漂わせるところだ。その美術館の直前に下のようなコミカルなとぼけた像が
このアカデミア美術館のあるフィレンツェは町全体が美術館みたいで重々しい雰囲気を漂わせるところだ。その美術館の直前に下のようなコミカルなとぼけた像が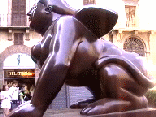 並んでいて少しホッさせてくれる。こういうバランスも時には息抜きに必要かもしれない。
フィレンツェからローマへ行く途中で、ピサに寄った。例の斜塔を見るためである。
並んでいて少しホッさせてくれる。こういうバランスも時には息抜きに必要かもしれない。
フィレンツェからローマへ行く途中で、ピサに寄った。例の斜塔を見るためである。 確かに傾きすぎて危険になり、5階あたりの高さのところで金属板を張り巡らし、太いワイヤーで反対側から引っ張って倒壊をやっと免れている感じだ。右のような写真を撮るとき、皆、下から塔を支えるような格好をして写ることがはやっているが、倒壊を防ぐのに何のご利益もないようだ。
確かに傾きすぎて危険になり、5階あたりの高さのところで金属板を張り巡らし、太いワイヤーで反対側から引っ張って倒壊をやっと免れている感じだ。右のような写真を撮るとき、皆、下から塔を支えるような格好をして写ることがはやっているが、倒壊を防ぐのに何のご利益もないようだ。ピサからローマまでの道は地中海に沿って、
 まさに太陽の道であった。大都会が近いのに、海岸に立つと水はきれいであった。おばあさんがぼんやりと海岸のパラソルの下で座ってじっと海を眺めている。泳ぐ人、サーフィンを持ち込む人、船を出して釣りに行く人,,,,ローマ人のバカンスの場所だった。
まさに太陽の道であった。大都会が近いのに、海岸に立つと水はきれいであった。おばあさんがぼんやりと海岸のパラソルの下で座ってじっと海を眺めている。泳ぐ人、サーフィンを持ち込む人、船を出して釣りに行く人,,,,ローマ人のバカンスの場所だった。 「ローマの休日」は暑さとの戦いであった。コロッセオは夕方7時の閉館10分前に駆け込み、混雑のない平和な闘技場を見ることができた。しかし翌日はヴァチカンの大天蓋の上まで狭いラセン階段を登り、システィー
 ナ礼拝堂から、スペイン広場、トレビの泉、真実の口などヘップバーンが新聞記者と動いたのとほとんど同じコース!でも最後のカラカラ浴場のあとは文字通りノドがカラカラで、丁度スイカの切り売りをしている露店のまえに皆で座り込んだ。
ナ礼拝堂から、スペイン広場、トレビの泉、真実の口などヘップバーンが新聞記者と動いたのとほとんど同じコース!でも最後のカラカラ浴場のあとは文字通りノドがカラカラで、丁度スイカの切り売りをしている露店のまえに皆で座り込んだ。 それにしても大昔の遺産に囲まれて生きている人たちが頼りにしているのは下のような普通の市場で、アメ横と同じ感じの露店が軒を連ねる場所には親しみがあり、本当の生活があった。
それにしても大昔の遺産に囲まれて生きている人たちが頼りにしているのは下のような普通の市場で、アメ横と同じ感じの露店が軒を連ねる場所には親しみがあり、本当の生活があった。