
ヨーロッパ大陸つまりギリシャ本土からは狭い海峡を隔てているだけで、西側にはイタリアとすぐ海でつながっている環境は、ここが地中海の楽園であるがゆえに、外国からの侵略の餌食にされてきた歴史がある。古くは9世紀にビザンチ ン帝国の一部に組み入れられ、ペロポネソス半島中部のミストラはその中心的役割を果たした。その後トルコに占領されたり、イタリアのヴェネチア共和国の属領になったり、18世紀末にはロシア・トルコ軍に攻略され、ナポレオンの進攻でフランスの属国になったこともある。その後パリ条約でイギリスの統治下に入り、第2次大戦でもイタリアやドイツの占領にあっていて、本当に開放されたのはつい50年前のことだ。このあたりの状況を、ケファロニア島を舞台に、痛快な筆致で冷徹に描き出したのが、「コレリ大尉のマンドリン」という小説で、これはイギリスでベストセラーになり映画にもなった。周辺民族の闖入による四面楚歌の中で暮らすことには慣れているようで、今でも古い城壁の類がやたらに目に付く。ペロポネソス半島は島ではないが、その南端マニ地方では、一軒一軒の民家が、分厚い石壁で出来た直方体の城砦の作りになっていて、異様な雰囲気を今に伝える。
ン帝国の一部に組み入れられ、ペロポネソス半島中部のミストラはその中心的役割を果たした。その後トルコに占領されたり、イタリアのヴェネチア共和国の属領になったり、18世紀末にはロシア・トルコ軍に攻略され、ナポレオンの進攻でフランスの属国になったこともある。その後パリ条約でイギリスの統治下に入り、第2次大戦でもイタリアやドイツの占領にあっていて、本当に開放されたのはつい50年前のことだ。このあたりの状況を、ケファロニア島を舞台に、痛快な筆致で冷徹に描き出したのが、「コレリ大尉のマンドリン」という小説で、これはイギリスでベストセラーになり映画にもなった。周辺民族の闖入による四面楚歌の中で暮らすことには慣れているようで、今でも古い城壁の類がやたらに目に付く。ペロポネソス半島は島ではないが、その南端マニ地方では、一軒一軒の民家が、分厚い石壁で出来た直方体の城砦の作りになっていて、異様な雰囲気を今に伝える。
イサカ(イタケ)島はレフカダ島の東部、ニドリからフェリーで1時間くらいのところにある小さな島だ。ギリシャは海の国だけあって、小さな島へ通うフェリーも大型できれいだ。その船が紺碧の鏡のように静かな内海をすべるように進む。静かなエンジンの音を聞きながら、空と海の青を突き抜けていく船の甲板で白いペンキの新しい欄干にもたれて、海風にあたっているときの爽快感はこの旅の最も強い印象のひとつだった。離れていくレフカダ島・ニドリの港のヨットが小さくなって、船はしばらく島に沿って進む。なだらかな丘の斜面に、白壁と茶色の屋根をした家が強い陽を受けてポツリポツリと光っている。赤茶けた崖が地肌を見せてそのまま海に落ち込んでいるところでは、その下の海面に黒味がかった影が揺らぐ。時に海風で飛ばされそうになる帽子を押さえて、思わずポケットからビデオを取り出す。ハーンも機会があると母によく連れて行ってもらったというが、たぶんこんな景色になじんでいたことだろう。ちょっと離れたシートで編み物をしている家内と私以外に日本人は誰もいない。アメリ
 カ人らしい年配の夫婦が手前のデッキに降りていった。船首に向かったベンチに腰をおろして、言葉を交わすこともなくうっとりしている。右前方から真っ白の船体のヨットが来るのが見える。フェリーの甲高い汽笛がこの静けさを破って、目を覚まさせてくれる。ヨットが右舷をすれ違う。茶色に日焼けした男がヨットの帆綱を握り、手を振っている。真っ白な船体が、真っ青な海の上で太陽を受けてまぶしい。日本では薄暗い、うっとうしい梅雨の最中の今、地球の反対側の人々は毎年この爽快な気候を満喫しているというこの不公平はいったい何なのだ。
カ人らしい年配の夫婦が手前のデッキに降りていった。船首に向かったベンチに腰をおろして、言葉を交わすこともなくうっとりしている。右前方から真っ白の船体のヨットが来るのが見える。フェリーの甲高い汽笛がこの静けさを破って、目を覚まさせてくれる。ヨットが右舷をすれ違う。茶色に日焼けした男がヨットの帆綱を握り、手を振っている。真っ白な船体が、真っ青な海の上で太陽を受けてまぶしい。日本では薄暗い、うっとうしい梅雨の最中の今、地球の反対側の人々は毎年この爽快な気候を満喫しているというこの不公平はいったい何なのだ。
などと思っていると、船はいつの間にかイサカ島の馬蹄形の入り江の脇に近づいている。向こうの山の中腹に道路を切り開いたらしい斜めの線が入っ ている。入り江の奥には、すぐ後ろに山を控えた海沿いの狭い場所に、家並みがこちらに向かって並んでいるのが見える。後ろの山の中腹にも点々と白壁の家がオリーブの林の中に浮き出ている。フェリーは先頭の鉄板のブリッジを前に半分倒しながら、ゆっくりと接岸した。これがホメロスが「オデュッセイア」の中でオデッセウスの故郷として大ロマンを展開した舞台に想定された島である。トロイア戦争に勝ったオデッセウスが、10年もかけて、この故郷を思い、数々の冒険の後、妻のペネロペと再会することになるのがこの島ということになっている。島自体が小さいこともあり、他の島と違って、道が狭いし曲がりくねっていて、運転するのに気が疲れる。ガソリンスタンドもオリーブの林に囲まれるようにして島に2つしかない。それでもFrikesという港から10分も車を進めると小さな丘の上のStavrosという村に出た。小さな幼稚園のような建物で学校の授業が行われている。はるか向こうに真っ青な入り江を望む小さな公園には松林に囲まれて「オデッセウス」の大きな銅像が立っている。口承伝承が元になって、ホメロスが自分の想像力を加えてまとめたのが「イリアス」や「オデュッセ
ている。入り江の奥には、すぐ後ろに山を控えた海沿いの狭い場所に、家並みがこちらに向かって並んでいるのが見える。後ろの山の中腹にも点々と白壁の家がオリーブの林の中に浮き出ている。フェリーは先頭の鉄板のブリッジを前に半分倒しながら、ゆっくりと接岸した。これがホメロスが「オデュッセイア」の中でオデッセウスの故郷として大ロマンを展開した舞台に想定された島である。トロイア戦争に勝ったオデッセウスが、10年もかけて、この故郷を思い、数々の冒険の後、妻のペネロペと再会することになるのがこの島ということになっている。島自体が小さいこともあり、他の島と違って、道が狭いし曲がりくねっていて、運転するのに気が疲れる。ガソリンスタンドもオリーブの林に囲まれるようにして島に2つしかない。それでもFrikesという港から10分も車を進めると小さな丘の上のStavrosという村に出た。小さな幼稚園のような建物で学校の授業が行われている。はるか向こうに真っ青な入り江を望む小さな公園には松林に囲まれて「オデッセウス」の大きな銅像が立っている。口承伝承が元になって、ホメロスが自分の想像力を加えてまとめたのが「イリアス」や「オデュッセ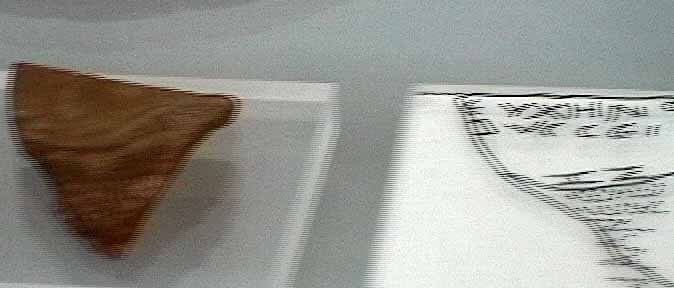 イア」だとも言われるので、事実と想像の境目がはっきりしないのかもしれないが、島の人にとってはオデッセウスは実在の人物なのだ。実際、Stavrosの小さな「考古学博物館」ではオデッセウスがつけていたという鎧の一部(写真左)が、そこに刻み込まれたOΔYC CE I(オデュッセイ)という文字とともに、展示されている。
イア」だとも言われるので、事実と想像の境目がはっきりしないのかもしれないが、島の人にとってはオデッセウスは実在の人物なのだ。実際、Stavrosの小さな「考古学博物館」ではオデッセウスがつけていたという鎧の一部(写真左)が、そこに刻み込まれたOΔYC CE I(オデュッセイ)という文字とともに、展示されている。
イサカ島は小さな島だが、その中央にちょっとした山がある。その頂上に通じる 道は、断崖を切り込むようにして作られていて、一応舗装されてはいるが、道幅が狭く、2台がすれ違うのは困難なくらいだ。でも、対向車に出会うことはほとんどない。しかし、断崖すれすれの道にもガードレールはほとんどなく、脇の岩壁もいたるところで崩れ落ちているし、道路はひびだらけ。だが、まわりは一面の青い海と空のパノラマを眼下に見渡すことができるので、ヒヤヒヤしながらもゆっくり車を走らせていく。かなりの数の急なヘアピン・カーブを何とか登りつめると、古い鐘楼のあるKatharaという修道院の門前に出た。人の気配はないが、めったに訪ねる人もいないのか、やせた犬が突然我々に向かって盛んに吠え始める。でも人が出てくる様子もない。脇のちょっと下がった丘の上でカラン、コロンという音がそよ風に乗って響いてくる。よく見ると、黒いヤギたちが水を飲もうとして首
道は、断崖を切り込むようにして作られていて、一応舗装されてはいるが、道幅が狭く、2台がすれ違うのは困難なくらいだ。でも、対向車に出会うことはほとんどない。しかし、断崖すれすれの道にもガードレールはほとんどなく、脇の岩壁もいたるところで崩れ落ちているし、道路はひびだらけ。だが、まわりは一面の青い海と空のパノラマを眼下に見渡すことができるので、ヒヤヒヤしながらもゆっくり車を走らせていく。かなりの数の急なヘアピン・カーブを何とか登りつめると、古い鐘楼のあるKatharaという修道院の門前に出た。人の気配はないが、めったに訪ねる人もいないのか、やせた犬が突然我々に向かって盛んに吠え始める。でも人が出てくる様子もない。脇のちょっと下がった丘の上でカラン、コロンという音がそよ風に乗って響いてくる。よく見ると、黒いヤギたちが水を飲もうとして首 につけられた鈴が鳴っている。静かだ。ほとんど360度見渡せるパノラマの一角には、はるか下方に張り出した半島の入り江の奥にイタケの町らしい集落が見える。この山すそに広がるオリーブとモミの木の樹林帯の中に白い城壁が崩れかかっている。青いインクを流したような一面の海に、青緑色のこぶのように大小の島々が浮き出しているのが見える。船があとに筋を残して浮かんでいる。修道院は手入れも行き届かないようで、壁は薄汚く、ひび割れている。石の十字架も中の鉄筋が錆びて露出し、荒涼としてはいるが、なんとなくこの大自然の中で調和しているのが不思議だ。こんなところに住むなんて、浮世離れした仙人の生活だなと思う。まさに修道院にはうってつけの場所だ。
につけられた鈴が鳴っている。静かだ。ほとんど360度見渡せるパノラマの一角には、はるか下方に張り出した半島の入り江の奥にイタケの町らしい集落が見える。この山すそに広がるオリーブとモミの木の樹林帯の中に白い城壁が崩れかかっている。青いインクを流したような一面の海に、青緑色のこぶのように大小の島々が浮き出しているのが見える。船があとに筋を残して浮かんでいる。修道院は手入れも行き届かないようで、壁は薄汚く、ひび割れている。石の十字架も中の鉄筋が錆びて露出し、荒涼としてはいるが、なんとなくこの大自然の中で調和しているのが不思議だ。こんなところに住むなんて、浮世離れした仙人の生活だなと思う。まさに修道院にはうってつけの場所だ。
Stavrosはこの島第2の規模とのことだったが、道路を挟んで数軒のタベルナとカフェが道端までテーブルをならべている以外には教会と学校と小さなスーパーがある程度だった。どこを見てもホテルの標識はないので、タベルナで尋ねてみたら、目の前にあるもう1軒の食堂の2階がホテルだという。実際行ってみるときれいな見晴らしのいい静かな部屋に案内された。冷房も冷蔵庫もテレビもついて2人で30ユーロ(4,100円)だという。申し分なかった。
 次の朝、10時に南のケファロニア島へ行くフェリーが出るというので、少し前にFrikesの岸壁に行った。そこには、ただ船着場のコンクリートがあるだけで、切符売り場などの建物は全くない。最初は誰もいなかったが、まもなくライトバンの車が来て、岸壁の淵に小さな移動式の机を持ち出し、切符を売り始める。乗用車は20ユーロ(2,800円)、その他に人間の乗船券が1人5ユーロ(690円)、2人で1,480円だから全部で4,300円くらい。まもなくどこからともなく、ぞろぞろ車が集まってくる。今日はかなり乗船する車が多い。アメリカ人を詰め込んだ観光バスや、食料品を載せた行商人の車、それに建築用の石材を満載したトラックも何台かある。フェリーは船首にしか開口部分がないので、すべて車はバックしながら乗船する。我々は早めに来ていたので、整理員の誘導で早く車を乗船させた。ホッとしてデッキでのんびりしていたら、デッキから下の車庫の状況を見ていたイギリス人らしい男が、「お前の車が障害になっているようなので、移動しなければならなくなるかも….」と言う。「人の車のことまでよく覚えている奴だな」と思いながら、下の車庫の方へ行ってみる。あとになって急に大型車が入ろうとして困っているようなので、整理員に申し出ると、とりあえず私の車を船外に出すことになった。混雑していたすべての車が何とか納まったのはいいが、私の車が1台だけ外に出ていて、再び入る余地がほとんどないように見えた。フェリーは1日に2本しかなく、この船をのがすと、夕方まで次の船はないことが頭をかすめた。家内もすでに船内にいるし…...などと思っていると、整理員も一生懸命、船首の突端のところに小さな場所を作ってくれて誘導してくれ、何とかギリギリで助かった。その間中、上のデッキに乗客が鈴なりになって身を乗り出して、この様子をかたずを呑んで見守ってくれていたようだ。私の車がうまく納まったときに、「観衆」から安堵の吐息が漏れたと、その状況を見ていた家内が話してくれた。しかし、これで私たちがここでは「外人」なのだということがよく分かった。まわりの人たちは皆大人だし、我々を仲間の一人として普通に扱おうとしてくれるのだが、東洋人は我々だけで目立ってしまうので、西洋人には特別な人間として記憶されてしまうようだ。それは日本に来る外国人が日本で感じるものと同じなのかもしれない。
次の朝、10時に南のケファロニア島へ行くフェリーが出るというので、少し前にFrikesの岸壁に行った。そこには、ただ船着場のコンクリートがあるだけで、切符売り場などの建物は全くない。最初は誰もいなかったが、まもなくライトバンの車が来て、岸壁の淵に小さな移動式の机を持ち出し、切符を売り始める。乗用車は20ユーロ(2,800円)、その他に人間の乗船券が1人5ユーロ(690円)、2人で1,480円だから全部で4,300円くらい。まもなくどこからともなく、ぞろぞろ車が集まってくる。今日はかなり乗船する車が多い。アメリカ人を詰め込んだ観光バスや、食料品を載せた行商人の車、それに建築用の石材を満載したトラックも何台かある。フェリーは船首にしか開口部分がないので、すべて車はバックしながら乗船する。我々は早めに来ていたので、整理員の誘導で早く車を乗船させた。ホッとしてデッキでのんびりしていたら、デッキから下の車庫の状況を見ていたイギリス人らしい男が、「お前の車が障害になっているようなので、移動しなければならなくなるかも….」と言う。「人の車のことまでよく覚えている奴だな」と思いながら、下の車庫の方へ行ってみる。あとになって急に大型車が入ろうとして困っているようなので、整理員に申し出ると、とりあえず私の車を船外に出すことになった。混雑していたすべての車が何とか納まったのはいいが、私の車が1台だけ外に出ていて、再び入る余地がほとんどないように見えた。フェリーは1日に2本しかなく、この船をのがすと、夕方まで次の船はないことが頭をかすめた。家内もすでに船内にいるし…...などと思っていると、整理員も一生懸命、船首の突端のところに小さな場所を作ってくれて誘導してくれ、何とかギリギリで助かった。その間中、上のデッキに乗客が鈴なりになって身を乗り出して、この様子をかたずを呑んで見守ってくれていたようだ。私の車がうまく納まったときに、「観衆」から安堵の吐息が漏れたと、その状況を見ていた家内が話してくれた。しかし、これで私たちがここでは「外人」なのだということがよく分かった。まわりの人たちは皆大人だし、我々を仲間の一人として普通に扱おうとしてくれるのだが、東洋人は我々だけで目立ってしまうので、西洋人には特別な人間として記憶されてしまうようだ。それは日本に来る外国人が日本で感じるものと同じなのかもしれない。
 「その透明度において、イオニア海の水は、他のどのような場所の空気と比べてもひけをとらない」と、どこかで読んだ記憶がある。高い屏風を三面鏡のように置いたようなそそりたつ崖の下に、三日月状に真っ白な砂を敷いたような海岸が広がり、その前にエメラルド色の海が望まれるような場所は、島のあちこちに見られるような気がする。近づいてみると、浅いところは波打つガラスを敷いたように透明で、底の玉砂利が小さな波を通してふらふらと形をゆがめている。少し深いところでは、水は明るい青色に変わり、底の石は白く光って見える。このような海岸でもひと気がないことが多く、強い日差しの下で、静かに打ち寄せる波の音だけがサラサラと聞こえる。遠くに目をやると、突き出た湾に沿って繁茂する緑が、下の海に写り、黒ずんだ影が小さく揺らぐ。遠くからは白い砂のように見えた波打ち際は、近寄ってみると、白の碁石のような玉砂利が黒や茶色の「碁石」と混ざり合って、まだら模様を作っている。
「その透明度において、イオニア海の水は、他のどのような場所の空気と比べてもひけをとらない」と、どこかで読んだ記憶がある。高い屏風を三面鏡のように置いたようなそそりたつ崖の下に、三日月状に真っ白な砂を敷いたような海岸が広がり、その前にエメラルド色の海が望まれるような場所は、島のあちこちに見られるような気がする。近づいてみると、浅いところは波打つガラスを敷いたように透明で、底の玉砂利が小さな波を通してふらふらと形をゆがめている。少し深いところでは、水は明るい青色に変わり、底の石は白く光って見える。このような海岸でもひと気がないことが多く、強い日差しの下で、静かに打ち寄せる波の音だけがサラサラと聞こえる。遠くに目をやると、突き出た湾に沿って繁茂する緑が、下の海に写り、黒ずんだ影が小さく揺らぐ。遠くからは白い砂のように見えた波打ち際は、近寄ってみると、白の碁石のような玉砂利が黒や茶色の「碁石」と混ざり合って、まだら模様を作っている。
この群島では一番南のザキントス島では、このような海岸には人がいっぱいになる。ギリシャの国旗のような白と青の 大きなビーチパラソルが海岸に平行して林立する。そこでは老いも若きもデッキチェアを並べて肌を焼く。この刺すようなまぶしいばかりの太陽光線はやけどをしないかと思うほどなのに、女性もトップレスで紫外線の沐浴だ。乳房が垂れ下がっているような年配の女性も実に堂々と歩いている。白い肌の若い女性の乳房が、赤みがかったリンゴを置いたように胸にくっついている。でも、パラソルや人間が占領しているのは海岸の波打ち際に寄ったところだけ。監視員のボランティアがいて、山側の半分の砂地には入らないように、入り口のところで一人一人に呼びかけている。砂地に差し込まれるパラソルの柄が、下に埋まっている海亀の卵を壊してしまい、海亀が産卵しに上がってこなくなったからだという。そのために全面立ち入り禁止にしている海岸もあるが、ギリシャ本土からのリゾート客が多いこの島では、ある程度の妥協が必要で、こんなことになったらしい。
大きなビーチパラソルが海岸に平行して林立する。そこでは老いも若きもデッキチェアを並べて肌を焼く。この刺すようなまぶしいばかりの太陽光線はやけどをしないかと思うほどなのに、女性もトップレスで紫外線の沐浴だ。乳房が垂れ下がっているような年配の女性も実に堂々と歩いている。白い肌の若い女性の乳房が、赤みがかったリンゴを置いたように胸にくっついている。でも、パラソルや人間が占領しているのは海岸の波打ち際に寄ったところだけ。監視員のボランティアがいて、山側の半分の砂地には入らないように、入り口のところで一人一人に呼びかけている。砂地に差し込まれるパラソルの柄が、下に埋まっている海亀の卵を壊してしまい、海亀が産卵しに上がってこなくなったからだという。そのために全面立ち入り禁止にしている海岸もあるが、ギリシャ本土からのリゾート客が多いこの島では、ある程度の妥協が必要で、こんなことになったらしい。
 ペロポネソス半島南端のVatheiaというところ海岸では、スイスからキャンピングカーで来たというスウェーデン人夫婦に会った。日曜以外は静かなそのビーチは、1軒のタベルナがあるほかはビーチパラソルすらない小さな入り江だったが、そこに1週間も滞在しているという。「スウェーデンは良いところだと言われているのになぜギリシャに?」と聞くと、北欧は雨ばかりで気が滅入るという。確かにこのまぶしいばかりの太陽が見せてくれる鮮やかな色と形の世界の洗礼を受けると、日本晴れの風景も、おぼろげにくすんだものになってしまうほどだ。我々もその景色のなかにある1軒のタベルナで「食べた」わけだが、最後に勘定書き(ギリシャ語でローカリアズモと教わっていたのでその語を使ってみた)を求め、お釣りの中からチップを出そうとすると、若いボーイはちょっと顔を赤らめて強く断った。この辺は自然だけでなく、人間も純粋なのだなあと改めて思った。
ペロポネソス半島南端のVatheiaというところ海岸では、スイスからキャンピングカーで来たというスウェーデン人夫婦に会った。日曜以外は静かなそのビーチは、1軒のタベルナがあるほかはビーチパラソルすらない小さな入り江だったが、そこに1週間も滞在しているという。「スウェーデンは良いところだと言われているのになぜギリシャに?」と聞くと、北欧は雨ばかりで気が滅入るという。確かにこのまぶしいばかりの太陽が見せてくれる鮮やかな色と形の世界の洗礼を受けると、日本晴れの風景も、おぼろげにくすんだものになってしまうほどだ。我々もその景色のなかにある1軒のタベルナで「食べた」わけだが、最後に勘定書き(ギリシャ語でローカリアズモと教わっていたのでその語を使ってみた)を求め、お釣りの中からチップを出そうとすると、若いボーイはちょっと顔を赤らめて強く断った。この辺は自然だけでなく、人間も純粋なのだなあと改めて思った。
ペロポネゾス半島の南方マニ半島への入り口に「ディロスの洞窟」というのがある。入場料一人 12ユーロ(1600円)はかなり高いなと思ったけど、すばらしい洞窟だった。洞窟全体が地底湖のようになっていて、半分水に浸かった細い迷路のような鍾乳石のトンネルを10人くらいのボートで静かに動き回る。船頭は周りのトンネルの壁を木の棒で押しながら舟を進ませる。天井や横壁は鍾乳石のモザイクだ。小さな鉛筆くらいの柱が無数に出ていてきれいな模様を作る。1500メートルも奥まで無数の迷路が縦横無尽に走る中を25分間も神秘的な世界を放浪させてくれるのだからあの入場料も高くないなと思った。さすがにこのあたりでも人気の場所のようで、多くの観光客がつめかけていた。列を作って待っている我々の前に数人のギリシャ人らしい人がいた。いざ乗るときに、お客を整理していた案内人が我々2人の日本人を、前のギリシャ人達より優先させてボートの一番前の席に案内した。悪いなと思いながらも我々は好意をすなおに受けた。順番を無視されたのに、そのギリシャ人たちには当然のような親切な表情があり、「はるばる遠くから来た日本人なのだから、我々の国をよく見てもらおう」というような感じが、案内人やその人たちの表情から読み取れた。イサカ島でフェリーに乗るときにも感じたが、ここでも我々が「外人」なのだということを実感した。
12ユーロ(1600円)はかなり高いなと思ったけど、すばらしい洞窟だった。洞窟全体が地底湖のようになっていて、半分水に浸かった細い迷路のような鍾乳石のトンネルを10人くらいのボートで静かに動き回る。船頭は周りのトンネルの壁を木の棒で押しながら舟を進ませる。天井や横壁は鍾乳石のモザイクだ。小さな鉛筆くらいの柱が無数に出ていてきれいな模様を作る。1500メートルも奥まで無数の迷路が縦横無尽に走る中を25分間も神秘的な世界を放浪させてくれるのだからあの入場料も高くないなと思った。さすがにこのあたりでも人気の場所のようで、多くの観光客がつめかけていた。列を作って待っている我々の前に数人のギリシャ人らしい人がいた。いざ乗るときに、お客を整理していた案内人が我々2人の日本人を、前のギリシャ人達より優先させてボートの一番前の席に案内した。悪いなと思いながらも我々は好意をすなおに受けた。順番を無視されたのに、そのギリシャ人たちには当然のような親切な表情があり、「はるばる遠くから来た日本人なのだから、我々の国をよく見てもらおう」というような感じが、案内人やその人たちの表情から読み取れた。イサカ島でフェリーに乗るときにも感じたが、ここでも我々が「外人」なのだということを実感した。
アテネの地下鉄の中心、シンタグマ駅の通路を歩いていたら、ギリシャ人がいきなり英語で話しかけてきた。「煎茶」と「番茶」はどう違うのかと言う。彼らには日本人、韓国人、中国人などの区別は難しいはずなのによく分かったなと思ったが、日本に来たこともあり、何となく親しみを感じたようだった。田舎道では、子供がじっと私たちの方を見ていたり、若者が通りすがりに、 我々に向かって親しみのある歓声をあげたり、道端の椅子に腰をおろしてボーッとしている老人も一瞬我々に顔をむけて見るようだった。道を聞くと例外なく一生懸命教えてくれる。英語が出来ない人に聞くと、ギリシャ語でまくし立てられる。こっちもIt’s Greek to me.(チンプンカンプンだよ)と言いたくなるが、身振り言語の助けを借りて、何とか分かったような気になる。
我々に向かって親しみのある歓声をあげたり、道端の椅子に腰をおろしてボーッとしている老人も一瞬我々に顔をむけて見るようだった。道を聞くと例外なく一生懸命教えてくれる。英語が出来ない人に聞くと、ギリシャ語でまくし立てられる。こっちもIt’s Greek to me.(チンプンカンプンだよ)と言いたくなるが、身振り言語の助けを借りて、何とか分かったような気になる。
奇妙なアルファベット(αβ)を使うギリシャ語は欧米の人たちにも恐怖心を与えているようで、ギリシャを個人で旅行するのは避けたい気持ちになるらしく、若い人を除いて彼らのほとんどは団体旅行で来る。日本人は海外旅行と言えば団体旅行で動き回ることは世界中で有名な事実で、我々が日本人なのに、欧米人でさえ団体で行く国を、個人で動いていることは奇異に写るらしい。ひと気のない美しい海岸でゆっくり風景に見とれているとき、背後の道路を、同じフェリーで一緒だった欧米人の観光バスが走りぬけていく。バスから手を振ってくれるので、笑顔で答える。そのときの彼らの何とも言えない表情が印象的であった。
実際、「外人」が下手でも、ギリシャ語を言おうとすると、ギリシャ人も悪い気はしないようなので、我々も覚えたばかりのギリシャ語の挨拶を、よく使ってみた。エフハリストウ(Ευχαρισω)=「ありがとう」と最後にアクセント置いて言うのはすぐ慣れた。必ず、笑顔と共に、パラカロ(Παρακαλω)「どういたしまして」と返ってきた。「おはよう」「こんちちは」のカリメラ(Καλημερα)も声をかけやすかった。ミケーネの遺跡に向かうとき、途中で道が分からなくなった。このときは、めずらしく家内が道を聞きに行った。英語で聞いたのに、答えはギリシャ語だったらしく、よく分からなかったが、その中に、ゼカ・レプタ(δεκα λεπτα)「(あと)10分」という部分が聞き取れたので、Ten minutes? と聞いたら、 Yes.が返ってきたと言う。彼女も、行く前に少しCDでギリシャ語を聞いていたので、何となく理解できたのだろう。挨拶以外にギリシャ語を聞き取れたことはほとんどなかったので、喜んでいた。
 しかし、ギリシャ人にとっても英語をしゃべることは就職の武器になるらしい。ザキントス島の、フロント1人のホテルで、きれいな若い女性がホテル番をしていた。英語が上手なので、「どこで勉強したの?」 と聞くと「ここで」という。すでに母親らしく、4歳くらいの女の子(写真右)を、客の居ないロビーで遊ばせな
しかし、ギリシャ人にとっても英語をしゃべることは就職の武器になるらしい。ザキントス島の、フロント1人のホテルで、きれいな若い女性がホテル番をしていた。英語が上手なので、「どこで勉強したの?」 と聞くと「ここで」という。すでに母親らしく、4歳くらいの女の子(写真右)を、客の居ないロビーで遊ばせな がら、仕事をしている。その日の夜、突然停電になった。内線は通じたので、フロントに電話したら、その女性が「これはこのホテルだけでなくて、あたり一帯なので、様子が分からない」と説明した。深夜になって、やっと電気がつき、やれやれと思ったが、今度はエアコンがつかない。また電話すると、まだ先ほどの女性がいて、「窓とエアコンは連動しているので、停電中に開いていた窓を閉めないとエアコンの電源が入らない」と、まるで、その部屋を見ているかのような答えが返ってきた。子供連れで、「外国語」を使いながら、深夜まで働いている母親はここにもいた。
がら、仕事をしている。その日の夜、突然停電になった。内線は通じたので、フロントに電話したら、その女性が「これはこのホテルだけでなくて、あたり一帯なので、様子が分からない」と説明した。深夜になって、やっと電気がつき、やれやれと思ったが、今度はエアコンがつかない。また電話すると、まだ先ほどの女性がいて、「窓とエアコンは連動しているので、停電中に開いていた窓を閉めないとエアコンの電源が入らない」と、まるで、その部屋を見ているかのような答えが返ってきた。子供連れで、「外国語」を使いながら、深夜まで働いている母親はここにもいた。
アテネの中心の一つ、オモニア広場から歩いて10分くらいのところのホテル(Hotel King Jason)で最初2泊した。アテネのホテルは多いので、インターネットで探して比較的安くてきれいなホームページから予約をしていた。それでも朝食つき2人で1泊67ユーロ(9,200円)であった。周りは崩れかかった土蔵のような家 が目に付き、決して優雅な環境ではなかったが、ホテルだけは割りにきれいな10階くらいのビルであった。「近くにうまいギリシャ料理の店がある」とホテルのボーイが言うので、行ってみた。ギリシャ人は10時ころにならないと夕食を食べないので、7時半では客は我々以外に誰もいない。でも営業はしている。驚いたことに、店の看板に「アレクサンダー大王」(メガス・アレクサンドロス=ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)と書かれている。シラク大統領を思わせる頭のはげたホリの深い顔の主人に名前の由来を尋ねると、自分の本名がアレクサンドロスだから、それにGreat(Μεγα?)を付けただけという。実際、戸口の上には巨大な茶色のアレクサンダー大王のイコンまで埋め込まれている。
が目に付き、決して優雅な環境ではなかったが、ホテルだけは割りにきれいな10階くらいのビルであった。「近くにうまいギリシャ料理の店がある」とホテルのボーイが言うので、行ってみた。ギリシャ人は10時ころにならないと夕食を食べないので、7時半では客は我々以外に誰もいない。でも営業はしている。驚いたことに、店の看板に「アレクサンダー大王」(メガス・アレクサンドロス=ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)と書かれている。シラク大統領を思わせる頭のはげたホリの深い顔の主人に名前の由来を尋ねると、自分の本名がアレクサンドロスだから、それにGreat(Μεγα?)を付けただけという。実際、戸口の上には巨大な茶色のアレクサンダー大王のイコンまで埋め込まれている。
さっそく有名なギリシャ料理、トマトの肉飯詰め(ドマテス・イエミステス)(7.5ユーロ[1,000円])を注文する。ひき肉とご飯を混ぜたようなものをトマトの中身をくりぬいたスペースに詰め込んで、オーブンで焼いたものと、ピーマンの中に同じも のを詰め込んだものの組み合わせだ。日本では、ピーマンの肉詰めはよくあるが、トマトはあまり煮て食べないのだが、これもアジな味だから帰国したら作ってみようかな....。前日の印象が悪くなかったので、翌日もほぼ同じ時間にその店を訪れた。今度はヤリいかを輪切りにしてゲソと共にカラッと揚げた「カラマリ」とタコの揚げ物にした。海の国だけあって、シーフードが豊富で、日本人の味覚と似ているのがいい。カラマリはその後方々で食べ、イカ供養をしなければならないほど私のお気に入りになった。2日連続で出かけたので、例のアレクサンダー大王氏もご機嫌で、サービスにご飯を出してくれたり、醤油やテリヤキソースをテーブルに置いてくれたり、最後にはスイカとウリのデザートまでタダでサービスしてくれた。「明日はいよいよレフカダ島へドライブに行くんだ」と言って店を出た。
のを詰め込んだものの組み合わせだ。日本では、ピーマンの肉詰めはよくあるが、トマトはあまり煮て食べないのだが、これもアジな味だから帰国したら作ってみようかな....。前日の印象が悪くなかったので、翌日もほぼ同じ時間にその店を訪れた。今度はヤリいかを輪切りにしてゲソと共にカラッと揚げた「カラマリ」とタコの揚げ物にした。海の国だけあって、シーフードが豊富で、日本人の味覚と似ているのがいい。カラマリはその後方々で食べ、イカ供養をしなければならないほど私のお気に入りになった。2日連続で出かけたので、例のアレクサンダー大王氏もご機嫌で、サービスにご飯を出してくれたり、醤油やテリヤキソースをテーブルに置いてくれたり、最後にはスイカとウリのデザートまでタダでサービスしてくれた。「明日はいよいよレフカダ島へドライブに行くんだ」と言って店を出た。
ビールもまわって、いい気分で10分ほど歩いてホテルに到着した。玄関を入って後ろを見ると、さっき別れたアレクサンダー大王氏が後ろでニコニコしているではないか。よく見ると傍らにスズキ製の彼のバイクがピカピカに磨かれて、おかれている。「これは日本製の俺のバイクだ。ちょっとこの辺を乗ってみないか」という。我々の出かけた後を、このバイクで追っかけてきたようだった。自分の店でアルコールを飲ませて、その続きに運転してみないかと言うのも面白いなと思ったが、「日本人で運転が好きそうだから、俺の日本製のバイクに乗せてやろう」と思いついたら、営業中の店を放り出しても、追いかけてきて、その好意を示してくれる率直な親切に感動した。ギリシャ人の一面を見た思いがした。
「ギリシャ人は運転が乱暴だから気をつけろ」とよく旅行書やインターネットのページには出ていた。確 かに都市の混雑した場面では、ちょっと無理だと思われる割り込みがよくあるし、掲示されている制限速度の2倍が実際の制限速度だと思った方がいい場面が多い。そして、彼らはよくクラクションを鳴らす。最初は何だろうと思ったが、一種の挨拶代わりに車同士でクラクションの交換を大胆に行う。また駐車違反を取り締まるということもないので、田舎の中心街などは道路があっても、広くはないのに、両側に勝手な向きで駐車することが普通である。一方通行でもない道で両側に駐車があり、1台がやっと通れるスペースが残されている場面で、両方向から車が来る場面もよくあるのだが、不思議にうまく流れるのはどうなっているのだろう。ギリシャに行く飛行機の中で、隣にリオリオスさんというギリシャ人のビズネスマンと乗り合わせた。ギリシャでの運転に少し不安があったので、「ギリシャの運転は危険だと言われているが.....」と言ったら、「それは酔っ払い運転が認められているからだろう」と言った。アテネのアレクサンダー大王氏がバイクの乗れと言ったとき、彼の言葉が急によみがえった。でも、車の絶対数が少ない上に、国土は広いので、全体としては実に快適なドライブであった。ただ、田舎に行くと、道路の行く先表示がギリシャ語だけで書かれているところも多いので、ギリシャ語を一応何とか読めるようにしていったのは正解だった。
かに都市の混雑した場面では、ちょっと無理だと思われる割り込みがよくあるし、掲示されている制限速度の2倍が実際の制限速度だと思った方がいい場面が多い。そして、彼らはよくクラクションを鳴らす。最初は何だろうと思ったが、一種の挨拶代わりに車同士でクラクションの交換を大胆に行う。また駐車違反を取り締まるということもないので、田舎の中心街などは道路があっても、広くはないのに、両側に勝手な向きで駐車することが普通である。一方通行でもない道で両側に駐車があり、1台がやっと通れるスペースが残されている場面で、両方向から車が来る場面もよくあるのだが、不思議にうまく流れるのはどうなっているのだろう。ギリシャに行く飛行機の中で、隣にリオリオスさんというギリシャ人のビズネスマンと乗り合わせた。ギリシャでの運転に少し不安があったので、「ギリシャの運転は危険だと言われているが.....」と言ったら、「それは酔っ払い運転が認められているからだろう」と言った。アテネのアレクサンダー大王氏がバイクの乗れと言ったとき、彼の言葉が急によみがえった。でも、車の絶対数が少ない上に、国土は広いので、全体としては実に快適なドライブであった。ただ、田舎に行くと、道路の行く先表示がギリシャ語だけで書かれているところも多いので、ギリシャ語を一応何とか読めるようにしていったのは正解だった。
ただ1つ困ったことがあった。それはトイレである。アテネの中心地シンタグマの地下鉄駅も、ホームの駅名は透明な プラスティック板に真っ赤で美しい文字が埋め込まれていて、駅舎もきれいで、実に多くの人が利用するが、公衆トイレは1つもない。地下鉄を出たところには、パンや飲料、新聞などを売るキオスクがいくつかあるが、そこで「トイレは?」と聞くと、通りの向こうにあるマクドナルドを指差して、「あそこだよ」という。マクドナルドは公衆トイレではないが多くの人がそこの地下トイレを利用するようだし、路上にテーブルとイスを並べたカフェやタベルナは、屋内より人気があり、屋内で座っている人ほとんどなくて、あえて屋内に行く人の多くは地下のトイレにいくようだ。
プラスティック板に真っ赤で美しい文字が埋め込まれていて、駅舎もきれいで、実に多くの人が利用するが、公衆トイレは1つもない。地下鉄を出たところには、パンや飲料、新聞などを売るキオスクがいくつかあるが、そこで「トイレは?」と聞くと、通りの向こうにあるマクドナルドを指差して、「あそこだよ」という。マクドナルドは公衆トイレではないが多くの人がそこの地下トイレを利用するようだし、路上にテーブルとイスを並べたカフェやタベルナは、屋内より人気があり、屋内で座っている人ほとんどなくて、あえて屋内に行く人の多くは地下のトイレにいくようだ。
これはドライブの時も同じで、有料(と言っても200円程度の)高速道路でも、ときどき「500メートル先 にWC」という標示が出たりする。寄ってみると、車が何台か駐車できるスペースが道路わきにあるだけで、トイレらしい建物はない。見ると男性は立ちションをしている。でも女性はどうすればいいんだろう。田舎の道でも同様で、車が休めるちょっと引っ込んだ場所の奥の方は「自然のトイレ」になっていて、カラカラに乾いた大地はあらゆる水分の補給を求めていて、そのような場所には人間の排泄物がカラカラになって点在する。ある場所では、道端で死んだ犬の死骸が、突き刺すような日差しで骨以外の部分が全部蒸発したように、乾燥した骨格だけがすべて原型のままで横たわっていた。我々は今までの習慣上、出来るだけガソリンスダンドのトイレや、町ではスーパーマーケットのトイレなどを利用したが、田舎では便座がないトイレがあったり、汚かったりして、こんな気候の国では「自然のトイレ」の方がはるかに清潔で自然なのかもしれないと思った。
にWC」という標示が出たりする。寄ってみると、車が何台か駐車できるスペースが道路わきにあるだけで、トイレらしい建物はない。見ると男性は立ちションをしている。でも女性はどうすればいいんだろう。田舎の道でも同様で、車が休めるちょっと引っ込んだ場所の奥の方は「自然のトイレ」になっていて、カラカラに乾いた大地はあらゆる水分の補給を求めていて、そのような場所には人間の排泄物がカラカラになって点在する。ある場所では、道端で死んだ犬の死骸が、突き刺すような日差しで骨以外の部分が全部蒸発したように、乾燥した骨格だけがすべて原型のままで横たわっていた。我々は今までの習慣上、出来るだけガソリンスダンドのトイレや、町ではスーパーマーケットのトイレなどを利用したが、田舎では便座がないトイレがあったり、汚かったりして、こんな気候の国では「自然のトイレ」の方がはるかに清潔で自然なのかもしれないと思った。

