
自民党幹部は、ニュージーランドが商業捕鯨に反対する報復としてODA援助を減らすと言ったそうだが、一旦自然が商業主義にさらされるとどんなひどい状況になるかを、自然と 共に生きるニュージーランドの人たちは誰よりも知っているようだ。実際、税金で鯨の病院まで作って鯨の健康管理に気を使っている人たちから見れば、鯨の肉を食わせるために捕鯨して儲けるなどという発想が理解できるわけがない。鯨だけではない。キウイ、アホウドリ、ペンギン、などの動物だけでなく、ニュージーランドにしか存在しない固いカウリの木なども、過去に、利益追求のために乱伐され、今や絶滅の危機に瀕しているとのこと。キウイも、オークランド動物園などに保護されているものの他にはなかなかお目にかかれない。夜行性なので、その厩舎では昼間くる人間のために、昼と夜を逆にして、昼間は真っ暗の室内に赤い電球でかすかに様子が見えるようにしてある。翼がなくて飛べない鳥だけに足が発達したようで、真っ暗でもラグビーボールのような身体をすごい速さで移動させ、細長いクチバシを落ち葉の中に深くうずめて虫を食べている。
共に生きるニュージーランドの人たちは誰よりも知っているようだ。実際、税金で鯨の病院まで作って鯨の健康管理に気を使っている人たちから見れば、鯨の肉を食わせるために捕鯨して儲けるなどという発想が理解できるわけがない。鯨だけではない。キウイ、アホウドリ、ペンギン、などの動物だけでなく、ニュージーランドにしか存在しない固いカウリの木なども、過去に、利益追求のために乱伐され、今や絶滅の危機に瀕しているとのこと。キウイも、オークランド動物園などに保護されているものの他にはなかなかお目にかかれない。夜行性なので、その厩舎では昼間くる人間のために、昼と夜を逆にして、昼間は真っ暗の室内に赤い電球でかすかに様子が見えるようにしてある。翼がなくて飛べない鳥だけに足が発達したようで、真っ暗でもラグビーボールのような身体をすごい速さで移動させ、細長いクチバシを落ち葉の中に深くうずめて虫を食べている。
ちょっと前に書いたが、南島の南部東海岸にオタゴ半島というのがあり、その突端にある国立アホウドリ保護区(Royal Albatross Colony)を訪ねてみた。数少なくなった鳥を必死に守っているという感じの施設である。 孤島の断崖にしか住まない鳥が人間の近くに住み着いた世界で唯一の場所だそうだ。かなり広い突端の部分全体が保護区になっていて、アホウドリが飛来して子育てをする断崖の近くは厳重な立入り禁止区域で、その一角に目立たぬように展望室が作られている。外の鳥から見えないように、展望室のガラスは全て色ガラスになっている。大学で生物学を研究しているという施設専属の若いガイドが何重にも設けられた柵につけられたドアの鍵を開けては我々を通し、長い登山道のような道を登りながら案内してくれてやっとたどり着いた展望室である。でも我々は幸運であった。大きなガラス窓越しに見るとアホウドリの真っ白い子供(と言っても8キロもある大きな鳥だが)が、3羽ほど互いに離れて断崖で休んでいる。するとガイドが急にLook!という。目を上げると黒い翼の親鳥らしいのが、自分の子供である白い1羽のところへ旋回して降り立った。親鳥といっても子供より軽く、体重は6〜7キロだという。でも餌の魚を2キロも喉の奥に抱えているようで、全体としては少し子供より重いらしい。早速餌付けが始まった。
孤島の断崖にしか住まない鳥が人間の近くに住み着いた世界で唯一の場所だそうだ。かなり広い突端の部分全体が保護区になっていて、アホウドリが飛来して子育てをする断崖の近くは厳重な立入り禁止区域で、その一角に目立たぬように展望室が作られている。外の鳥から見えないように、展望室のガラスは全て色ガラスになっている。大学で生物学を研究しているという施設専属の若いガイドが何重にも設けられた柵につけられたドアの鍵を開けては我々を通し、長い登山道のような道を登りながら案内してくれてやっとたどり着いた展望室である。でも我々は幸運であった。大きなガラス窓越しに見るとアホウドリの真っ白い子供(と言っても8キロもある大きな鳥だが)が、3羽ほど互いに離れて断崖で休んでいる。するとガイドが急にLook!という。目を上げると黒い翼の親鳥らしいのが、自分の子供である白い1羽のところへ旋回して降り立った。親鳥といっても子供より軽く、体重は6〜7キロだという。でも餌の魚を2キロも喉の奥に抱えているようで、全体としては少し子供より重いらしい。早速餌付けが始まった。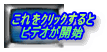 子供が親のクチバシを刺激して、親が口を開き、その瞬間に子供は親の咽の奥までクチバシを突っ込んで餌を引き出して食べる。これを数回繰り返した後で
子供が親のクチバシを刺激して、親が口を開き、その瞬間に子供は親の咽の奥までクチバシを突っ込んで餌を引き出して食べる。これを数回繰り返した後で 親はまたどこかへ消えていった。この餌付けは2〜3日に1回しか行われず、よっぽど運が良くないとその場にめぐり合わせることはないという。たまたまビデオカメラを向けていたので、その有様を全部収録することができた。ここにその部分のビデオクリップを貼り付けたので、興味のある向きはクリックしてビデオのままごらんいただきたい。真っ黒いサギも近くに見られたが、アホウドリに比べると、あの大きなサギが
親はまたどこかへ消えていった。この餌付けは2〜3日に1回しか行われず、よっぽど運が良くないとその場にめぐり合わせることはないという。たまたまビデオカメラを向けていたので、その有様を全部収録することができた。ここにその部分のビデオクリップを貼り付けたので、興味のある向きはクリックしてビデオのままごらんいただきたい。真っ黒いサギも近くに見られたが、アホウドリに比べると、あの大きなサギが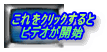 ひどく小さく見える。生後4ヶ月になるのにまだ飛べない子供が懸命に羽ばたく練習をしている。3重の折りたたみ傘のような構造の翼は広げると子供でも3メートルにもなるという。
ひどく小さく見える。生後4ヶ月になるのにまだ飛べない子供が懸命に羽ばたく練習をしている。3重の折りたたみ傘のような構造の翼は広げると子供でも3メートルにもなるという。
すぐ近くの海岸でペンギンが自然に暮らしているのを観察できる場所がある。ここはアホウドリの場所と違って政府の資金援助がなく、全く民間の動物愛好家が絶滅に瀕した動物を保護しようと、研究もしながら、少し高い見学料(NZ$27=1600円)だけで運営している。それも黄目ペンギン(yellow-eyed penguin)と言われる身長60cmくらいのこの地にしかいないという種類のものだ。実際 遠くからではよく分からないが、写真などでは目の虹彩が黄色に見える。これも10人くらいのグループをガイドが案内する形で行われている。寒さに震えながら、夕方の海岸を小さな断崖の上から眺めてい
遠くからではよく分からないが、写真などでは目の虹彩が黄色に見える。これも10人くらいのグループをガイドが案内する形で行われている。寒さに震えながら、夕方の海岸を小さな断崖の上から眺めてい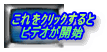 ると、海の中から1羽のペンギンがヨタヨタと浜辺に上がってきた。ときどき立ち止まって様子を見ながら、そのままスタスタ浜辺の砂地と横切って雑草の生えた丘陵地に向かう。そこには目立たぬように木の皮の小さな三角屋根で覆った横穴がいくつか作られていて、その前には別のペンギンが白いお腹をみせてじっと立っている。ペンギンの習性にあうように人間が作った彼らの住まいだ。彼らの自然な生活を妨害しない配慮から、丘陵地一面に半透明のビニールで覆われた塹壕のようなトンネルが迷路のように掘られていて、そこを我々は急ぎ足で走る。そしてちょっと大きな穴倉に出る。ちょうど目の位置あたりに周りを見渡せるくらいの10cm巾くらいの隙間が作ってあって、そこから静かに観察したり、写真を撮る。でもペンギンの目を守るためにフラッシュは厳禁との事。動物への気の使いようは人間以上だ。
ると、海の中から1羽のペンギンがヨタヨタと浜辺に上がってきた。ときどき立ち止まって様子を見ながら、そのままスタスタ浜辺の砂地と横切って雑草の生えた丘陵地に向かう。そこには目立たぬように木の皮の小さな三角屋根で覆った横穴がいくつか作られていて、その前には別のペンギンが白いお腹をみせてじっと立っている。ペンギンの習性にあうように人間が作った彼らの住まいだ。彼らの自然な生活を妨害しない配慮から、丘陵地一面に半透明のビニールで覆われた塹壕のようなトンネルが迷路のように掘られていて、そこを我々は急ぎ足で走る。そしてちょっと大きな穴倉に出る。ちょうど目の位置あたりに周りを見渡せるくらいの10cm巾くらいの隙間が作ってあって、そこから静かに観察したり、写真を撮る。でもペンギンの目を守るためにフラッシュは厳禁との事。動物への気の使いようは人間以上だ。
北島の北部Northlandと呼ばれる部分の西海岸に、シダやカウリが茂るウィポウア森林地区というのがあり、その中に、とてつもなく大きくて古いカウリの大木が見られる。高さは50mくらいだが、周囲が13m以上もあり、周りの木と全く違うスケールに度肝を抜かれる。まるで地球の太い軸が地 中から飛び出したかのようでもあり、森のお化けが急に目の前に現れたような感じでもある。実際このカウリは「森の神」と呼ばれている。ニュージーランドだけにしかないこの木は目が詰まっていて固く、船を作るのに適した材質ということで過去に乱伐され、これも絶滅に瀕した生き物である。目が詰まった材質は成長するのに時間がかかるようで、この巨木は樹齢2000年とのこと。人間が100年生きるのは奇跡だが、この木はキリストが生まれてからの2000年を全部生きて見てきたという世界1長寿の生物だと思うと恐ろしくなるほど感動的だ。これも保護を受けて今はしっかり守られているようだが、これを見世物にしてお金をとるようなことはしていないのが良い。土曜日だったが2台くらいの乗用車が来ていたくらいで、文字通り悠久な静寂の森の感があった。
中から飛び出したかのようでもあり、森のお化けが急に目の前に現れたような感じでもある。実際このカウリは「森の神」と呼ばれている。ニュージーランドだけにしかないこの木は目が詰まっていて固く、船を作るのに適した材質ということで過去に乱伐され、これも絶滅に瀕した生き物である。目が詰まった材質は成長するのに時間がかかるようで、この巨木は樹齢2000年とのこと。人間が100年生きるのは奇跡だが、この木はキリストが生まれてからの2000年を全部生きて見てきたという世界1長寿の生物だと思うと恐ろしくなるほど感動的だ。これも保護を受けて今はしっかり守られているようだが、これを見世物にしてお金をとるようなことはしていないのが良い。土曜日だったが2台くらいの乗用車が来ていたくらいで、文字通り悠久な静寂の森の感があった。
ニュージーランドと言えば土ボタル(glow worm)が有名だが、我々は北島のワイトモ洞窟ではなく、南島の南方、テ・アナウ湖の対岸にあるテ・アナウ洞窟の土ボタルを見た。地下水が大量に溢れる鍾乳洞の中を小さなボートでさかのぼったところが鉄板でせき止められていて、小さな人工の池にな っていた。そこにまた10人乗りくらいのボートを浮かべて洞の奥に進み、手を伸ばせば届きそうな、狭くなった洞窟の壁に無数に張付いているホタルが発する微かな光を楽しむ。実際はfungus gnatと呼ばれる小さなハエの幼虫が餌を消化中に黄燐が酸化して出す光だそうで、空腹なほど光が強くなるという。真っ暗な宇宙に突然投げ出されたかのような錯覚に捕らわれながら、小さな無数の星の微かな輝きに包まれてうっとりとしてしまう。地上で見るホタルよりデリケートな小さい光だ。大量にあふれ出る地下水が堰を越えて滝のように流れ落ちるゴーゴーという音だけが不気味に響いている。同じボートに乗り合わせた外人たちも文字通り息をのんでいてその存在が全く感じられず、ひとりで真っ暗な小宇宙にぽっかり浮かんで、さまよっているような幻想的な、不思議なひとときであった。しかしこれもこの地の自然なのだ。
っていた。そこにまた10人乗りくらいのボートを浮かべて洞の奥に進み、手を伸ばせば届きそうな、狭くなった洞窟の壁に無数に張付いているホタルが発する微かな光を楽しむ。実際はfungus gnatと呼ばれる小さなハエの幼虫が餌を消化中に黄燐が酸化して出す光だそうで、空腹なほど光が強くなるという。真っ暗な宇宙に突然投げ出されたかのような錯覚に捕らわれながら、小さな無数の星の微かな輝きに包まれてうっとりとしてしまう。地上で見るホタルよりデリケートな小さい光だ。大量にあふれ出る地下水が堰を越えて滝のように流れ落ちるゴーゴーという音だけが不気味に響いている。同じボートに乗り合わせた外人たちも文字通り息をのんでいてその存在が全く感じられず、ひとりで真っ暗な小宇宙にぽっかり浮かんで、さまよっているような幻想的な、不思議なひとときであった。しかしこれもこの地の自然なのだ。
南島のクィーンズタウンからさらに南のテ・アナウに向かう道はワカティプ湖の東側に沿って進む。その湖の南端でっ車を止めて小休止した。一面の原始林が湖畔に迫る人っ子ひとりいない神秘の世界。林立する大木の樹皮を苔が一面に覆い、枝から枝へ不気味な太いツタが絡み合う。地面の落ち葉や鋭い草の葉を踏みつけると、水分を含んで柔らかくなったその下の堆積物が靴に押されて凹み、その脇から下の水がしみだしてくる。そんな中をゆっくり進むと、静かな湖の淵へ出た。全くひと気のない原始の森と湖の真っ只中だ。まだ十分に太陽が高く上っていないので、右側に大きくそびえる雪をかぶった岩山が湖に影を落として、湖面が深い藍色をしている。湖面を流れる微風がかすかにさざ波を立てている。前方にずっとつづく果てしない水の広がりのむこうで青い空がまぶしい。足元にリズムをとるかのように打ち寄せる静かな波の音。その波に洗われる丸い小石の行列。手付かずの生の自然との融合である。
人間が親切で旅が気持ちよく進むのもニュージーランドの特徴かもしれない。南島の南方の大都市、ダニーデンのダウンタウンでパーキングビルに駐車したとき、入口のブースにいる年配の男性に、オクタゴンという広場への道を尋ねた。彼は足がびっこだったのに、“I’ll show you.”と、わざわざ大きなビルの反対側のまで階段を登って抜け穴のような道が見えるところまで我々を案内してくれた。帰りもその抜け穴の入口で、駐車券を精算機に入れてから、財布にコインのないことに気づき、キャンセルの仕方が分からなかった。、さっきのブースへ行って尋ねたら、こんどは近くにいた若い男がまたずっとはなれた別の口まで走っていって解決してくれた。
アホウドリの繁殖地に行ったときも、国立の施設なのに、我々のためにとても便宜をはかってくれた。本来なら、その施設への訪問者は予約が絶対必要で、最初に1時間もビデオや説明のオリエンテーションを受けなければ繁殖地を見せてもらえない仕組みになっている。しかし我々は次にペンギンの繁殖地見学を予定していたので、その旨を話し日本からわざわざ来たことがわかると、予約なしの飛び込みなのに、すぐにあいているガイドに連絡をとって、そのまま直接繁殖地を案内してもらった。しかもそのあと、先に書いたように、めったに見れないというアホウドリの餌付けの場面に遭遇した。
北島の北方NorthlandのWhangarei の“i”つまり観光案内所 で夕方、その日の宿泊場所を尋ねていて、「見晴らしのいいところが良いのですが」といったら、最初の若い女性係員は、「30分くらいは郊外の方へ出ないとありませんね」という。すると側で他の客の話を聞いていた年配の女性が一段落したらしく、口をはさんだ。「いや、近くに良いところがあるよ」という。そして車で5分くらいの小さな空港の裏の静かな海岸沿いの高級モテルを紹介してくれた。そこへの行き方を地図で教えてから、NZ$3.45(200円)でその場で売っているその地図にルートをしるして、笑顔と共に、タダでくれた。実際、そのモテルは、湾と対岸の風景が眼前に180度広がる予想以上の宿だった。豪華な朝食(cooked breakfast)つきで1人1泊NZ$60(3600円)であった。
で夕方、その日の宿泊場所を尋ねていて、「見晴らしのいいところが良いのですが」といったら、最初の若い女性係員は、「30分くらいは郊外の方へ出ないとありませんね」という。すると側で他の客の話を聞いていた年配の女性が一段落したらしく、口をはさんだ。「いや、近くに良いところがあるよ」という。そして車で5分くらいの小さな空港の裏の静かな海岸沿いの高級モテルを紹介してくれた。そこへの行き方を地図で教えてから、NZ$3.45(200円)でその場で売っているその地図にルートをしるして、笑顔と共に、タダでくれた。実際、そのモテルは、湾と対岸の風景が眼前に180度広がる予想以上の宿だった。豪華な朝食(cooked breakfast)つきで1人1泊NZ$60(3600円)であった。
南島の内陸部は国道といっても交通量がぐっと少なくなる。オフシーズンであることもあるだろうが、 15分や20分くらい対向車に出合わないことも多い。大部分が牧場の大地がうねりながらもずっと遠くまで広がり、ずっと向こうに青黒い低い山並みが続く。さらにその上の遠方には雪をかぶってゴツゴツと空に突き刺さるようにそびえる白い山並みが重なる。冬とはいっても陽射しは強く、窓を閉めると汗をかくくらいだ。そんな中を車を飛ばすのは実に快適だ。しかしこういう状況になれた運転手には睡魔に襲われる危険もあるようだ。「眠いですか?(Feeling sleepy?)」「少し休息をお取りください(Take a rest!)」と書かれた、目が回っているような渦巻きの看板に出会う。日本ではまず見かけないような交通標識で、南島でしか見なかったが、やさしい思いやりをかけられたようで、思わず緊張がとれた。実際、国道沿いには一定間隔ごとに、木の下にテーブルが置かれた図案の標識があり、眠くなったらそこに停車してリクライニングシートを倒してちょっとうとうとすると再び気分が爽快になった。驚いたことに「命を大切に!」と日本語で書かれた交通標識も見た。日本人のドライバーも増えてきているようだ。
15分や20分くらい対向車に出合わないことも多い。大部分が牧場の大地がうねりながらもずっと遠くまで広がり、ずっと向こうに青黒い低い山並みが続く。さらにその上の遠方には雪をかぶってゴツゴツと空に突き刺さるようにそびえる白い山並みが重なる。冬とはいっても陽射しは強く、窓を閉めると汗をかくくらいだ。そんな中を車を飛ばすのは実に快適だ。しかしこういう状況になれた運転手には睡魔に襲われる危険もあるようだ。「眠いですか?(Feeling sleepy?)」「少し休息をお取りください(Take a rest!)」と書かれた、目が回っているような渦巻きの看板に出会う。日本ではまず見かけないような交通標識で、南島でしか見なかったが、やさしい思いやりをかけられたようで、思わず緊張がとれた。実際、国道沿いには一定間隔ごとに、木の下にテーブルが置かれた図案の標識があり、眠くなったらそこに停車してリクライニングシートを倒してちょっとうとうとすると再び気分が爽快になった。驚いたことに「命を大切に!」と日本語で書かれた交通標識も見た。日本人のドライバーも増えてきているようだ。
今度はトラブル。ニュージーランドの家庭ではエネルギーを全部電気で賄っているようだ。それでも電気料金が日本よりかなり安く、大きな農家でも、電気ストーブや電気コンロ、電気毛布や温水器などの熱エネルギーもすべて電気に頼って1ヶ月6000円位だという。でもこれには落とし穴があった。南島Lake Tekapoのモテルに泊まった日はかなり寒かった。お風呂はなくシャワーの設備しかなかったので、シャワーで身体を暖めつつ、洗っていて家内が20分くらい出しっぱなしにして使ったあとで、私が入ってシャワーの蛇口を開いてしばらくすると、お湯が冷たい水に変わってしまった。どうしても再びお湯にならず、あわてて電気毛布にくるまって暖を取ったが、もう少しで風邪を引くところだった。バンガロー風のつくりで、管理人室が遠く、寒いところを出て行く気もしないまま、翌日は管理室はカラで管理人にも会えずに、そのまま出てしまった。その後、ファーム・ステイをしたときに、そのようすを話したら、主人は「それは当然ですよ。電気温水タンクはシャワーでは1人せい ぜい5分程度しか使わないことを前提にできていて、使い切ってしまうと、再び温水が溜まるまで、5〜6時間はかかりますよ」とのことだった。大型の瞬間ガス湯沸かし器に慣れた生活をしていて、お湯がいかに貴重なものか分からずに生きてきたことを感じた。
ぜい5分程度しか使わないことを前提にできていて、使い切ってしまうと、再び温水が溜まるまで、5〜6時間はかかりますよ」とのことだった。大型の瞬間ガス湯沸かし器に慣れた生活をしていて、お湯がいかに貴重なものか分からずに生きてきたことを感じた。
コンセントつまり電気のソケットの形が違うのは、お国柄仕方ないとしても、スイッチは日本と反対で、上に上げるとOFFになり、下げるとスイッチが入る。しかもコンセントには必ず、となりにスイッチがあり、それを下げないでプラグを差し込んだだけでは電気は通じない。このように母国の習慣と違うのは慣れるのに時間がかかるし、面倒だ。でも230Vなのは熱として使うとき効率がいいような気がする。
ニュージーランドは雨が多いと聞かされていたが、天気には恵まれた。北島のWhangareiに行った次の日も、抜けるような青空の快晴だった。朝BBの主人にあって、”Beautiful
day, isn't it?" といったら、"You've brought it with you."「あなた方がこの天気を連れてきたくれたんですよ」と返してくれた。普通なら、"Yes,
isn't it?."か何かで流すところなのに、こういう言い方は感じが良かった。覚えておこうと思った。日本だと「雨男」「雨女」ということは言っても、「晴れ男(女)」とはあまり聞かない。明るい表現もあっていいのでは.....と思う。

