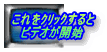タスマニアには19世紀初頭の入植者が、囚人(convicts)を奴隷のように使いながら、成功を収めた旧家が歴史的遺産として公開されている。彼らは羊毛が世界で珍重される時代に、広大な敷地を確保し牧畜をした。成功すると、イギリスから高価な家具や高級車、蒸気自動車まで買い付け、十数人の子供をつくり、優雅な生活をし ていたらしいが、何世代かたつうちに種々のいさかいも起こり、跡取りもなくなり、国の遺産管理団体(National Trust)に資産が移管されて一般に公開される羽目になるというケースが多いようだ。
ていたらしいが、何世代かたつうちに種々のいさかいも起こり、跡取りもなくなり、国の遺産管理団体(National Trust)に資産が移管されて一般に公開される羽目になるというケースが多いようだ。
しかし邸内にはこの土地にはない調度品の数々、高価な絵画、宮殿にあるようなベッド、銀やガラスの食器類が置かれ、格子のある窓からは外に広がる緑と花々が望まれる。
広い敷地にはこの土地にある変わった植物が集められて、世界のほかの地域には存在しない変種が繁茂している。例えば写真のヒロ ハノナンヨウスギ(Bunya Pine)などは木の怪物だ。何本もの枝が幹から真横に出て、太い幹にはたこのイボのような形の穴が無数に開き気持ちが悪い。でもその実はそのままでも食べられるらしく、アボリジニはそれをパンにして食べていたそうで、その木がある山は縄張り争いの元となったという。マルメロ(Quince)も目に付いた。カリンに似た実をつけ、そのままでは食べられないが、ジャムやワインにする人もいるようだ。
ハノナンヨウスギ(Bunya Pine)などは木の怪物だ。何本もの枝が幹から真横に出て、太い幹にはたこのイボのような形の穴が無数に開き気持ちが悪い。でもその実はそのままでも食べられるらしく、アボリジニはそれをパンにして食べていたそうで、その木がある山は縄張り争いの元となったという。マルメロ(Quince)も目に付いた。カリンに似た実をつけ、そのままでは食べられないが、ジャムやワインにする人もいるようだ。
実際この地域の収穫物を加工して、ソース工場をつくり成功した大邸宅を見学した。ソースといってもお菓子にかけるジャムのようなものまであり、甘党と辛党の両方の要望に応える。タスマニアの真ん中EvandaleというところのTasmania Gourmet Sauce
Companyだ。青い屋根と白壁の別荘のような平屋の建物が、輝くような緑の木々と花が咲き乱れる花壇の中にうずくまっている。庭の芝生には人懐こい白い犬が転げまわる。木々の間からは四方に広がる大平原が望まれ、遠くに馬が草を食んでいるのが見える。これがソース会社かと目を疑うほどだ。会社というより別荘と言った方がいいような家の台所の ような場所でソースは作られていた。競争が厳しい日本では考えられないようなノンビリした優雅な「工場」だ。出来てきたソースはきれいに包装されて棚に並べられ、女主人がお土産に小さなビン入りのケーキ用のソースをくれた。
ような場所でソースは作られていた。競争が厳しい日本では考えられないようなノンビリした優雅な「工場」だ。出来てきたソースはきれいに包装されて棚に並べられ、女主人がお土産に小さなビン入りのケーキ用のソースをくれた。
大農家はその敷地に付属するチャペルまで持っている。そこで結婚 式をやっている場面にぶっつかった。七面鳥が餌をついばんでいる農場に並んだ教会から突然花嫁と花婿が出てきたので、Congratulations!と声をかけたら、Thank youとうれしそうな笑顔が返ってきた。カメラを向けたらわざわざ2人とも私のほうを向いてくれて、ポーズをとってくれた。そういえば、その近くのだだっ広くて暗い倉庫の中にはスピーチの台が用意され、テーブルクロスもない机が無造作に並べられて、披露宴会場になる段取りがあった。でも決して虚飾にならず、見栄を張らず、お金をかけない素朴な田舎の結婚式だった。その前庭の七面鳥はひょっとしたら、つぶされてお祝いの食卓に上がるのかなと、偶然の取り合わせを一人楽しんでいた。
式をやっている場面にぶっつかった。七面鳥が餌をついばんでいる農場に並んだ教会から突然花嫁と花婿が出てきたので、Congratulations!と声をかけたら、Thank youとうれしそうな笑顔が返ってきた。カメラを向けたらわざわざ2人とも私のほうを向いてくれて、ポーズをとってくれた。そういえば、その近くのだだっ広くて暗い倉庫の中にはスピーチの台が用意され、テーブルクロスもない机が無造作に並べられて、披露宴会場になる段取りがあった。でも決して虚飾にならず、見栄を張らず、お金をかけない素朴な田舎の結婚式だった。その前庭の七面鳥はひょっとしたら、つぶされてお祝いの食卓に上がるのかなと、偶然の取り合わせを一人楽しんでいた。
メルボルンの北方、Castlemaineという小さな町にClevedon
Manor  という旧家があり、BBをやっているというので泊まってみた。かなり古風の屋敷から主人が待っていたように迎え入れてくれた。日本から予約しようとしてSkype電話で話した相手の人だったので、よく分かっていたようだ。古風な家具とベッドの大きな部屋以外に、邸宅の応接間にも冷房が入っていて、脇にシェリー酒が用意され、どうぞごゆっくり・・・というので、2人でシェリーを傾けながら、古めかしい調度品を吟味していた。そのとき主人が顔を出したので、脇にあったたくさんの巻物のことを聞いてみた。巾30cmくらいの巻き紙にあけられた無数の穴を読み取って、鍵盤を自動的に動かすピアノーラという自動ピアノ。実際に「演奏」してもらったが、演奏者はオルガンのような足のべダルを繰り返し、踏みつけて動力を供給しなければならず、大変な「運動」のようだった。でも、音はそれなりにリズムをもって鳴り、ピアノを弾けない人がピアノの原音を聞ける点はいいし、何よりそれが1920年代のしろものなのにまだ十分に機能していることに驚いた。その実演の様子はビデオの最後の方に入れてあるので、興味のある方はご覧ください。
という旧家があり、BBをやっているというので泊まってみた。かなり古風の屋敷から主人が待っていたように迎え入れてくれた。日本から予約しようとしてSkype電話で話した相手の人だったので、よく分かっていたようだ。古風な家具とベッドの大きな部屋以外に、邸宅の応接間にも冷房が入っていて、脇にシェリー酒が用意され、どうぞごゆっくり・・・というので、2人でシェリーを傾けながら、古めかしい調度品を吟味していた。そのとき主人が顔を出したので、脇にあったたくさんの巻物のことを聞いてみた。巾30cmくらいの巻き紙にあけられた無数の穴を読み取って、鍵盤を自動的に動かすピアノーラという自動ピアノ。実際に「演奏」してもらったが、演奏者はオルガンのような足のべダルを繰り返し、踏みつけて動力を供給しなければならず、大変な「運動」のようだった。でも、音はそれなりにリズムをもって鳴り、ピアノを弾けない人がピアノの原音を聞ける点はいいし、何よりそれが1920年代のしろものなのにまだ十分に機能していることに驚いた。その実演の様子はビデオの最後の方に入れてあるので、興味のある方はご覧ください。
Clevedon Manorの朝食はなかなかのものだった。クラシックな家具に取り囲まれた部屋の壁には騎手だったStuart氏の名馬が入賞の首輪とともに何枚もかけられていて、彼の若いころの愛馬と一緒の写真もあった。白馬3代を車で10分ほどのところにある飼育場で飼っていて、57歳の今でも乗りこなしていると、彼の友人のJoyさんが朝食の用意をしながら説明してくれた。ここに来る途中でたまたま競馬場を見たが、日本と違うのは観覧席の狭いことだった。壮大な競技場なのに周 囲には緑の芝生の中にポツンポツンとベンチが置いてあるだけだった。彼らは賭けをしたり人に見せたりするより、自分で馬に乗って仲間と競走するのを楽しむために競馬場を利用することを改めて知らされた。
囲には緑の芝生の中にポツンポツンとベンチが置いてあるだけだった。彼らは賭けをしたり人に見せたりするより、自分で馬に乗って仲間と競走するのを楽しむために競馬場を利用することを改めて知らされた。
われわれの寝室は花模様の壁布とベッドカバーに囲まれて、女王の間という雰囲気であったが、コンセントがすぐに見当たらず、もって行ったパソコンを動かすのに苦労した。でも窓からは庭の大きな木や花壇が望まれ、額のある大鏡や古風なカウチなども置かれて、パソコンを扱う雰囲気ではなかった。我々はその晩の唯一のお客だった。
<このページ上部へ移動>
タスマニア島中部の平原にある小さな村Mole CreekのコテッジHoliday Villageにつくと、管理人がいない。太い蛇が出て助けを求めて人を探していた模様。Villageというように小 高い丘の中腹に並んだコテッジの1つに車ごと横付け。2人で11000円(117ドル)。コテッジの前はずっと遠くのクレイドル・マウンテンの山並みまで緩やかに波打つ平原が広がり、裏手は小高い山に通じる斜面を利用して、牧場が広がっている。でも中は寝室2つにオーブンや電子レンジ、トースター、冷蔵庫、テレビ、湯沸し、なべ、皿、洗剤までそろった2LDKの感覚。早速4キロ離れた小さなスーパーへ出かけて肉やソーセージ、野菜、などを買い込んで自己流にステーキを焼く。ややwell-doneになった肉にナイフをいれて顔を上げたら、寝室の窓ガラスのレースのカーテン越しに熊に似た大きな動物が迫ってきた。レースのカーテンをまくると何か得体の知れない黒と茶色の羊に似た動物が草をはんでいる。「脅かすなよ!」と内心ホッとする。
高い丘の中腹に並んだコテッジの1つに車ごと横付け。2人で11000円(117ドル)。コテッジの前はずっと遠くのクレイドル・マウンテンの山並みまで緩やかに波打つ平原が広がり、裏手は小高い山に通じる斜面を利用して、牧場が広がっている。でも中は寝室2つにオーブンや電子レンジ、トースター、冷蔵庫、テレビ、湯沸し、なべ、皿、洗剤までそろった2LDKの感覚。早速4キロ離れた小さなスーパーへ出かけて肉やソーセージ、野菜、などを買い込んで自己流にステーキを焼く。ややwell-doneになった肉にナイフをいれて顔を上げたら、寝室の窓ガラスのレースのカーテン越しに熊に似た大きな動物が迫ってきた。レースのカーテンをまくると何か得体の知れない黒と茶色の羊に似た動物が草をはんでいる。「脅かすなよ!」と内心ホッとする。
Holiday Villageのすぐ隣に、Trowunna Wildlife Parkという自然動物園がある。目玉はタスマニアン・デビルという熊を犬くらいの大きさにしたような動物。肉食で獰猛と案内書などにはかかれているが、実際 檻の外で与えられた野ウサギを食いちぎっている姿は野生そのもの。鋭く長い歯をむき出しにして骨までカリカリとむさぼるさまを見ると名付けた人の気持ちが伝わってくる。カンガルーは子供のときから後ろ足が発達しているようで、前足は杖のように使うだけ。ほとんど2本足と尻尾の3点で身体を支えて立っている。人間はひょっとしたらカンガルーから進化して2本足になったのかと思わせるほどの安定した姿勢。そして性格もコアラなどと違って温厚だ。カンガルーのような腹袋が人間にもあれば、人間社会ももっと温和なものになったかもしれない。鷲も金網のない場所で飼われていて、じっと低い木にとまっているが、オリがないと堂々とした風格は周りを威圧して怖いような雰囲気だ。一般にオーストラリアの地方の動物園は広い場所のところどころに低い石垣などで囲って動物を放し飼いにしてある。草の生え放題の通路らしいところを次の場所を探しながらずっと離れた所へ移動する。だから途中、大蛇でも出てきそうな感じは野生そのものである。
檻の外で与えられた野ウサギを食いちぎっている姿は野生そのもの。鋭く長い歯をむき出しにして骨までカリカリとむさぼるさまを見ると名付けた人の気持ちが伝わってくる。カンガルーは子供のときから後ろ足が発達しているようで、前足は杖のように使うだけ。ほとんど2本足と尻尾の3点で身体を支えて立っている。人間はひょっとしたらカンガルーから進化して2本足になったのかと思わせるほどの安定した姿勢。そして性格もコアラなどと違って温厚だ。カンガルーのような腹袋が人間にもあれば、人間社会ももっと温和なものになったかもしれない。鷲も金網のない場所で飼われていて、じっと低い木にとまっているが、オリがないと堂々とした風格は周りを威圧して怖いような雰囲気だ。一般にオーストラリアの地方の動物園は広い場所のところどころに低い石垣などで囲って動物を放し飼いにしてある。草の生え放題の通路らしいところを次の場所を探しながらずっと離れた所へ移動する。だから途中、大蛇でも出てきそうな感じは野生そのものである。

このあたりには鍾乳洞も複数存在する。その1つMarakoopa Caveを訪ねる。かなり大きく、美しい鍾乳洞。聞き取りにくいオーストラリア語で年配ガイドが説明してくれる。上から下がって来る鍾乳石(stalactite)と下から伸びる鍾乳石(stalagmite)のでき方、つながり方、生成過程などを説明しているがやっかい。鍾乳石は細長い白や茶色の針金のようなものが多いし、変化のある姿をしているが、割に天井が低いしルートのすぐ近くにあるので、折り取られた無残なものもある。これは見つかると150万円の罰金だという。夏のためか洞窟内の川は水量が少ないが、水が静かにたまっている下には傘に開いた珊瑚のような大きな結晶が見事だ。最深部には30メートルくらいの細い谷が形成されて、その底に一応水の流れがかすかに確認できる。最後の洞窟内のホールでガイドが電気を消すと、岩天井に張り付いた無数の土ボタルがオーストラリアの星のように光る。これはニュージーランドで見たものより大きく発光も鮮やかだ。
ここから更に奥の国立公園Cradle Mountainに出かける。深山に囲まれたLake Dove一周6kmのウォーキングコースを2時間の予定でトライ。静かな原生林に囲まれた深緑の湖水のまわりにハイキングコースを作るのは大変だと思われるのに、枕木を半分の長さにしたような木材を並べて丁寧な歩道が造られている。時々すれ違うオーストラ リア人にHi!などとやっていたが、たまたまGood day, mate!「ガッダイ マイト!」と呼びかけてみると、驚いた様子で苦笑いが返ってきた。「何だ アメリカ人も言わない、オーストラリア語(?)を黄色人種が使いあがって…」とでも言いたそう。湖の向こうにはタスマニアのアルプスとでも言うべき1000m級の山が連なっている。富士山のように尖った峰をもつ山の脇に歯が抜けたような大きな凹みをもつ山がある。これがどういう感覚か「ゆりかご」の形に似てる(?)とでもいうのかCradle mountain(ゆりかご山)と名づけられて、このあたりが国立公園になっている。確かに山が少ないこの地方では注目を集めるが、われわれにとってはむしろこの付近の苔むす大きな木々が複雑に絡み合う原生林の方がめずらしい。昼なお暗く湿った空間にはギザギザになった白い骸骨のような倒木やユーカリの剥がれ落ちた樹皮が絡みつき、足の踏み入れようもない。毒蛇や毒グモもいるというし、どんな得体の知れない動物がいて突然襲い掛かってくるかもしれないという雰囲気でも
リア人にHi!などとやっていたが、たまたまGood day, mate!「ガッダイ マイト!」と呼びかけてみると、驚いた様子で苦笑いが返ってきた。「何だ アメリカ人も言わない、オーストラリア語(?)を黄色人種が使いあがって…」とでも言いたそう。湖の向こうにはタスマニアのアルプスとでも言うべき1000m級の山が連なっている。富士山のように尖った峰をもつ山の脇に歯が抜けたような大きな凹みをもつ山がある。これがどういう感覚か「ゆりかご」の形に似てる(?)とでもいうのかCradle mountain(ゆりかご山)と名づけられて、このあたりが国立公園になっている。確かに山が少ないこの地方では注目を集めるが、われわれにとってはむしろこの付近の苔むす大きな木々が複雑に絡み合う原生林の方がめずらしい。昼なお暗く湿った空間にはギザギザになった白い骸骨のような倒木やユーカリの剥がれ落ちた樹皮が絡みつき、足の踏み入れようもない。毒蛇や毒グモもいるというし、どんな得体の知れない動物がいて突然襲い掛かってくるかもしれないという雰囲気でも ある。やがて小雨が体にあたるが、もう1時間以上もぶっ続けに登山道の上り下りを繰り返していて、寒さは吹き飛んでしまった。でも傘をさすほどでもない。普通2時間かかると言われているコースをノンストップ1時間半で駆け抜けるように歩いたのだが、そんなことをオーストラリア人に言えば、「典型的な日本式観光」だといわれそうだ。
ある。やがて小雨が体にあたるが、もう1時間以上もぶっ続けに登山道の上り下りを繰り返していて、寒さは吹き飛んでしまった。でも傘をさすほどでもない。普通2時間かかると言われているコースをノンストップ1時間半で駆け抜けるように歩いたのだが、そんなことをオーストラリア人に言えば、「典型的な日本式観光」だといわれそうだ。
 てよく見ると表皮が墨になって焼けこげている。見晴らしの良い場所に来て車を止めて周りの人に聞いてみると、1年前にVictoria州は大規模な森林火災に襲われて、ひどい被害を受けたのだという。なるほど高い崖から眼下に広がる森林を見渡しても、緑の葉の間から、真っ黒な幹が何本も透いて見える。そのあたりの一番高い場所には監視塔が建てられ、緊急の場合のヘリポートに設定された巨岩もある。このあたり、どこに車を走らせても黒い森林から逃れることができない。実に広範囲の火災だったことが分かる。しかし黒い幹の先に伸びる枝からは緑の葉が元気よく伸びる。今年はこのあたりは干ばつで植物が生き延びるのもきついはずだが、その生命力は驚異的だ。
てよく見ると表皮が墨になって焼けこげている。見晴らしの良い場所に来て車を止めて周りの人に聞いてみると、1年前にVictoria州は大規模な森林火災に襲われて、ひどい被害を受けたのだという。なるほど高い崖から眼下に広がる森林を見渡しても、緑の葉の間から、真っ黒な幹が何本も透いて見える。そのあたりの一番高い場所には監視塔が建てられ、緊急の場合のヘリポートに設定された巨岩もある。このあたり、どこに車を走らせても黒い森林から逃れることができない。実に広範囲の火災だったことが分かる。しかし黒い幹の先に伸びる枝からは緑の葉が元気よく伸びる。今年はこのあたりは干ばつで植物が生き延びるのもきついはずだが、その生命力は驚異的だ。