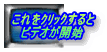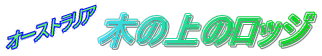
タスマニア島の西より、クレイドル山国立公園の近くの原生林の奥深くに高い木の上に作られたロッジがある。インターネットで予約して 泊まってみた。C137、C136号線の対抗2車線の細い道をかなり進んでいると看板が出た。更に未舗装の山道で8キロ先だという。高くそびえる樹林が道の両側から迫っている砂利道だが車の乗り心地はそれほど悪くはない。距離を示す丁寧な案内板をたどっていくと、樹林の間から、奇妙なロッジが見えてきた。まだ正午近くだったが早速チェックイン。ネットのページで見たような木の上に作られたロッジ(treetop lodges)で急斜面のがけに太い丸太を何本も立ててそれに支えられたロッジが並んでいる。入り口は山の上の普通の地面から入れるようになっているが、部屋は宙に浮いているような感じで、歩くと少しゆれる。部屋にはベッドとソファの他には太い煙突のついた暖炉があるが、冷蔵庫や湯沸しの電気ポットなどは木製のキャビネットの中に隠されていて、けばけばしい文明の利器が目に触れないように気を使ってあ
泊まってみた。C137、C136号線の対抗2車線の細い道をかなり進んでいると看板が出た。更に未舗装の山道で8キロ先だという。高くそびえる樹林が道の両側から迫っている砂利道だが車の乗り心地はそれほど悪くはない。距離を示す丁寧な案内板をたどっていくと、樹林の間から、奇妙なロッジが見えてきた。まだ正午近くだったが早速チェックイン。ネットのページで見たような木の上に作られたロッジ(treetop lodges)で急斜面のがけに太い丸太を何本も立ててそれに支えられたロッジが並んでいる。入り口は山の上の普通の地面から入れるようになっているが、部屋は宙に浮いているような感じで、歩くと少しゆれる。部屋にはベッドとソファの他には太い煙突のついた暖炉があるが、冷蔵庫や湯沸しの電気ポットなどは木製のキャビネットの中に隠されていて、けばけばしい文明の利器が目に触れないように気を使ってあ る。もちろんテレビ、電話、時計、などは全くない。ベランダから隣のロッジをみると斜めに渡した丸太に支えられただけの同じ様なベランダが見えて大丈夫かなと思う。しかしベランダの柵も、節目が突き出した小枝を皮のついたまま並べたもので、まさに野生の真ん中にいるようだ。ロッジはタスマニアの原生林に囲まれていて、大きなユーカリの幹から剥がれ落ちた樹皮が下の大きな枝に枯れて引っかかっている。見下ろすと地面近くは大きな羊歯(しだ)の海。静寂そのもので、何百年も前に戻ったようだ。ほとんどが砂漠のはずのオーストラリアにこんな原生林の世界があるのを見つけるのはうれしいものだ。
る。もちろんテレビ、電話、時計、などは全くない。ベランダから隣のロッジをみると斜めに渡した丸太に支えられただけの同じ様なベランダが見えて大丈夫かなと思う。しかしベランダの柵も、節目が突き出した小枝を皮のついたまま並べたもので、まさに野生の真ん中にいるようだ。ロッジはタスマニアの原生林に囲まれていて、大きなユーカリの幹から剥がれ落ちた樹皮が下の大きな枝に枯れて引っかかっている。見下ろすと地面近くは大きな羊歯(しだ)の海。静寂そのもので、何百年も前に戻ったようだ。ほとんどが砂漠のはずのオーストラリアにこんな原生林の世界があるのを見つけるのはうれしいものだ。
ロッジの付近の原生林の森の中は、浩然の気を歩いて実感できるように山道が通っている。高低差があるところは木製の足場がついていて、その上をトカゲがすばやく行き来するが蛇などは来ないのでホッとする。このあたりはシダの成長がものすごい。Tree Fernといって棕櫚のような形の幹から大きな羽を広げるようにシダの葉が無数に広がり重なり合う。今年は雨が降らなかったせいか枯れた羊歯が目に付く。静かな森に甲高い鳥の鳴き声だけが響く。突然目の前にとてつもな い巨木が現れる。上を見ても周りの樹木の枝が邪魔しててっぺんも見えない。ルートを見失わないように、山道に沿って小さな赤い蛍光版のようなものが幹につけてあってそれを辿っていけば迷わずにロッジに戻れるような仕掛けになっている。途中にはバーベキューもできるような場所も作ってあって、そばには渓流が走り、きれいな山水も利用できる。その川べりに小さな小屋があり、中では小さな発電機が回っていた。かなり上から太目のパイプで山水を落とし、そのエネルギーで発電しているようだ。その電気は地中に埋めたケーブルで先ほどのロッジにつなぎ、そこのロッジのすべての電気をまかなっているという。原生林の中に一箇所しかないロッジなので、エコ・ツーリズムを実行しているらしい。
い巨木が現れる。上を見ても周りの樹木の枝が邪魔しててっぺんも見えない。ルートを見失わないように、山道に沿って小さな赤い蛍光版のようなものが幹につけてあってそれを辿っていけば迷わずにロッジに戻れるような仕掛けになっている。途中にはバーベキューもできるような場所も作ってあって、そばには渓流が走り、きれいな山水も利用できる。その川べりに小さな小屋があり、中では小さな発電機が回っていた。かなり上から太目のパイプで山水を落とし、そのエネルギーで発電しているようだ。その電気は地中に埋めたケーブルで先ほどのロッジにつなぎ、そこのロッジのすべての電気をまかなっているという。原生林の中に一箇所しかないロッジなので、エコ・ツーリズムを実行しているらしい。
山の中の一軒宿なので、一番近いスーパーでも車で30分以上か かるという。部屋にはキッチンもついていないし、宿にはレストランもあるので、今日はそこで「外食」。交通不便な分値段は高い。でも丸太小屋の大部屋を思わせる食堂の各テーブルにはローソクが立てられ、白いテーブルクロス。窓の外はユーカリの林。そこで安いグラスワインと鹿の肉のステーキをすすめられて食べてみる。柔らかくて癖もなくうまい。でもワインとステーキで約40ドル。つぎつぎに泊り客は食事に来る。老夫婦が多いが、ワインのビンを持ち込んで飲んでいるカップルもある。犯罪者の集団から出発した国のせいか、ここでは、酒に関して妙なこだわりがあり、レストランでも厳しいライセンスを取らないとビールさえも出せない。だからBYO (Bring Your Own)といって自分で飲む酒をレストランに持ち込んで飲む習慣がある。確かにその方がお客は好みに合わせて適当な量の酒を安く飲めるので合理的だが、われわれはつい忘れてしまう。
かるという。部屋にはキッチンもついていないし、宿にはレストランもあるので、今日はそこで「外食」。交通不便な分値段は高い。でも丸太小屋の大部屋を思わせる食堂の各テーブルにはローソクが立てられ、白いテーブルクロス。窓の外はユーカリの林。そこで安いグラスワインと鹿の肉のステーキをすすめられて食べてみる。柔らかくて癖もなくうまい。でもワインとステーキで約40ドル。つぎつぎに泊り客は食事に来る。老夫婦が多いが、ワインのビンを持ち込んで飲んでいるカップルもある。犯罪者の集団から出発した国のせいか、ここでは、酒に関して妙なこだわりがあり、レストランでも厳しいライセンスを取らないとビールさえも出せない。だからBYO (Bring Your Own)といって自分で飲む酒をレストランに持ち込んで飲む習慣がある。確かにその方がお客は好みに合わせて適当な量の酒を安く飲めるので合理的だが、われわれはつい忘れてしまう。
ここは山小屋だが、spa付とある。この国ではspaとは温泉ではなく浴槽がついていて、お風呂に入れるということだ。普通オーストラリア人はシャワーですませる習慣があり、バストイレ付き(en suite)とあってもトイレとシャワーしかついていないので、お風呂は楽しめない。部屋を歩くだけで床が揺れるような、この木の上の掘っ立て小屋でお風呂に入れるのは不思議だが風流(?)でもある。
 翌朝は珍しく雨。真夏なのに寒いので暖炉をつける。8:00朝食といわれていたのに8:00にレストランへ行くと誰もいない。上の管理人宿舎から車で駆けつけた女性が準備を始める。何でも大まかで適当に…がオーストラリア精神のようだ。時間もかなりいい加減なところがある。やがて丸太小屋の食堂が突然停電になる。水力を利用した自家発電の装置が急な雨でびっくりしたようだ。修理が完了するまでもゆっくりしたものだ。でも、久しぶりに朝食にbacon(バイコン)とeggs(ヘッグズ)がタダでつく。
翌朝は珍しく雨。真夏なのに寒いので暖炉をつける。8:00朝食といわれていたのに8:00にレストランへ行くと誰もいない。上の管理人宿舎から車で駆けつけた女性が準備を始める。何でも大まかで適当に…がオーストラリア精神のようだ。時間もかなりいい加減なところがある。やがて丸太小屋の食堂が突然停電になる。水力を利用した自家発電の装置が急な雨でびっくりしたようだ。修理が完了するまでもゆっくりしたものだ。でも、久しぶりに朝食にbacon(バイコン)とeggs(ヘッグズ)がタダでつく。
![]()
無愛想が普通のチェコ旅行のあとでは、「オーストラリア人は笑顔で親切だ」が第1印象。共産主義と資本主義が作る人間心理の差を実感する。それにしてもまわりのすべて目に入るもの聞こえてくるものが英語だけで何とかなるのは気がらくだ、と思いきや、独特のリズムで口ごもってしゃべられるオーストラリア語は英語とは思えないこともある。
ローンセストンでBackpackers Hubという安宿に泊まる。受付の若者は、我々が2人で泊まるのに「鍵が1つでいいか?」と聞くのに「ワンケイ?」(One key?)という。最初何のことかわからなかった。I’m going to hospital todayがI’m going to hospital to dieと聞こえるといってオーストラリアに来る英米人は笑うが、英語の「エイ」が豪州語では「アイ」に近く発声されるだけではない。「アイ」は「オイ」に近く聞こえるし、さっきのように「イー」は「エイ」になる。つまりmateがmightに、keyはKに、lineはloinに聞こえるので、英語のつもりで聞いていると、早い流れの中で言葉のイメージが混乱して理解できなくなり、たぶん英米人でも大変だと思われる。その他、豪州人が人に会った時の挨拶「ガッダイ マイト」(Good day, mate.)は発音を別にしても、この表現自体、オーストラリア以外ではあまり聞かない。Thank youに対してもNo worriesと答える人がほとんどで、You are welcomeなどはまず聞かない。舗装道路はpaved roadと言わずに必ずsealed roadという。その他、Don’t you?が「ドンチャ」に、NoがNowに聞こえるし、rはwに、tはdに近く聞こえることがある。だからtradeはtwade、waterはwaderに聞こえ、tiltはchilledに聞こえるといった具合できりがない。つまりここでは英語が話されていることにはなってはいるが、英語とは違う「オーストラリア語」の世界といったほうがいい。実際、ホバートのバプ・ガイドのように、オーストラリア人以外の観光客が集まる場所では、意識的にイギリス人のガイドを使うこともしているようだ。こういう状況も知らずに、英語留学と称してオーストラリアに来る日本人が果たして「英語」を習得して帰れるのか甚だあやしいものだ。
この現象は、こちらへ送られてきた囚人がほとんどロンドンの下層階級で、ロンドンの下町方言(cockney)を話したのでそれがこちらで広まったせいだと一般には言われている。しかしこの150年間ここで使用されているうちに、オーストラリア独自の言葉に変わった。これからは私の独断だが、イギリスより一般に高温な気候のオーストラリアでは、口の周りの筋肉も弛緩していて動きやすく、口を開けかげんに発声されるのではないか。従って口をあまり開かないはずのエイが開き気味のアイになり、イーなども少し開いてエイになるのではないかと考えた。ついでだが、この逆の現象が、寒い東北地方でエをイに近く発声することだろう。
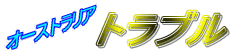
先のゴードン河クルーズは予約が必要だとネットに出ていたので、日本からSkype電話を入れておいた。前日電話予約を再確認しておこうと、Gordon River World
Heritage Cruisesと書いてある案内所に 入る。クルーズは一人80ドルと高価なのだが、35ドルで参加できるはずのカードがあったので、そのカードの案内書にしたがって申し込んだのだが、カードが通用しないという。約束が違うじゃないかといろいろやりあっているうちに、全く同じ名前で隣の店でやっている船会社がそれであることが分かり、すっかり予約を乗り換えて、万事うまく行った。だがカードの書類に書かれた電話番号は最初にけんかしたエイジェントのものであることは確認していたし、新しいエイジェントでもそのあたりはあいまいで、いいかげんだった。観光に力を入れている割には、きちんとしたことが出来にくい国だ。
入る。クルーズは一人80ドルと高価なのだが、35ドルで参加できるはずのカードがあったので、そのカードの案内書にしたがって申し込んだのだが、カードが通用しないという。約束が違うじゃないかといろいろやりあっているうちに、全く同じ名前で隣の店でやっている船会社がそれであることが分かり、すっかり予約を乗り換えて、万事うまく行った。だがカードの書類に書かれた電話番号は最初にけんかしたエイジェントのものであることは確認していたし、新しいエイジェントでもそのあたりはあいまいで、いいかげんだった。観光に力を入れている割には、きちんとしたことが出来にくい国だ。
タスマニアのローンセストンを去ってメルボルンへ戻る日に、飛行機の時間まですこし余裕があったので、近くのFlanklin House という旧家を見学に行った。例によってSee
Tasmania Cardを出し、係員がカードを機械に差し込んで、処理している間に、博物館になっているところを見て回っていた。しばらくして、その庭園をまわっているときに、その係員が走って飛んできた。カードはもう使用期限が過ぎているという。そんなはずはないと押し問答になった。確か一週間通用のカードで、買ったときに説明をうけたのは最初に使ったときから、時間で計算が始まり、その1週間後で切れると聞いた。つまり最初の日は午後2時ころから使い始めたので、7日後の午前中はまだ有効期間のはずだったので、その旨を説明した。「でも機械にかけると期限切れ」と出るという。私も最初の日に受けた説明を繰り返して主張した。その係員は、仕方がないと思ったようで、「よかったら、その募金箱に多少のお金をいれていただくということで、これはいいことにしましょう」と向こうの小さな箱を指差しながらその場をおさめて消えた。もちろん募金箱には何も入れなかったが、これもオーストラリア方式の融通のつけ方かもしれない。
<このページ上部へ移動>
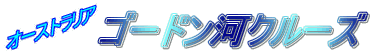
タスマニア島西海岸は1年に300日は雨が降る原生雨林地帯なの に今日は雲ひとつない青空から灼熱の太陽が照りつける。タスマニアの太陽は紫外線が強く危険だとは聞かされていたが日焼け止めも用意していない。しかし今日はここ西海岸にあるゴードン河をさかのぼって世界遺産の雨林地帯を探検するクルーズに参加する。料金は昼食込みで80ドルだが、例のSee-Tasmaniaカードで35ドルになる。船着場に着くと真っ白でモダンなデザインの大きな双胴船が桟橋に待機している。まるでレストランに入ったときのように、船の入り口に案内嬢がいて一人ひとり指定の座席まで案内してくれる。ジャンボ機のビズネスクラスのような差席配置だが、真ん中の4列の座席は眺望を良くするために1段高くせり上げてある。前方と両側窓はもちろん大きく、真ん中には無料のドリンクバーもあり、何だか展望台付の応接間がそのまま動いていくといった感じだ。しかも大自然の真っ只中に。
に今日は雲ひとつない青空から灼熱の太陽が照りつける。タスマニアの太陽は紫外線が強く危険だとは聞かされていたが日焼け止めも用意していない。しかし今日はここ西海岸にあるゴードン河をさかのぼって世界遺産の雨林地帯を探検するクルーズに参加する。料金は昼食込みで80ドルだが、例のSee-Tasmaniaカードで35ドルになる。船着場に着くと真っ白でモダンなデザインの大きな双胴船が桟橋に待機している。まるでレストランに入ったときのように、船の入り口に案内嬢がいて一人ひとり指定の座席まで案内してくれる。ジャンボ機のビズネスクラスのような差席配置だが、真ん中の4列の座席は眺望を良くするために1段高くせり上げてある。前方と両側窓はもちろん大きく、真ん中には無料のドリンクバーもあり、何だか展望台付の応接間がそのまま動いていくといった感じだ。しかも大自然の真っ只中に。
定刻に岸壁を離れた高速双胴船はしばらく様子を見ていたがやがて60キロのスピードで飛ばしマッコーリー・ハーバーといわれる広大な湾を横切る。前方の甲板に出ると、真夏の太陽の下でも、寒いほどだ。それに向かい風だと呼吸するのも困難なくらい。隣の人が「ペンギンがいた」と騒いでいる。ガイド嬢が出てきて、イルカもよく現れるという。ま もなく船はスピードを落とし、舳先をまげて、手付かずの自然がそのままのゴードン河河口に入る。途端に船の両側には原生林が迫ってくる。ぎっしりと詰まった木々は太陽を求めて枝を伸ばしているのがよく分かる。緑に輝いている樹木もあるが、色あせた不景気なもの、すっかり枯れて白い枝と幹をさらしているものも見える。森が下の川面と接するところでは、枯れた大木が横倒しになって重なっている。風が深緑の川面にさざ波を立てる。その中を船は音もなくすべるようにゆっくりと進む。気がつくと周りにいた人たちがすっかり消えてキャビンに移ったようだ。このあたり何十キロ四方にわたって人間はいないし、人の手も入っていない世界自然遺産保護区域だ。何千年も続いた深い大自然の真ん中に、地球には新入りの自分が一人でいるような不思議な気分になる。
もなく船はスピードを落とし、舳先をまげて、手付かずの自然がそのままのゴードン河河口に入る。途端に船の両側には原生林が迫ってくる。ぎっしりと詰まった木々は太陽を求めて枝を伸ばしているのがよく分かる。緑に輝いている樹木もあるが、色あせた不景気なもの、すっかり枯れて白い枝と幹をさらしているものも見える。森が下の川面と接するところでは、枯れた大木が横倒しになって重なっている。風が深緑の川面にさざ波を立てる。その中を船は音もなくすべるようにゆっくりと進む。気がつくと周りにいた人たちがすっかり消えてキャビンに移ったようだ。このあたり何十キロ四方にわたって人間はいないし、人の手も入っていない世界自然遺産保護区域だ。何千年も続いた深い大自然の真ん中に、地球には新入りの自分が一人でいるような不思議な気分になる。

しばらく船はそのまま進む。河口からもう1時間も入っただろうか。河がやや細くなった森の脇に、丸太を何本か組み合わせただけの船着場が見えてくる。船はエンジンを逆噴射させて接岸。乗客は船を下りて、雨林の中に作られた木製の歩道を奥に進む。両側には昼なお暗い樹林が続く。太さもさまざまな木々がもつれるように上に伸びて、その下では朽ちた老木が横倒しになり、その形をとどめない老木にはコケが一面にまとわりついている。縦横に走る幹の間には、太いくもの巣のような植物が絡まりながら広がる。植物が生存競争を繰り広げる原型をみる。文字通り大変な葛藤の中で、本来動けない植物は、それでも手足のような枝を伸ばしあい、お互い に闘争をしているようだ。生まれたその場所で、そのまま成長し、その場所で倒れてほかの樹木やコケの餌になるか、斜面を転がって河辺で骸骨のように白い朽ちた姿をさらす。とても人間が手を出せる場所ではない。
に闘争をしているようだ。生まれたその場所で、そのまま成長し、その場所で倒れてほかの樹木やコケの餌になるか、斜面を転がって河辺で骸骨のように白い朽ちた姿をさらす。とても人間が手を出せる場所ではない。
ゴードン河への途中にサラ島という小さな島がある。これはタスマニア島に送られた犯罪者のうちの重罪犯を隔離するための場所として使われた。周囲たった21キロの小さな島だが、椰子の木が茂り、青い 海と空に囲まれたきれいな空気の大自然で、一見キャンプ地としては理想的な場所だ。だがここはポート・アーサーに監獄が出来る前に重罪犯を収容した監獄の島だ。この付近にはHuon Pineという大木が育ち、それを利用して造船が行われた。Huon Pineは150年経っても人の腰くらいの高さにしかならない木で耐水性がある。3万年も樹齢を重ねて倒れた大木が地中から掘り出されたときでさえ、まだ船の材料として使えたという奇跡的な木でもある。囚人たちは奴隷として造船に使役された。そしてここで造りだされる優れた船は評判になった。しかし一方重罪犯に対する鞭打ちなども年に8000回も行われ、囚人には地獄の島として恐れられた。
海と空に囲まれたきれいな空気の大自然で、一見キャンプ地としては理想的な場所だ。だがここはポート・アーサーに監獄が出来る前に重罪犯を収容した監獄の島だ。この付近にはHuon Pineという大木が育ち、それを利用して造船が行われた。Huon Pineは150年経っても人の腰くらいの高さにしかならない木で耐水性がある。3万年も樹齢を重ねて倒れた大木が地中から掘り出されたときでさえ、まだ船の材料として使えたという奇跡的な木でもある。囚人たちは奴隷として造船に使役された。そしてここで造りだされる優れた船は評判になった。しかし一方重罪犯に対する鞭打ちなども年に8000回も行われ、囚人には地獄の島として恐れられた。
 サラ島にはまだ崩れかけた独房が残っているが、それは鞭打ちより残酷なものとして囚人には恐れられたという。電気もなく何も置かれてない島の独房だから、文字通り暗黒・無音の世界になる夜を含めて24時間全くの孤独に置かれる。1日1度だけ看守が入ってきて、500gのパンと水を置いて消えていく。その状態に何日も置かれると、大抵の囚人は気が狂って死んでいったという。しかし、管理者はそれを知っていて、さらに独房の数を増やしたそうだ。
サラ島にはまだ崩れかけた独房が残っているが、それは鞭打ちより残酷なものとして囚人には恐れられたという。電気もなく何も置かれてない島の独房だから、文字通り暗黒・無音の世界になる夜を含めて24時間全くの孤独に置かれる。1日1度だけ看守が入ってきて、500gのパンと水を置いて消えていく。その状態に何日も置かれると、大抵の囚人は気が狂って死んでいったという。しかし、管理者はそれを知っていて、さらに独房の数を増やしたそうだ。

牧場の一部を切り取ってきれいな墓地が作られている。小さな均整の取れた墓石の周りには一面に花が飾られている。そのすぐそばで牛 の群れがガリッと音を立てながら草を食む。牧童の人生を過ごした人は牛のすぐ側に埋められていて、牛に守られているという感じがいい。
の群れがガリッと音を立てながら草を食む。牧童の人生を過ごした人は牛のすぐ側に埋められていて、牛に守られているという感じがいい。
遠くの牧場では小さな黒い岩の塊のようなものが点在する。近づくとそれらは毛を刈り取られた羊だと判明する。真夏なので羊も洋服を脱いでさっぱり…ということだろうが、この強い紫外線の下で日陰もないところでは羊も皮膚がんにならないかと心配になる。
今日泊まるのはタスマニア東海岸のフレシネット国立公園の近くにあるRedcliff HouseというファームのBBだ。説明によるとこの牧場も囚人の労働で作られたものだという。実際居間には昔のここの様子が大 きな写真にして貼ってあるし、歴史的な遺品がずいぶんおかれている。最近まで羊を飼っていたようだが今では売り払ったようで、BBが中心のようだ。この農場が所有する東京ドームの1.2倍の広さがある牧場を歩いてみた。乾燥して草がほとんど生えていない。しかしよく見ると大きな黒豆のような羊の糞がほとんど隙間もないほど落ちている。羊は自分の糞の間から生えてくるわずかの草を探して食べていたらしい。聞いてみると、牧場は羊を飼っている農家に貸して使わせているそうだ。地下水を利用する機械設備を入れる余裕はなく、屋根の雨水をタンクにためるだけの給水施設なので、水不足になると深刻だ。化繊の普及にともない、羊毛の値段も下がる一方で、一見何の作業も要らないように見える羊を飼うという仕事も大変なことなのだと思った。だからこの広大な農家も売りに出されていた。女主人に事情を聞いてみると、やはり夫婦が年を取って、体力が続かなくなり、同時に都会の便利さと楽しみのある生活をしたいという。ここに移ってBBを始めてまだ4年にしかならないという。一見大自然に恵まれて、広大な土地を支配して、気持ちよく暮らしているように見えるのに、4年もするとあきがくるということらしい。あえて売値を聞いてみると、すべての牧場や由緒ある家屋をすべて含めて、1億1400万円とのこと。「私がオーストラリア人の成功者なら買いたいところだがね…」とかってなことをいったら真剣な顔になり、「確かに日本からだとちょっと遠すぎますか」と残念そうだった。
きな写真にして貼ってあるし、歴史的な遺品がずいぶんおかれている。最近まで羊を飼っていたようだが今では売り払ったようで、BBが中心のようだ。この農場が所有する東京ドームの1.2倍の広さがある牧場を歩いてみた。乾燥して草がほとんど生えていない。しかしよく見ると大きな黒豆のような羊の糞がほとんど隙間もないほど落ちている。羊は自分の糞の間から生えてくるわずかの草を探して食べていたらしい。聞いてみると、牧場は羊を飼っている農家に貸して使わせているそうだ。地下水を利用する機械設備を入れる余裕はなく、屋根の雨水をタンクにためるだけの給水施設なので、水不足になると深刻だ。化繊の普及にともない、羊毛の値段も下がる一方で、一見何の作業も要らないように見える羊を飼うという仕事も大変なことなのだと思った。だからこの広大な農家も売りに出されていた。女主人に事情を聞いてみると、やはり夫婦が年を取って、体力が続かなくなり、同時に都会の便利さと楽しみのある生活をしたいという。ここに移ってBBを始めてまだ4年にしかならないという。一見大自然に恵まれて、広大な土地を支配して、気持ちよく暮らしているように見えるのに、4年もするとあきがくるということらしい。あえて売値を聞いてみると、すべての牧場や由緒ある家屋をすべて含めて、1億1400万円とのこと。「私がオーストラリア人の成功者なら買いたいところだがね…」とかってなことをいったら真剣な顔になり、「確かに日本からだとちょっと遠すぎますか」と残念そうだった。

このBBの同宿者にRon & Fay Toobyというメルボルンから来た夫婦がいた。気さくな人で話しているうちに私と同じ年だと分かると肩を組んで写真を撮った。弟が2才年下だと分かると、ワザとコケにしてBaby(バイビー), Baby(バイビー)!とからかい。「《こんなアホな奴がオーストラリアいたよ》と、日本に帰ったら写真を見せて伝えてくれ」というので、「《オーストラリアの首相に会って来たよ》と言って見せるよ」と言うと、少し顔を赤らめた。でも彼はオーストラリアからベトナム戦争に兵役として参戦したと言った。日本の憲法がもっと早く「改正」されていたら、私も多分同じ運命で戦死していたかもしれないと思った。
Victoria州西方のGrampians国立公園のMackenzie Fallsというと ころに行ってみる。この辺りでは珍しく川が峡谷を作り、岩が壁を作っているところで滝になっている。岩壁は凸凹で滝の白い水に変化を与え、30メートルくらいの高さの面白いレースのカーテンを作る。 その滝つぼのところは大きな深い池になっていて若者がみな泳いで楽しんでいる。年配夫婦も助け合いながら泳いでいく。滝に打たれながら「修行」していて、冷たさに耐えられず悲鳴をあげている人がいる。ビキニ姿の若い女性が一人で滝に打たれながら衆目の監視に笑って耐えているのは、さすがにオーストラリア人だ。しかし、近くには大きな看板があり、「水泳禁止」となっているが注意する人もいない。オースとリラリア流の余計なことを気にしない(easy-going)自由な生き方なのだろうか。
ころに行ってみる。この辺りでは珍しく川が峡谷を作り、岩が壁を作っているところで滝になっている。岩壁は凸凹で滝の白い水に変化を与え、30メートルくらいの高さの面白いレースのカーテンを作る。 その滝つぼのところは大きな深い池になっていて若者がみな泳いで楽しんでいる。年配夫婦も助け合いながら泳いでいく。滝に打たれながら「修行」していて、冷たさに耐えられず悲鳴をあげている人がいる。ビキニ姿の若い女性が一人で滝に打たれながら衆目の監視に笑って耐えているのは、さすがにオーストラリア人だ。しかし、近くには大きな看板があり、「水泳禁止」となっているが注意する人もいない。オースとリラリア流の余計なことを気にしない(easy-going)自由な生き方なのだろうか。
 ギンが群れを成して夕方あがってくる自然の海岸をみなで見物するのが有名な島だが、我々は夕方までいるつもりもなく、岬の自然を楽しむだけだ。海岸の岸壁に沿って木製の歩道が完備していて、通路以外に人間が入り込めないように工夫されているので、岸壁の弱弱しい植物も自生していて、そこに点在する鳥の巣も守られている。波が荒いので、海岸が削り取られて、ゴツゴツしているだけでなく、波の力で大きな洞穴まで形成されるほどだ。「ベルギー」の文字が英語で入った野球帽をかぶっていたら、通りがかりの若者が、「Hullo, Belgium!」と声をかけてきた。「Hullo,
Australia!(オーストライリア)」と返してやった。海を巡る木製の歩道はよく考えてあり、階段の代わりにスロープなので、乳母車や車椅子の観光客も目立つ。
ギンが群れを成して夕方あがってくる自然の海岸をみなで見物するのが有名な島だが、我々は夕方までいるつもりもなく、岬の自然を楽しむだけだ。海岸の岸壁に沿って木製の歩道が完備していて、通路以外に人間が入り込めないように工夫されているので、岸壁の弱弱しい植物も自生していて、そこに点在する鳥の巣も守られている。波が荒いので、海岸が削り取られて、ゴツゴツしているだけでなく、波の力で大きな洞穴まで形成されるほどだ。「ベルギー」の文字が英語で入った野球帽をかぶっていたら、通りがかりの若者が、「Hullo, Belgium!」と声をかけてきた。「Hullo,
Australia!(オーストライリア)」と返してやった。海を巡る木製の歩道はよく考えてあり、階段の代わりにスロープなので、乳母車や車椅子の観光客も目立つ。