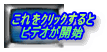路線バスでポルトガル南端のサレマへ行くため、リスボンのレテ・リオス発着所へ向かう。地下鉄のジャルダン・ズーロジコ駅で降りて、あたりをキョロキョロ見てみるが。バスは見えない。早速、変なポルトガル語を試してみるか... 通りかかった人に“Perdao.”(=Excuse me.)と呼び止めておいて、おもむろに“Onde fica a estacao de autocarrro?”(=Where is the bus depot?)
と言ってみる。“Ah, autocarro.”と言って、バスの駅が見えるところまで連れて行ってくれた。 “Muito obrigado.”(=Thank you) “De nada”(=Oh, it’s nothing.)となり、通じた。やれやれ。皆本当に親切だ。
切符売り場は英語が通じるが、もらった切符はポルトガル語だけ。そこでベンチに座って、 持ってきた「ポルトガル語-英語辞典」で調べる。行き先のLagosや出発時間の10:30はすぐわかるが、Viatura:92とあるのはCar-number:92で、Lugar:3はSeat-number:3らしい。つまり92番バスを見つけて座席番号3に座ればいい。電光掲示板は空港と同じでPartida(出発)とChegada(到着)に分かれて、バスの出発(到着)ホーム(Linha)を示してくれるので分かりよい。結局あとでバスの番号はどうでもよく、掲示板に出るプラットホーム番号が大切と分かるが、プラットホームも20くらいあって随分混雑している。バスは日本の高速道路を走る路線バスとほぼ同じで、客席が高くクッションも良くて、快適。でも、南のLogosまで4時間走って15ユーロ(2000円位)なので高くない。その上このコースではどういうわけか若い女性の車掌もついて、車内でエスプレッソのコーヒーまで出してくれた。ただ、
持ってきた「ポルトガル語-英語辞典」で調べる。行き先のLagosや出発時間の10:30はすぐわかるが、Viatura:92とあるのはCar-number:92で、Lugar:3はSeat-number:3らしい。つまり92番バスを見つけて座席番号3に座ればいい。電光掲示板は空港と同じでPartida(出発)とChegada(到着)に分かれて、バスの出発(到着)ホーム(Linha)を示してくれるので分かりよい。結局あとでバスの番号はどうでもよく、掲示板に出るプラットホーム番号が大切と分かるが、プラットホームも20くらいあって随分混雑している。バスは日本の高速道路を走る路線バスとほぼ同じで、客席が高くクッションも良くて、快適。でも、南のLogosまで4時間走って15ユーロ(2000円位)なので高くない。その上このコースではどういうわけか若い女性の車掌もついて、車内でエスプレッソのコーヒーまで出してくれた。ただ、 サービスのつもりか、テレビとうるさい音楽を運転手の趣味でかけっぱなし。そう言えば、Rickの本には、気になる人は耳栓を持っていった方がいいと書いてあったっけ。
サービスのつもりか、テレビとうるさい音楽を運転手の趣味でかけっぱなし。そう言えば、Rickの本には、気になる人は耳栓を持っていった方がいいと書いてあったっけ。
南部のAlgarve地方は路線バスがあまり便利ではない。仕方がないので、レンタカーを借りようと思ってLagosを歩いていたら、Luzcarという地元のレンタカーが目に付く。入って聞いてみると完全な保険を付けて3日で65ユーロだという。これだと1日3000円以下ということになり安い。しかも見せられた車はルノーのClioという新車。早速契約して乗ったのはいいが、オートマ車に慣れていたため、マニュアル車と知りつつクラッチを踏むのを忘れて変速機でガガーといわせてしまう。びっくりして店員が振り返ったが、笑っている。日本人だから車は大丈夫と信頼していた様子だったのに裏切ってしまった。でも一旦慣れてしまうとマニュアル車で右側通行も快適だ。
Lagosから西Salemaへ向かう道は車も少なく、広くて緑の中を走っていて気持ちがいい 。Salemaの海岸はリゾートではない。日本語の案内書でも全く無視されている漁村。だから日本人は1人もいない。素朴なポルトガルの漁村の感じがそのまま。海岸に平行して走るメインストリートも巾が4m位しかなく、数軒の小さな店があるだけ。その石畳を歩いていると、家と家の間から海岸が見えて、その向こうに真っ青な海がのぞまれる。作家・壇一雄が長く滞在したというSanta Cruzも漁村だったらしいが、リスボンの近くだから今はリゾート地になり、最果てのこことは全く違う姿だろう。ポルトガル南端の海岸も現在ではほとんどがリゾート化していて、1800年前アフリカからムーア人が住み着いたときの姿をとどめているのは、このSalemaから西のSagresまでだけだという。その素朴さからアダムとイブの世界に帰るというのか、この隣のFigueiraの海岸などは夏になるとトップレスやヌーディストの場所にもなるらしい。
。Salemaの海岸はリゾートではない。日本語の案内書でも全く無視されている漁村。だから日本人は1人もいない。素朴なポルトガルの漁村の感じがそのまま。海岸に平行して走るメインストリートも巾が4m位しかなく、数軒の小さな店があるだけ。その石畳を歩いていると、家と家の間から海岸が見えて、その向こうに真っ青な海がのぞまれる。作家・壇一雄が長く滞在したというSanta Cruzも漁村だったらしいが、リスボンの近くだから今はリゾート地になり、最果てのこことは全く違う姿だろう。ポルトガル南端の海岸も現在ではほとんどがリゾート化していて、1800年前アフリカからムーア人が住み着いたときの姿をとどめているのは、このSalemaから西のSagresまでだけだという。その素朴さからアダムとイブの世界に帰るというのか、この隣のFigueiraの海岸などは夏になるとトップレスやヌーディストの場所にもなるらしい。
Rickが推薦するペンションは海岸から100mほど入った小高い丘の上の真っ白い家だ。道路から階段を上がっていくと、ほとんど同時にアメリカ人夫婦が到着した。聞くと、彼らもRickの本に引かれて、そのコースを私と反対周りでたどってきたという。やがて、宿の主人Johnが現れた。きれいな英語だ。夕食のためのレストランを推薦してもらって、部屋を案内してもらう。私は申し込みが遅かったので3階のやや狭い部屋。だからベッドが高い位 置にあって短いハシゴで上る。ベッドの部分は屋根裏部屋の感じで、目の前の斜めになった天井に小さなガラス窓が埋め込まれていて、寝ていると星空が見える。朝になると窓には露がたまる。しかし、ハシゴを降りると目の前の大きな窓の向こうに青い海が一面に広がり、更にベランダに出ると海岸も迫ってくる。
置にあって短いハシゴで上る。ベッドの部分は屋根裏部屋の感じで、目の前の斜めになった天井に小さなガラス窓が埋め込まれていて、寝ていると星空が見える。朝になると窓には露がたまる。しかし、ハシゴを降りると目の前の大きな窓の向こうに青い海が一面に広がり、更にベランダに出ると海岸も迫ってくる。
Rickの本を見せると10%引きで40ユーロを朝食付きで36ユーロにしてくれる。その朝食がすばらしい。よく知られているように、ヨーロッパのContinental breakfastというのはパンとコーヒー(紅茶)だけというのが普通。ここではジュースやコーンフレークスや種々の果物の類はもちろん、ハムエッグや半熟卵まで作ってくれる上に、パンはご主人のお手製で種類も豊富。ジャムも奥さんお手製のものを含めて、15種類くらいはある。更にお客のその日の予定を聞きながら、自分で作ったその付近のカラー写真入りの案内パンフを渡しながら、詳しく説明してくれる。
 とにかくヨーロッパ大陸南西の突端Sagresの岬に行ってみる。荒涼とした岬の先端に要塞がある。広々とした城壁の内側に錆付いた大砲が海に向いている。攻めてくるムーア人を想定しているのであろうか。城壁から身を乗り出して下を見ると、所々鳥の糞で白くなった黒い断崖が続き、その先には海辺がずっと先まで伸びている。青い海は海岸の100m以上手前から波が砕けて白い波に変わり、そのまま海岸の方向に進むが、まだ届かぬうちに次の白い波が更に大きく上から覆いかぶさる。この壮観さは多分この2000年位変わっていないのだろう。ポルトガルを世界の覇者にしたエンリケ王子も500年前にこの要塞で最期を遂げた。
とにかくヨーロッパ大陸南西の突端Sagresの岬に行ってみる。荒涼とした岬の先端に要塞がある。広々とした城壁の内側に錆付いた大砲が海に向いている。攻めてくるムーア人を想定しているのであろうか。城壁から身を乗り出して下を見ると、所々鳥の糞で白くなった黒い断崖が続き、その先には海辺がずっと先まで伸びている。青い海は海岸の100m以上手前から波が砕けて白い波に変わり、そのまま海岸の方向に進むが、まだ届かぬうちに次の白い波が更に大きく上から覆いかぶさる。この壮観さは多分この2000年位変わっていないのだろう。ポルトガルを世界の覇者にしたエンリケ王子も500年前にこの要塞で最期を遂げた。
岬の付近は断崖になっているのに手すりや柵など全くない。飛び込み(?)自由なのに、気にする人もいないようだ。そのすぐ近くの荒涼とした場所一面にセーター、マフラー、帽子などの毛糸製品を並べて売っている。家一軒ない荒 地なので、カラフルな毛糸が目立つ。分厚いセーターが全部25ユーロ。家内に1つどうかと思うというと、ヘソを出しルックの日焼けした元気のいい女性が、勢いよく、次々と着て見せてくれる。野外だから手や体を振り回してもぶっつかるものもない。すごいエネルギー。
地なので、カラフルな毛糸が目立つ。分厚いセーターが全部25ユーロ。家内に1つどうかと思うというと、ヘソを出しルックの日焼けした元気のいい女性が、勢いよく、次々と着て見せてくれる。野外だから手や体を振り回してもぶっつかるものもない。すごいエネルギー。
断崖の上、すぐ近くの見晴らしのいい場所に、国営の宿舎ポウサダがある。赤い瓦と白い壁にアーチ型の窓を付けた細長い建物だ。崖を下りたところにプライベート・ビーチのようなところがあるが、プールも備えて、広々とした静かなところ。でも料金はシングルで冬でも100ユーロと高い。ランチだけでも利用できるが、普通のレストランの倍くらいはする。普通ポウサダはこのような自然を楽しむ宿舎よりも、古城の廃墟などに手を入れて宿舎にしたものが多い。だがアイルランドなどの素朴な古城のホテルなどと違って、ポウサダは改装するときに、素朴な雰囲気を壊すのに役人が金をかけすぎて、異常に高価なホテルしてしまったものが多いように思う。

ポウサダをあとにして、サレマへ戻る途中でBispoという小さな村があった。椰子の木やユーカリの林に面して茶色の瓦に白壁の家々がまとまっている。11月でも南国の太陽は暑い。細い石畳の道を奥へ入ってみるが、人の気配がない。時計を見ると2時。そうか、シエスタ(昼寝の時間)だ。空き地では洗濯物だけが強い太陽を浴びて影を作る。写真を撮ろうと狭い道に駐車して飛び出したら、横の青いドアから中年の婦人が顔を出した。“Posso fotographar?” (=May I take a picture?)と言ったらポーズをとってくれたので、1枚。するとどこからともなく笑顔の少年が現れた。もう1枚。“Fala ingles?”(=Do you speak English?)と試してみる。“Posso.”(=I can.)と小声で言ったが、そのあと口から出たのは“Good-bye!”だけだった。また静かになった。
次の日、隣の大きな町Lagosへ出た。Bom Diaという名のヨットによる奇岩・洞窟めぐりを見つけた。2時間のクルーズで15ユーロ。 長さ30mほどの3本マストのヨット。でもエンジンつき。ヴァスコ・ダ・ガマも確か最初はこのくらいの帆船で大洋に出た。集まったお客はドイツ語を話す老夫婦ともう1組東欧系の男とアジア系の女の夫婦。それにオーストラリアから来たという若い女性と私の6人だけ。ヨットを操るのは日焼けした4人の若い男たち。風はほとんどないのにヨットはエンジンでスイスイと進む。スピードが作り出すそよ風が快い。紺碧の海、強い太陽が赤茶けた絶壁に反射してまぶしい。海面から突き出した岩に真っ黒い大きな鳥たち、白いかもめのような鳥が群がる。案内人に鳥の名前を聞いても、英語では分からないという。やがて、小さな白いボートがヨットに近づいた。足場が不安定だが、支えあって皆がそれに移動。ヨットでは行けない洞窟へ入るためだ。目の前の断崖の下にボートで入れるくらいの穴が開いている。ボートは岩に注意しながらその中に突っ込んでいく。「これはパリの凱旋門だよ」と日焼けしたガイドの声。「あれはガレージ、その向こうはトイレ、回廊、大聖堂…」とすべての洞穴にあだ名がある。中に入っても天井が抜けているところが多く、大きな洞穴という感じはしない。しかしギザギザに大きくあいた穴から真っ青な空が見える。海も、周りの岩の色との関係かエメラルド・グリーンに輝く。「見上げてみろ、煙突があるから…」とガイド。どういうわけかボーリングであけたような自然の穴が分厚い岩を貫いている。「煙突があるから、ここは台所だよ」とちょっと無理な想像をして笑わせ
長さ30mほどの3本マストのヨット。でもエンジンつき。ヴァスコ・ダ・ガマも確か最初はこのくらいの帆船で大洋に出た。集まったお客はドイツ語を話す老夫婦ともう1組東欧系の男とアジア系の女の夫婦。それにオーストラリアから来たという若い女性と私の6人だけ。ヨットを操るのは日焼けした4人の若い男たち。風はほとんどないのにヨットはエンジンでスイスイと進む。スピードが作り出すそよ風が快い。紺碧の海、強い太陽が赤茶けた絶壁に反射してまぶしい。海面から突き出した岩に真っ黒い大きな鳥たち、白いかもめのような鳥が群がる。案内人に鳥の名前を聞いても、英語では分からないという。やがて、小さな白いボートがヨットに近づいた。足場が不安定だが、支えあって皆がそれに移動。ヨットでは行けない洞窟へ入るためだ。目の前の断崖の下にボートで入れるくらいの穴が開いている。ボートは岩に注意しながらその中に突っ込んでいく。「これはパリの凱旋門だよ」と日焼けしたガイドの声。「あれはガレージ、その向こうはトイレ、回廊、大聖堂…」とすべての洞穴にあだ名がある。中に入っても天井が抜けているところが多く、大きな洞穴という感じはしない。しかしギザギザに大きくあいた穴から真っ青な空が見える。海も、周りの岩の色との関係かエメラルド・グリーンに輝く。「見上げてみろ、煙突があるから…」とガイド。どういうわけかボーリングであけたような自然の穴が分厚い岩を貫いている。「煙突があるから、ここは台所だよ」とちょっと無理な想像をして笑わせ る。地質学的にも面白そうな場所だが、ガイドからは岩に付けたあだ名以外の説明はない。もともと英語が十分でない上に興味もなさそう。わいわいやって楽しければいい…というのがポルトガル流のようだ。
る。地質学的にも面白そうな場所だが、ガイドからは岩に付けたあだ名以外の説明はない。もともと英語が十分でない上に興味もなさそう。わいわいやって楽しければいい…というのがポルトガル流のようだ。
やがて再び「母船」のヨットに戻る。クルーが3つの帆を全部張って、エンジンを止めた。静かだ。波が船に当たる音だけが聞こえる。「漂流」している気分。となりにいたオーストラリアの若い女性と話してみる。Millerさんといってメルボルンでの会社勤めをやめて、ためた金で3ヶ月のヨーロッパ一人旅をしている人だ。もともと父親がフランス人なのでフランス語もこなし、パリを振り出しに、スペイン、ポルトガルと来たらしい。これが終わったらもう1度メルボルンで教員養成学校へ行って教師になると張り切っていた。
翌日9時のエヴォラ行きのバスに乗るためラゴスのバス駅へ。1日に2本しかないバスなので、乗り遅れると大変。またMillerさんも待っている。自分はやせているのに、身体以上の大きさのバックパックをかついだ上に胸の前にもかなりのバッグを抱きかかえるようにかけて、更に手荷物も持っている。「やせた身体なのに、どうして荷物はそんなに太っているのか?」と話しかけると「みんなにそう言われるのよ」と笑った。私の軽装備に驚き、「たったそれだけ?」というから、「毎晩洗濯が大変だよ」と言ったら納得した。
町全部が世界遺産のエヴォラはリスボンから100km以上内陸に入ったアレンテジョ(Alentejo)と呼ばれる地域の中心だった。Alentejoというのはリスボンに流れる「Tejo河の背後」の地域の意味。ここはオリーブとコルクの木々が生い茂る土地の真ん中にある2000年以上の歴史を背負った場所だ。しかも、一部ローマ時代からの城壁に囲まれた内部は、中央の広場から歩いて5分か10分の範囲にすべての名所がある。
紀元前2世紀ころ、この付近の小麦や銀に目を付けたローマ帝国は、この町を支配下 に置いた。紀元1世紀ころ町の中心だった広場にはまだ14本の巨大な石柱が残っていて当時の壮大な神殿の面影を伝える。その後8世紀にムーア人に占領されて12世紀にはキリスト教徒に奪還される。リスボンと違って1755年の大地震の影響もなく、戦争で爆撃されたこともないエヴォラにはその間の2000年の歴史がそのまま奇跡的に残っている。
に置いた。紀元1世紀ころ町の中心だった広場にはまだ14本の巨大な石柱が残っていて当時の壮大な神殿の面影を伝える。その後8世紀にムーア人に占領されて12世紀にはキリスト教徒に奪還される。リスボンと違って1755年の大地震の影響もなく、戦争で爆撃されたこともないエヴォラにはその間の2000年の歴史がそのまま奇跡的に残っている。
朝10時に旅行案内所の前に集まれば、12ユーロで名所を徒歩で案内してくれるというので行ってみる。すでにカナダ人、アメリカ人、ドイツ人、スペイン人、フランス人など10人くらいが集まっている。アルファシンニャさんという65歳くらいの女性ガイドが英語とスペイン語で説明する。何しろこの狭い場所に2000年間の変遷 がいたるところで積み重なっていて、専門家でないとなかなか見分けにくい。ローマ時代の外壁が建物の中に保存されたまま、建物は事務所に使われていたり、市役所の地下でローマ浴場が急に見つかり、目下大規模に発掘中だったりする。そのローマ風呂の底には裸の女性が何人もモザイクで描かれている。昔の宮廷の馬屋だったところが、今はきれいなみやげ物屋になっていたり、ローマ時代に戦車が通った石畳がうまく補修されて新しいところと区別がつかなくなったりする。
がいたるところで積み重なっていて、専門家でないとなかなか見分けにくい。ローマ時代の外壁が建物の中に保存されたまま、建物は事務所に使われていたり、市役所の地下でローマ浴場が急に見つかり、目下大規模に発掘中だったりする。そのローマ風呂の底には裸の女性が何人もモザイクで描かれている。昔の宮廷の馬屋だったところが、今はきれいなみやげ物屋になっていたり、ローマ時代に戦車が通った石畳がうまく補修されて新しいところと区別がつかなくなったりする。
ヴァスコ・ダ・ガマが1498年にインド航路を発見してから住んでいたという家がある。一般公開されていないはずのこの家にガイドさんは裏木戸から入って案内してくれた。彼が長い航海で発見した変わった動植物を壁画として描かせたものがまだ残っている。彼の個人用の小さなチャペルがある。広い屋敷に住む大胆な冒険家なのに、こんな狭い「仏間」を設けて祈っていたのかと思う。自動車のない時代、どこにも必ず馬屋があり正面の広い場所を占めているのも印象に残る。

前もって本で読んでいたので、Inquisition(異教徒を裁く宗教裁判)はあったのかとガイドに聞いてみる。隣で聞いていたスペイン婦人が、「それはどこにでもあったわよ」とすぐに反応した。ガイドもうなずいて、早速その場所へ連れて行ってくれた。12世紀にキリスト教徒が奪還した後、ムーア人も城の外に住む場所を与えられていた。だが、そのうちユダヤ人などと共に「踏み絵」を踏ませるような「裁判」に追い込み、「有罪」にして広場に連行、数千人を焼き殺したらしい。それを記憶にとどめるため、「宗教裁判所」の前には石棺が置かれ、その中に大理石の「囚人」が横たわっている。日本ではキリスト教徒を排除するために「踏み絵」が使われたが、皮肉にも日本にキリスト教を伝えた本家では異教徒を殺すために「尋問」が行われていたのだ。
この近くには、壁も柱も全て人骨で出来た教会堂Chapel of Bones(Capela
dos Ossos)もある。何しろ5000体もの空ろな頭蓋骨が、無数の手足の人骨を積み重ねた壁や柱の中から我々を見つめる。ご丁寧に、入口には「私たち人骨は、あなた方の 骨と一緒になれるのをここで心待ちにしております」と書かれている。エヴォラ中の教会の墓場からこれだけ多数の人骨を集めたそうだが、こうなると墓場の不気味さを通り越して壮観でさえある。「From dust we come, to dust we return(我々は塵から生まれ塵に帰る<Hamlet>)ですね」とガイドに言ってみると、「それこそ、この教会が言いたかったことですよ」と同意した。実際1600年代初頭にはエヴォラの人々は物質的に繁栄していて、富だけに関心があった。そのとき社会の行く末を案じた3人の牧師が、死という現実を突きつけて、物質的繁栄のはかなさを人々に気づかせるために考え出したことだという。しかしこのやり方
骨と一緒になれるのをここで心待ちにしております」と書かれている。エヴォラ中の教会の墓場からこれだけ多数の人骨を集めたそうだが、こうなると墓場の不気味さを通り越して壮観でさえある。「From dust we come, to dust we return(我々は塵から生まれ塵に帰る<Hamlet>)ですね」とガイドに言ってみると、「それこそ、この教会が言いたかったことですよ」と同意した。実際1600年代初頭にはエヴォラの人々は物質的に繁栄していて、富だけに関心があった。そのとき社会の行く末を案じた3人の牧師が、死という現実を突きつけて、物質的繁栄のはかなさを人々に気づかせるために考え出したことだという。しかしこのやり方 を、「お金がすべての日本」に持ってきても焼け石に水かもしれないと思った。
を、「お金がすべての日本」に持ってきても焼け石に水かもしれないと思った。
ポルトガルはカトリック系であるせいか、聖母マリア信仰が目に付く。確かに私のような門外漢から見れば、十字架に釘ではり付けにされたキリストより、キリストを生む前のマリア像の方が包容力に満ちているように見える。ここの大聖堂も聖マリア教会(Santa Maria de Evora)と呼ばれる。回廊の隅にもキリストを身ごもって妊娠したマリア像が2箇所にあり、堂内にも金箔のかけられたお腹の大きいマリア像が祭壇に祭られている。こんな姿のマリア像はめずらしく、私は他の国では見たことがない。この付近の異教徒の間に、もともと女神信仰が強く、彼らを改宗させやすいので妊娠したマリアを使ったという見方もあるが…。
エヴォラからリスボン経由で西海岸の町ナザレに向かう。リスボンからは2階建ての路線バス。カメラを使うのに便利なので、2階の1番前の席を取った。やがて隣に中年の女性が座り、何となく話が始まった。リスボン大学で言語学を教えているフレイタスという教授だ。彼女の英語が上手なので、話が弾み、ビデオなどを撮るのも忘れてしまった。大学の国際会議のお膳立ても彼女の仕事で、よく旅行するという。早速、英語にポルトガル語を混ぜて作っていた私の旅程表を見てもらった。Rickの作ったコースだったが、「私が回るとしてもこんなコースをとるだろうね」と言った。私のプランにDouro河沿いのReguaがあるのに気づいて、「時間があったら更にDouro河上流、スペインとの国境近くのMiranda do Douroが歴史的にも観光的にも面白いところですよ」と推薦してくれた。
王家と民衆の良い関係がポルトガルの世界制覇の基になったことを彼女が話してくれたことは前に書いたが、パルプの原料を取るためにオーストラリアから持ち込まれたユーカリの木が、生長が早く強くて、当地に自生している松を圧迫していること。温暖化で昨年は水不足になり、制限給水までしなければならなかったこと。若者が都会に出てしまい農業 が衰退して土地の劣化がすすんでいること。また若者の生活が変化して世代間格差が生まれて問題になっていること…などを熱心に語ってくれて、日本の問題とだぶり、これらは大きな世界の流れなのかとも思った。
が衰退して土地の劣化がすすんでいること。また若者の生活が変化して世代間格差が生まれて問題になっていること…などを熱心に語ってくれて、日本の問題とだぶり、これらは大きな世界の流れなのかとも思った。
パン、カステラなどのポルトガル語が日本語に入ったいきさつなどを話すと興味を示した。さすが言語学の専門らしく、ブラジル・ポルトガル語が母音を保持しているのに、本家のポルトガル語は母音が落ちて子音が連続するなどの変化が出てきたことなどを丁寧に説明してくれた。まるで大学の講義をタダで聞いているのかと思うくらいだった。彼女はナザレの1つ手前で降りた。
ナザレは弓なりになった砂浜が続く美しい海岸の町。すぐ近くにそそり立つ 断崖の上の町Sitioにケーブルカー(ascensor)で登って町を見下ろすと、まさに絶景。しかしその驚くべき壮大なパノラマから少し目をそらして崖のすぐ横を見ると、列を成した洗濯物が風にはためいている。リゾートになっても昔の漁村の生活があちこちに残っているのだ。頭から膝まで黒いマントやショールに身を包んだ女性をよく見かける。女性は寡婦になると真っ黒に身を包んで余生をすごすという伝統を守っているという。一方、冬に港で北風にさらされながら海岸で漁師の夫を待つ妻は、7重のスカートをはいて暖を取ることを覚えた。それが名物になり、あちこちでカラフルな何層ものスカートを開いて観光客に見せているオバサンが目に付く。裏道の路上に七輪を置いて、いわしの塩焼きをする煙がたちこめる。レ
断崖の上の町Sitioにケーブルカー(ascensor)で登って町を見下ろすと、まさに絶景。しかしその驚くべき壮大なパノラマから少し目をそらして崖のすぐ横を見ると、列を成した洗濯物が風にはためいている。リゾートになっても昔の漁村の生活があちこちに残っているのだ。頭から膝まで黒いマントやショールに身を包んだ女性をよく見かける。女性は寡婦になると真っ黒に身を包んで余生をすごすという伝統を守っているという。一方、冬に港で北風にさらされながら海岸で漁師の夫を待つ妻は、7重のスカートをはいて暖を取ることを覚えた。それが名物になり、あちこちでカラフルな何層ものスカートを開いて観光客に見せているオバサンが目に付く。裏道の路上に七輪を置いて、いわしの塩焼きをする煙がたちこめる。レ ストランに入って注文すると大きなイワシが5匹ものった皿が出てきた。白壁を背景に緑で縁取りされた戸口で椅子に座った老婆が編み物をしている。絵になりそうな光景。若者が夕日を見ながら岩の上でたむろしている。ケーブルカーの乗り場を聞くと、皆がいっせいに笑顔で反応する。ここでは私は外人なのだ。夕日が白壁や砂浜を赤く染める。打ち寄せる白波は夕日を受けてしぶきがピンク色に変わる。実に美しくて面白いところだ。
ストランに入って注文すると大きなイワシが5匹ものった皿が出てきた。白壁を背景に緑で縁取りされた戸口で椅子に座った老婆が編み物をしている。絵になりそうな光景。若者が夕日を見ながら岩の上でたむろしている。ケーブルカーの乗り場を聞くと、皆がいっせいに笑顔で反応する。ここでは私は外人なのだ。夕日が白壁や砂浜を赤く染める。打ち寄せる白波は夕日を受けてしぶきがピンク色に変わる。実に美しくて面白いところだ。
断崖の上の小さな町Sitioの広場に小さな教会がある。入ってみて驚いた。正面一番奥、金箔で装飾された神聖な祭壇の近く、説教台のあるマリア像のすぐ前の壇上に2人の人影が見えた。牧師かな? いや観光客だ。田舎の教会は開放的で誰がどこに入ろうと気にしないが、こんなところにまで…と思った。しかし私も好奇心から入ってみた。正面脇の入口から正面背後に通じる通路がある。その脇には青いタイルが一面に貼られ、聖画が描かれた小さな部屋が続く。気がついたら正面の祭壇の高いところに立っていた。牧師になったように、会堂を見渡す。正面の2階にパイプオルガンが見える。明るい光線がステンドグラスから射し込む。それにしても見知らぬ訪問者に対して恐ろしく寛大なマリア様だが、有名な人助けの逸話も流れ、人々の信仰を集めているようだ。

ナザレからバスで1時間くらい南へ行ったところにオビドス(Obidos)という小さなかわいい町がある。緑豊かな平野の一画に、城壁に囲まれて白壁の家が密集している一画があり、細い石畳の道で区切られた歴史ある所に800人が住んでいる。入口近くから城壁に上ると町全体が見渡せて、小さな「城下町」の全体像が良く分かる。中央に広場と教会があり、それを囲むように茶色の瓦屋根と白壁の家が密集している。そして城壁の反対側にはお城があり、今はポウサダ(宿舎)になっている「天守閣」(?)がそびえる。町中を歩くと、黄色と青の窓枠の上にブーゲンビリアやゼラニウムが白壁を覆い、その間を細い凸凹の石畳が続く。白壁にカラフルなお皿をたくさん吊るした店。タイル画をぶら下げた窓の下には陶器の人形が並んでいる。私の下手な腕でも絵葉書のような写真が撮れそうだ。しかしメインストリートから少し脇に入ると、窓からは洗濯物が窓から垂れ下がり、車がやっと1台通れるくらいの巾の石畳の道をすごいスピードで車が通過する。

ここも紀元前3世紀ころケルト人が築き、ローマ人、ムーア人が住んだあと1282年に当時のディニス王が支配する。ところが、王妃がこの町をすっかり気に入ったというので、王は町全体を王妃へのプレゼントにしてしまう。そのあと600年間、引き継いだ全ての王が、この町を王妃への贈り物にするという「伝統」を守ったとか。
城壁に上る階段は段差が大きく、かなりの数だった。途中で休んでいたら、英語で話しかけてきた婦人がいた。聞くとイギリス人でこの町が気に入って数年前から住み着いているという。「今日は来週からのチョコレート祭りで準備が大変」と城壁にバナーを取り付ける作業に飛び回っている。それで表通りの頭上にネスカフェのNestle社の花綱飾り(festoon)があったのか…と気がついた。人が住む町を見せて入場料をとるのも変なので、企業と提携(?)して町を引き立てようというのか、「秋祭り」の準備が進んでいた。<次ページへ>