|

世の中「英会話」ブームだ。しかし中身のある英会話がどのくらい行われているのだろうか。ここには2時間近くも続くすばら しい「英会話」のお手本がある。人間と人生に深い関心のある脚本家とディレクターという2人は、ユーモア、皮肉、驚き、深みのある内容を、リズムのある心地よい英語で表現する。「死刑台のエレベーター」の巨匠ルイ・マル監督が1981年に作ったちょっと変わった映画である。ほとんど男2人の会話だけという形と、内容がやや難解ということからか、 しい「英会話」のお手本がある。人間と人生に深い関心のある脚本家とディレクターという2人は、ユーモア、皮肉、驚き、深みのある内容を、リズムのある心地よい英語で表現する。「死刑台のエレベーター」の巨匠ルイ・マル監督が1981年に作ったちょっと変わった映画である。ほとんど男2人の会話だけという形と、内容がやや難解ということからか、 日本では普通の映画館はもちろん、テレビやアート・シアターでさえ、公開されたことがない。でも、作られた年には、世界では、その年のべスト10に入る映画とも言われた作品で、海外のインターネット上では今でも議論がある。残念ながら日本語字幕の入った映画やビデオは存在しない。でも、インターネット上のアマゾン・コムなどのネット上の書店では世界のビデオやスクリプトを販売していて、英語版では求めることができるようになった。 日本では普通の映画館はもちろん、テレビやアート・シアターでさえ、公開されたことがない。でも、作られた年には、世界では、その年のべスト10に入る映画とも言われた作品で、海外のインターネット上では今でも議論がある。残念ながら日本語字幕の入った映画やビデオは存在しない。でも、インターネット上のアマゾン・コムなどのネット上の書店では世界のビデオやスクリプトを販売していて、英語版では求めることができるようになった。
 登場人物2人の立場の違いをはっきりと示す「電気毛布」の議論の場面から紹介させていただこう。この映画の主人公の一人、貧しいウォリーは、クリスマスに「電気毛布」を贈られて、生活が全く変ったと喜ぶ。眠りも違うし、見る夢まで違ってきた。起きた時の感じも違う。以前とはまるで別世界に生きているようだと感嘆する。一方、会話の相手のアンドレは、電気毛布に包まれて感電死するのはごめんだよ、とトボケたあとで、「電気毛布の快適さが曲者で、現実感覚を失うことになる危険がある」と反論する。 登場人物2人の立場の違いをはっきりと示す「電気毛布」の議論の場面から紹介させていただこう。この映画の主人公の一人、貧しいウォリーは、クリスマスに「電気毛布」を贈られて、生活が全く変ったと喜ぶ。眠りも違うし、見る夢まで違ってきた。起きた時の感じも違う。以前とはまるで別世界に生きているようだと感嘆する。一方、会話の相手のアンドレは、電気毛布に包まれて感電死するのはごめんだよ、とトボケたあとで、「電気毛布の快適さが曲者で、現実感覚を失うことになる危険がある」と反論する。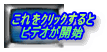
「もし電気毛布がなかったら、もう1枚毛布を探すとか、コートを探してきて何枚もかけるとかして、寒いという感じを忘れないでいることができる。隣の人が寒いんじゃなかろうか…という同情心、世界で寒さに震える人に対する思いやりの気持も出てくる。また『寒さって良いなあ。寄り添って暖めあうこともできる!』なんていう場面だってあるだろう」と想像する。更に
「電気毛布は、外の刺激を受けないために精神安定剤を使うのと同じで、それを喜ぶのは、テレビ中毒と同じ脳神経の退化現象に似ている。つまり、我々だって動物なんだから、太陽、月、季節などを切り離した架空の世界に生きれば、人間性に深刻な影響を受けるのは当然だよ」と言う。それに対して、
「ニューヨークは寒いんだ。アパートも冬は寒い。生活も厳しい。このつつましい安らぎを俺は絶対手放さないぞ! このピリピリすることばかりの世の中で、もっと安らぎが欲しいくらいだよ」とウォリーは感情を込めるが、

「いいか、その快さが危険なんだよ。快適さを求めるのは自然なことだが、快さにだまされて、自分が落ち込んでいく危険に気がつかないんだよ。昔Hatfield婦人という大金持ちがいたんだがね、何と餓死してしまったんだよ。彼女は鶏しか食べなかった。鶏が大好物で、鶏を食べているときだけが幸せだった。知らず知らずのうちに、身体が弱り、遂には死んだ。でも、我々は今皆、このHatfieldなんだよ。快適な電気毛布に包まれて、食いたい物しか食わない。現実世界との接触がない生活では、真に命に必要なものを取り入れることはできないんだよ」とアンドレは反論し、話は進んでいく。
2人は正確には、共にニューヨークに住む Wallace Shawn(脚本家)と Andre Gregory(ディレクター)で、以前ウォリー(Wallaceの愛称)の作品をアンドレが上演したことがあって、二人は友人になった。ウォリーは、有名な雑誌New Yorkerの編集長だった父を持ち、若い頃は裕福な家庭に育った。だが36才の今、金銭感覚はなく、芸術以外には興味を持てず、あまり売れない脚本を書いては、苦しい生活に耐えていた。一方、10才年上のアンドレは、成功した演出家だったが、非常にデリケートな心の持ち主である。人々が実生活で、演劇以上にうまく「演技」しているのを見て、舞台での演技は余計な事に思え、自分がやっていることに嫌気がさして行き詰まってしまう。だから演劇界から降りて、新しい演劇の可能性や人生の本質を模索するために世界を放浪した。彼の行動範囲は、ポーランド、イスラエル、チベット、インド、サハラ砂漠、スコットランドのフィンドホーン共同体などに及んだ。
 日本の演劇界にも影響を与えたポーランドの演出家グロトフスキの依頼を受けて、ポーランドの森の古城跡で徹夜の合宿を繰り返した様子が映画の初めの方に詳しく出てくる。全く英語の分からない40人の演劇愛好者を対象にしながら、「心の言語」で不思議にも彼の気持は伝わる。独特の「自然の舞台装置」の中では、ちょっとした刺激や状況が与えられると、全く自然発生的に、考えられないような美しい歌が生まれ、楽器が演奏される。それが爆発的に神秘的な踊りに変わり、素朴な光や音、人間の本性から生まれた動きの祭典が演出できて、彼自身も本当の創造の喜びを経験する。 日本の演劇界にも影響を与えたポーランドの演出家グロトフスキの依頼を受けて、ポーランドの森の古城跡で徹夜の合宿を繰り返した様子が映画の初めの方に詳しく出てくる。全く英語の分からない40人の演劇愛好者を対象にしながら、「心の言語」で不思議にも彼の気持は伝わる。独特の「自然の舞台装置」の中では、ちょっとした刺激や状況が与えられると、全く自然発生的に、考えられないような美しい歌が生まれ、楽器が演奏される。それが爆発的に神秘的な踊りに変わり、素朴な光や音、人間の本性から生まれた動きの祭典が演出できて、彼自身も本当の創造の喜びを経験する。
ウォリーが現実の中に小さな幸せを求め、自然科学を尊重するのに対して、アンドレは自然科学を超えたものに興味を持ち、その一見「異常な」状況に身をおいて、普通の日常からでは見えないものを感じ取ろうとする。例えば、ある時期、彼は大きな旗に異常なほどの興味を持った。どこで仕事をしても、そばには大きな旗を立てる。仲間と旅に出ても、広げてその上で談笑する。夜は旗に包まって寝る。そうしているうちに旗は、その時々の生活の鼓動を受信して、それを保存する力があると彼は考える。そのうち偶然優れた旗職人に出会い、インドの旅に持参するために自分専用の旗を作ってもらう。出来てき た物を見ると、意に反してケバケバしいデザインで真ん中にヒットラーのカギ十字を思い出させる大きな卍がある。インドへの旅に、家族からの気持を旗に入れ込んでもらおうとして、娘に、一晩この旗を敷いて寝てくれと頼むが、娘は絶対イヤだと言う。いよいよお別れパーティの最中、奥さんが旗のことを思い出し皆に紹介しようとしたら、突然真っ青になり嘔吐して、パーティもお開きになる。本人もこの旗には嫌気がさして、何も言わずに女性の知人にプレゼントするが、彼女も不吉な旗の影響を本能的に感じ取り、儀式をしてそれを燃やしてしまう。 た物を見ると、意に反してケバケバしいデザインで真ん中にヒットラーのカギ十字を思い出させる大きな卍がある。インドへの旅に、家族からの気持を旗に入れ込んでもらおうとして、娘に、一晩この旗を敷いて寝てくれと頼むが、娘は絶対イヤだと言う。いよいよお別れパーティの最中、奥さんが旗のことを思い出し皆に紹介しようとしたら、突然真っ青になり嘔吐して、パーティもお開きになる。本人もこの旗には嫌気がさして、何も言わずに女性の知人にプレゼントするが、彼女も不吉な旗の影響を本能的に感じ取り、儀式をしてそれを燃やしてしまう。
スコットランドの東海岸にフィンドホーンという場所がある。その辺りの土壌は海岸の砂地なのに、世界最大のカリフラワーを育てたり、英国では絶対育たないと言われた樹木を育てるのに成功したという。面白いのは植物や昆虫などと気持が通じ合え ることらしい。例えば、昆虫が野菜を食い荒らすときは、昆虫と話をして、昆虫が食べてもいい畑を一部に作ってやると、人間用のところには昆虫は手をつけないと言う。共同体の人たちは全ての事物には神が宿っていると考えて、我々が機械的にすることでも、異常なほど気持を込めて振る舞う。冷蔵庫、ストーブ、車など全ての物には人間と同じ名前が付けられていて、人間と同じ様に大切に扱われるという。彼はフィンドホーンの森に入ってみる。樹木の葉、1枚1枚の中に生きている物が見える。全速力で走ってみると、周りから生命力が取り込まれて、気持がひどく高揚するのが実感され、森を出ても、その気持が持続するという。実際、この共同体には今でも日本を含めて、世界から毎年多くの人が体験に訪れている。 ることらしい。例えば、昆虫が野菜を食い荒らすときは、昆虫と話をして、昆虫が食べてもいい畑を一部に作ってやると、人間用のところには昆虫は手をつけないと言う。共同体の人たちは全ての事物には神が宿っていると考えて、我々が機械的にすることでも、異常なほど気持を込めて振る舞う。冷蔵庫、ストーブ、車など全ての物には人間と同じ名前が付けられていて、人間と同じ様に大切に扱われるという。彼はフィンドホーンの森に入ってみる。樹木の葉、1枚1枚の中に生きている物が見える。全速力で走ってみると、周りから生命力が取り込まれて、気持がひどく高揚するのが実感され、森を出ても、その気持が持続するという。実際、この共同体には今でも日本を含めて、世界から毎年多くの人が体験に訪れている。
また、ニューヨーク州、ロングアイランドのモントークという荒野での変わった体験も語られる。ちょうど初冬の万聖節(ハロウィーン)のころで、日本のお盆と同じで、先祖の霊が戻ってくると信じられている時期だ。9人ほどの合宿で、そのうちの3人が、彼を含む他の人たちに仕掛けた体験だった。
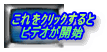 「我々は月のないハロウィーンの真夜中、荒野の断崖の上に呼び出された。寒かったが待っていると、3人が白いシーツを頭からかぶったような姿で現れた。気味が悪かった。やがて、焼け落ちた建物の地下室に連れて行かれた。そこにはテーブルとベンチがあって、紙、鉛筆、ワインとグラスが置いてあって、遺書を書くように言われたんだ。…それから一人ずつ目隠しをされて、寒くて暗い荒野の中を走らされて、別の物置の地下室に連れて行かれた。そこで、貴重品を渡して、全身、裸になるように言われた。その 「我々は月のないハロウィーンの真夜中、荒野の断崖の上に呼び出された。寒かったが待っていると、3人が白いシーツを頭からかぶったような姿で現れた。気味が悪かった。やがて、焼け落ちた建物の地下室に連れて行かれた。そこにはテーブルとベンチがあって、紙、鉛筆、ワインとグラスが置いてあって、遺書を書くように言われたんだ。…それから一人ずつ目隠しをされて、寒くて暗い荒野の中を走らされて、別の物置の地下室に連れて行かれた。そこで、貴重品を渡して、全身、裸になるように言われた。その まま、テーブルに寝かされ、全身をきれいに拭かれた。ナチの強制収容所と秘密警察が一瞬頭をかすめた。やがて立たされて、裸のまま写真を撮られ、裸のまま目隠しをされてまた荒野を走らされて、テントの中のような場所に投げ出された。そこは寒かったけど、同じ様な裸の人間がゴロゴロしていたので、身を寄せ合って何とか寒さをしのいだ。待っていると、また目隠しをされて、担架のようなものに乗せられて、森を突っ走り、下ろされた場所は2メートルも掘られた墓穴だった。ほどなく、身体の上に木切れが置かれ、手に貴重品が握らされ、顔に白い布がかけられたと思ったら、土をかけられ始めた。生き埋めとは、まさにこういう気持なんだと思い知らされた」と彼は語る。かなり時間がたって、彼らは「救い出され」、目隠しをとかれて、大きな焚き火の周りでワインと音楽に踊り狂って夜を明かした。 まま、テーブルに寝かされ、全身をきれいに拭かれた。ナチの強制収容所と秘密警察が一瞬頭をかすめた。やがて立たされて、裸のまま写真を撮られ、裸のまま目隠しをされてまた荒野を走らされて、テントの中のような場所に投げ出された。そこは寒かったけど、同じ様な裸の人間がゴロゴロしていたので、身を寄せ合って何とか寒さをしのいだ。待っていると、また目隠しをされて、担架のようなものに乗せられて、森を突っ走り、下ろされた場所は2メートルも掘られた墓穴だった。ほどなく、身体の上に木切れが置かれ、手に貴重品が握らされ、顔に白い布がかけられたと思ったら、土をかけられ始めた。生き埋めとは、まさにこういう気持なんだと思い知らされた」と彼は語る。かなり時間がたって、彼らは「救い出され」、目隠しをとかれて、大きな焚き火の周りでワインと音楽に踊り狂って夜を明かした。
もちろんこの「葬儀」は芝居である。でも、彼は演劇にはこういう新鮮な現実感が必要だというのである。彼が若いころ、ギリシャ演劇を演出していて、主人公が惨殺され首をはねられる場面を実感させるのに、死体安置所から生首を持ってきて、観客の間に回したらどうかと、演技者に提案して、ひどい拒絶反応にあったようだが、彼の真意は演技者にその場面の現実感を持たせることにあったようだ。現代の演劇界のように、醜悪な世の中をそのまま舞台で再現してみても、観客が絶望感に苦しむのを手助けするだけだと言う。
ある時、アンドレは「高山」(こうざん)という日本人の僧侶に出会う。彼の雰囲気が「真夏の夜の夢」に出てくる妖精に似ていて、笑顔がなんとも言えないというので、高山は、当時アンドレが関心のあった「星の王子」の王子役にぴったりだということになった。そこで、アンドレは高山とサハラ砂漠に出かけて「星の王子」を撮ることになる。しかし、当時アンドレの精神状態は不安定で、よく頭に幻覚が走ったりしていた。ラクダに乗って、毎日進んでみても、なかなか雑念が消えず、ニューヨークにいるときと同じことを考えている。座禅のようなことを繰り返してみるが効果はない。棕櫚の葉が風に揺れて擦れる音が聞こえる暗い夜、オアシスの向うの方の砂丘から、高山の低い美しい歌声が響いてくる。暗い中を歌声の方に砂の上を辿っていく。彼らは自分の求めているものが何だか分からなくなっていた。どうしようもなくなって、真剣に砂漠の砂を食べ始める。もちろん吐き出してしまうが、それほど気持が行き詰っていたんだと彼は言う。
「自分が今までやってきたことは何だったんだろうか? 大したことはない人間なのに俺は何様のつもりだったのだろう? イランの国王にでもなったつもりだったのか? 俺はヒットラーお抱えの建築家アルバート・スピアのようだ。彼は自分が特別の人間で、普通の人間の基準は当てはまらないと言って、自分勝手をやって、逮捕され裁判にかけられた。俺もそろそろ捕らえられて監獄送りになるころだ!」という自己嫌悪も彼に付きまとう。
2人はすべて意見を異にしているようだが、次の点では意気投合する。彼らは言う。忙しく動き回っていても心は死んでいる人は実に多いと。生活全体を「自動操縦」に切り替えて、考えることもやめて、感じる感覚も必要なくなり、ロボットの生活に入る。そうなると「習慣」で生きることになり、実際に「生きている」とは言えなくなる。食べる物の味も感じることができなくな り、ただ口に詰め込むだけ。感情を表すことも出来ず、人との真の交流も出来なくなる。一人一人が疎外感を持って、孤立して生きることになる。目が付いていても、本当に見ていることはない。人が悲しみに沈んでいるのに、肌の色が褐色をしていることだけを見て、「元気そうだね!」と声をかける。友人の親が死んだことを知っていながら、同情心も持てないで、当人に冗談ばかり言って平気でいる。腕の傷を直す専門医は腕以外に目が行かず、患者が死にかかっていても、腕が少し良くなれば、笑顔で患者の肉親に自分の「腕」を自慢する。 り、ただ口に詰め込むだけ。感情を表すことも出来ず、人との真の交流も出来なくなる。一人一人が疎外感を持って、孤立して生きることになる。目が付いていても、本当に見ていることはない。人が悲しみに沈んでいるのに、肌の色が褐色をしていることだけを見て、「元気そうだね!」と声をかける。友人の親が死んだことを知っていながら、同情心も持てないで、当人に冗談ばかり言って平気でいる。腕の傷を直す専門医は腕以外に目が行かず、患者が死にかかっていても、腕が少し良くなれば、笑顔で患者の肉親に自分の「腕」を自慢する。
人々に「見る目」がないとすれば、外見だけでことはすんでしまう。だから、医者はいかに力がなくても、医者らしい格好をすることに気を使う。テロリストも必ずテロリストらしいスタイルでテレビの画面に現れる。芸術家も父親も、人の頭にあるそれらしいイメージに合わせるように身を整える。そしてそのイメージに合うように「役割」を演じることに一生懸命になる。しかし、自分の内面の生活では、どう生きていいかよく分からない。役割を演じるだけの架空の世界では、本当の経験はないし、物事を実感としてとらえる心のモードに切り替わらない。
習慣だけで生きていて、1瞬1瞬を新しい気持で生きることのない生活はやがて倦怠感をもたらす。生きることが退屈になり、無気力になって行く。しかし、この無気力を蔓延させるもとに何があるのだろうか? それは、大きな力を持って世界を圧倒する、金銭中心の全体主義政治体制の洗脳力だとアンドレは言う。しかし、これは非常に危険なことで、生き延びられない人が出てくるかもしれないという問題だけではない。無気力な人間は眠っているのと同じだ。眠っていれば決して「ノー」とは言わないので、全体主義政体にとってこんな好都合なことはないのだとも言う。皆がロボットになって、魂のない死体のような人間がウヨウヨと町を歩きまわるだけの時代が来るかもしれない。でも、その野蛮で無法な恐ろしい時代はやがて訪れるとスウェーデンの物理学者ビヨンストランドは予言する。彼自身、テレビ、新聞、雑誌などは一切見ない生活だ。ジョージ・オーウェルが「1984年」などで描く、全体主義国家の脅威を感じるからで、メディアはすべて人間をロボットに変えていると信じているのだ。
実際、ニューヨークは、死体置き場のような町になりつつあるという。ロボットのような人間だけが住む町。食べ物も、画一的なロボットが食べるような餌で、人に語りかけても、人間のような反応は返ってこない。アンドレがイギリスの樹木の専門家と話したときの言葉がおもしろい―

「ニューヨークの人は『こんな町は早く出たい』と言う人が多いのに、決して出ない。それは、その町が今までにないタイプの強制収容所になっているからだ。そこに収容されている囚人が自ら建設し、守衛まで引き受けている変な監獄だ。しかも自分で作ったこの監獄を誇りにして威張るのに、自分では精神分裂病にかかっている。その結果、ロボトミー手術で精神的に去勢されて脱走する元気もなく、監獄を監獄と見る能力まで失っている」というのだ。しかし、この「ニューヨーク」という言葉を「東京」と入れ替えてみると、似たような現象があることに気付く。
やがて、ロボットだけがはびこる時代になると、かつては、感情も知能もある「人間」という生物がこの世に存在したことさえ完全に忘れられてしまう時代が来るかもしれない。実際、ロボットの時代には、人間の歴史や記憶は意識的に消されていく。ビヨンストランドをはじめ、「人間」が絶滅する危険を感じる人たちは、「人間保護区」を真剣に考え始めている。トキの絶滅を心配する場合の処置と同じ考えだ。中世の暗黒時代に地下組織を作って教会の不当な弾圧を免れたのにも似ている。「人間保護区」は、人間がロボットになってしまった世の中で、細々と人間が人間として機能し続ける唯一の場である。 また人間の本当の歴史・文化・輝きが、この人間受難の時代を生き延びて保存され、新しい時代に再現されることを目的とする。そして、この保護区で、生き延びるには新しい「言語」が必要だとアンドレは言う。「言語」と言っても「心の言語」で、詩の言語、ポーランドの森で英語が分からない人たちと通じ合ったときの言葉でない言葉、ミツバチが蜜の場所を知らせるときにするダンスのような言語だ。そして、その言語を習得するには、「鏡の国のアリス」で「鏡の向こうに見える世界」に飛び込むような気持の切り替えが必要で、そうすれば、万物とのつながりが見えてきて、この世の全てが分かるようになるとアンドレが締めくくる。 また人間の本当の歴史・文化・輝きが、この人間受難の時代を生き延びて保存され、新しい時代に再現されることを目的とする。そして、この保護区で、生き延びるには新しい「言語」が必要だとアンドレは言う。「言語」と言っても「心の言語」で、詩の言語、ポーランドの森で英語が分からない人たちと通じ合ったときの言葉でない言葉、ミツバチが蜜の場所を知らせるときにするダンスのような言語だ。そして、その言語を習得するには、「鏡の国のアリス」で「鏡の向こうに見える世界」に飛び込むような気持の切り替えが必要で、そうすれば、万物とのつながりが見えてきて、この世の全てが分かるようになるとアンドレが締めくくる。
そこで、ウォリーの出番だ。
極めて「現実的」な反応だと自分でことわってから、自分は、抽象的な生きがいより、目の前の現実を生き抜くのが大変なんだという。彼女と仲良く暮らし、チャールトン・へストンの自伝を読むのが最高に楽しいし、それだけでいいんだ。時にはパーティにでも出かけたり、無い知恵を絞って劇が書けたりすれば言うはことないのだという。
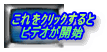 「朝、目を覚ましたら、冷えたコーヒーが枕元で私が飲むように一晩そこで待っていてくれたのが分かる。ゴキブリも蝿も死んで浮いてないのを見るとゾクゾクするほどうれしい。もちろんゴキブリが浮いていたら、悲しい気持になるが、こんな些細なことで充分ではないのか。わざわざ地球の果てまで、人生の真実を追究しに行かなくても、身近な小さな幸せで、どうしていけないんだ? 1杯のうまいコーヒーとコーヒーケーキ以上のものが何故必要なんだ? 君にもすばらしい奥さんがいる。子供達もいる。新聞も配達されると、ゆっくり読むことだって出来る。それだけで充分じゃないか? つまらぬ目的意識を捨てて、純粋な生き方を追求せよと言っても、人間は元来、目的を追求して動き回るように作られている。目的意識を取り除けというのは、木に、枝や根っこを切って生きろというのと同じで、無理な事だよ。木から枝や根を切り落としたら、木ではなくなり、丸太になってしまうだろう?」と切り込む。しかし 「朝、目を覚ましたら、冷えたコーヒーが枕元で私が飲むように一晩そこで待っていてくれたのが分かる。ゴキブリも蝿も死んで浮いてないのを見るとゾクゾクするほどうれしい。もちろんゴキブリが浮いていたら、悲しい気持になるが、こんな些細なことで充分ではないのか。わざわざ地球の果てまで、人生の真実を追究しに行かなくても、身近な小さな幸せで、どうしていけないんだ? 1杯のうまいコーヒーとコーヒーケーキ以上のものが何故必要なんだ? 君にもすばらしい奥さんがいる。子供達もいる。新聞も配達されると、ゆっくり読むことだって出来る。それだけで充分じゃないか? つまらぬ目的意識を捨てて、純粋な生き方を追求せよと言っても、人間は元来、目的を追求して動き回るように作られている。目的意識を取り除けというのは、木に、枝や根っこを切って生きろというのと同じで、無理な事だよ。木から枝や根を切り落としたら、木ではなくなり、丸太になってしまうだろう?」と切り込む。しかし
「忙しく動き回っていても、心は死んでいることが多いのは事実だよ。本当に気持が進んで行動しているか考えてみろ。もし機械的な生き方をしているのなら、生き方を考え直す必要があると思うよ。若いときは、やれデートだ、やれダンスだと動き回り、ある関係が出来ると、突然人生は固まってしまう。仕事だって同じ事だ。でも、心の中が生き生きしていれば、たとえ小さな部屋に居ても、一緒に暮らしている人との間に生気が流れ、その小さな部屋でいつも大冒険が起きる。でも、常に心が凍りつく危険はある。そんなときは全ての雑音を遮断して、しばらく「演技」をして暮らすことをやめてみて、心の声に耳を傾けるのだ。そのためにはサハラやエベレストに行かなきゃダメなこともあるが、自分の家でも充分できる」とアンドレ。
「でも、その静かな時間というのが、どうも苦手なんだ。静かにしていて自分の内面が見えてくるのは怖いし、人と面と向かうのも怖いんだよ。君には奇妙に見えるかもしれないがね…」
「いや、怖いと思うのは当然だよ。人間は危険でわけのわからない生き物だからね。人間って、深く知れば深く知るだけ、ますます分からなくなるものなんだよ。人間がそんな不安定な存在だから、皆何か安定したものを求める。つまり父、母、夫、妻などの作られたイメージにしがみつくんだ。そしてその役割を「演技」する。情事に走るのもひと時の安定が欲しいんだよ。しかし、それらは実体のないものだ。人間と付き合うのはお化けと付き合うようなものさ。我々自身が幻なのだから。」
うまくまとまりませんが、皆さんは2人の考えをどう思われますか?


|

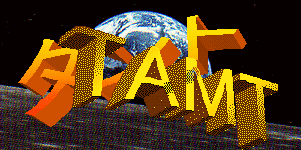

 しい「英会話」のお手本がある。人間と人生に深い関心のある脚本家とディレクターという
しい「英会話」のお手本がある。人間と人生に深い関心のある脚本家とディレクターという 日本では普通の映画館はもちろん、テレビやアート・シアターでさえ、公開されたことがない。でも、作られた年には、世界では、その年のべスト
日本では普通の映画館はもちろん、テレビやアート・シアターでさえ、公開されたことがない。でも、作られた年には、世界では、その年のべスト
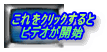


 た物を見ると、意に反してケバケバしいデザインで真ん中にヒットラーのカギ十字を思い出させる大きな卍がある。インドへの旅に、家族からの気持を旗に入れ込んでもらおうとして、娘に、一晩この旗を敷いて寝てくれと頼むが、娘は絶対イヤだと言う。いよいよお別れパーティの最中、奥さんが旗のことを思い出し皆に紹介しようとしたら、突然真っ青になり嘔吐して、パーティもお開きになる。本人もこの旗には嫌気がさして、何も言わずに女性の知人にプレゼントするが、彼女も不吉な旗の影響を本能的に感じ取り、儀式をしてそれを燃やしてしまう。
た物を見ると、意に反してケバケバしいデザインで真ん中にヒットラーのカギ十字を思い出させる大きな卍がある。インドへの旅に、家族からの気持を旗に入れ込んでもらおうとして、娘に、一晩この旗を敷いて寝てくれと頼むが、娘は絶対イヤだと言う。いよいよお別れパーティの最中、奥さんが旗のことを思い出し皆に紹介しようとしたら、突然真っ青になり嘔吐して、パーティもお開きになる。本人もこの旗には嫌気がさして、何も言わずに女性の知人にプレゼントするが、彼女も不吉な旗の影響を本能的に感じ取り、儀式をしてそれを燃やしてしまう。 ることらしい。例えば、昆虫が野菜を食い荒らすときは、昆虫と話をして、昆虫が食べてもいい畑を一部に作ってやると、人間用のところには昆虫は手をつけないと言う。共同体の人たちは全ての事物には神が宿っていると考えて、我々が機械的にすることでも、異常なほど気持を込めて振る舞う。冷蔵庫、ストーブ、車など全ての物には人間と同じ名前が付けられていて、人間と同じ様に大切に扱われるという。彼はフィンドホーンの森に入ってみる。樹木の葉、
ることらしい。例えば、昆虫が野菜を食い荒らすときは、昆虫と話をして、昆虫が食べてもいい畑を一部に作ってやると、人間用のところには昆虫は手をつけないと言う。共同体の人たちは全ての事物には神が宿っていると考えて、我々が機械的にすることでも、異常なほど気持を込めて振る舞う。冷蔵庫、ストーブ、車など全ての物には人間と同じ名前が付けられていて、人間と同じ様に大切に扱われるという。彼はフィンドホーンの森に入ってみる。樹木の葉、 まま、テーブルに寝かされ、全身をきれいに拭かれた。ナチの強制収容所と秘密警察が一瞬頭をかすめた。やがて立たされて、裸のまま写真を撮られ、裸のまま目隠しをされてまた荒野を走らされて、テントの中のような場所に投げ出された。そこは寒かったけど、同じ様な裸の人間がゴロゴロしていたので、身を寄せ合って何とか寒さをしのいだ。待っていると、また目隠しをされて、担架のようなものに乗せられて、森を突っ走り、下ろされた場所は
まま、テーブルに寝かされ、全身をきれいに拭かれた。ナチの強制収容所と秘密警察が一瞬頭をかすめた。やがて立たされて、裸のまま写真を撮られ、裸のまま目隠しをされてまた荒野を走らされて、テントの中のような場所に投げ出された。そこは寒かったけど、同じ様な裸の人間がゴロゴロしていたので、身を寄せ合って何とか寒さをしのいだ。待っていると、また目隠しをされて、担架のようなものに乗せられて、森を突っ走り、下ろされた場所は り、ただ口に詰め込むだけ。感情を表すことも出来ず、人との真の交流も出来なくなる。一人一人が疎外感を持って、孤立して生きることになる。目が付いていても、本当に見ていることはない。人が悲しみに沈んでいるのに、肌の色が褐色をしていることだけを見て、「元気そうだね
り、ただ口に詰め込むだけ。感情を表すことも出来ず、人との真の交流も出来なくなる。一人一人が疎外感を持って、孤立して生きることになる。目が付いていても、本当に見ていることはない。人が悲しみに沈んでいるのに、肌の色が褐色をしていることだけを見て、「元気そうだね
 また人間の本当の歴史・文化・輝きが、この人間受難の時代を生き延びて保存され、新しい時代に再現されることを目的とする。そして、この保護区で、生き延びるには新しい「言語」が必要だとアンドレは言う。「言語」と言っても「心の言語」で、詩の言語、ポーランドの森で英語が分からない人たちと通じ合ったときの言葉でない言葉、ミツバチが蜜の場所を知らせるときにするダンスのような言語だ。そして、その言語を習得するには、「鏡の国のアリス」で「鏡の向こうに見える世界」に飛び込むような気持の切り替えが必要で、そうすれば、万物とのつながりが見えてきて、この世の全てが分かるようになるとアンドレが締めくくる。
また人間の本当の歴史・文化・輝きが、この人間受難の時代を生き延びて保存され、新しい時代に再現されることを目的とする。そして、この保護区で、生き延びるには新しい「言語」が必要だとアンドレは言う。「言語」と言っても「心の言語」で、詩の言語、ポーランドの森で英語が分からない人たちと通じ合ったときの言葉でない言葉、ミツバチが蜜の場所を知らせるときにするダンスのような言語だ。そして、その言語を習得するには、「鏡の国のアリス」で「鏡の向こうに見える世界」に飛び込むような気持の切り替えが必要で、そうすれば、万物とのつながりが見えてきて、この世の全てが分かるようになるとアンドレが締めくくる。
