 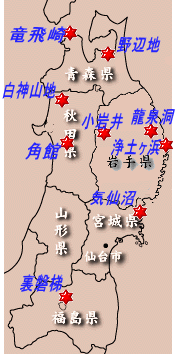
日本の東北地方に、ギリシャの海岸ではないかと錯覚させるような場所があるとは思わなかった。津軽半島の突端、竜飛崎への道はまさにそれだ。すみきった薄い青一色に広がる空の下、一面の紺碧の海がところどころに、やや明るい青の縞を走らせて迫ってくる。空と海の青が接するところでは、半島がカーブを描いて先の方に伸びているのであろうか、一部に薄黒い帯がボーッと突き出して見える。海岸近くの海から突き出している岩に向かって砕ける白い波。白い点線の中心線が海岸線に沿ってきれいに曲がっていく舗装道路 に沿って車は滑るように走っていく。道路の右側の緑におおわれた急な斜面のところどころに張り付いている白壁の家が後ろに飛んでいく。広く開いた海側の窓から入る海風が快く顔面をなぜる。 に沿って車は滑るように走っていく。道路の右側の緑におおわれた急な斜面のところどころに張り付いている白壁の家が後ろに飛んでいく。広く開いた海側の窓から入る海風が快く顔面をなぜる。
半世紀ほど前には、近くで生まれた太宰治がここを「本州の袋小路」と書いた。実際、昭和36年頃行かれた元同僚のN先生は、「全くの地の果てで、日本海側の道は山道同然、民宿の姉ちゃんからきつく行かないよう注意されましたっけ」とおっしゃっておられる。実際、展望台から見下ろすと、巨大な灰色の蛇が緑の中を這い上がってくるかのように、曲がりくねった道路が海辺から続いてくるのがみえる。ひと昔前、太宰はこの険しい辺境の地をさまよっているうちに、その厭世観の源が醸成されたのだろうか。ここの冬の寒さは並ではないだろう。あたりに林立する風車が、平均10メートルにもなるという冬の海風の強さを暗示する。見渡す限り、緑でおおわれている大地に、巨木がほとんど存在しないことも、冬の自然の厳しさを何となく示しているようだ。「津軽海峡の冬景色」というのは決してロマンティックなものではないだろう。
しかしたまたまこの日は、夏も終わりの快晴の1日だった。両脇に急斜面の山並みが連なる間を切り開くように進むところでは、両側の山が左右からせり出して、目の前にはV字型の風景が展開する。そんなときに、道が急な下りになり、そのV字型の視野に、突然真っ青な海の青が飛び込んでくる。まるで海にまっさかさまに飛び込んでしまうのではないかと錯覚するくらいだ。しかしそのときの何とも言えない爽快感。これもギリシャの海で味わった感動だった。
青い津軽海峡も、南の方角は午後の太陽をまともに受けて、海面全体が鏡のように強い光を反射して真っ白に輝く。 まるで富士山頂から太陽を反射する真珠色の雲海をのぞんでいる感じである。しかし目を少し横にずらすと、再び海は紺碧の広がりに戻る。すると、向こうに、灰色がかった青の塊が広がって迫ってくる。そのスカイラインは山々の鋭い稜線を見せてギザギザに空に食い込んでいる。それが北海道だ。この下には青函鉄道トンネルが通じている。そしてこの下150mにはその地下駅がある。分かった!
この辺の道路が、「袋小路」から「ギリシャ」に変ったのは、青函トンネルの建設機材を運ぶためだったのだ。しかし巨大な橋を作るのと違って、地上の自然や景観が破壊されることもなく、工事が終わってトラックが走らなくなった道路は、我々にそのすばらしい辺境にアクセスする便宜だけを残してくれたようだ。 まるで富士山頂から太陽を反射する真珠色の雲海をのぞんでいる感じである。しかし目を少し横にずらすと、再び海は紺碧の広がりに戻る。すると、向こうに、灰色がかった青の塊が広がって迫ってくる。そのスカイラインは山々の鋭い稜線を見せてギザギザに空に食い込んでいる。それが北海道だ。この下には青函鉄道トンネルが通じている。そしてこの下150mにはその地下駅がある。分かった!
この辺の道路が、「袋小路」から「ギリシャ」に変ったのは、青函トンネルの建設機材を運ぶためだったのだ。しかし巨大な橋を作るのと違って、地上の自然や景観が破壊されることもなく、工事が終わってトラックが走らなくなった道路は、我々にそのすばらしい辺境にアクセスする便宜だけを残してくれたようだ。
東京では梅雨の花である「あじさい」が、ここでは真夏の太陽の下で咲き誇っている。最近田舎の道路を走っていると、道沿いに色鮮やかな花壇が長々と作られていて、気持ちを和ませてくれる。あるときは「サルビア街道」になり、またあるときは「コスモス街道」に出会う。この竜飛崎からの道は「あじさい街道」だった。あじさいはかなり背丈の大きな植物なので、道路わきはあじさいの葉で緑の塀が出来て、その中から白や紫の大きな顔が、群をなして我々を見つめる。しばらく見とれて走るうちに、道端は普通の緑に戻る。時たま小さなヒマワリなども緑の中に顔を出し、後ろに飛んでいく。
竜飛崎から日本海に沿って秋田県の能代の方に向かう途中に、世界遺産に指定されている白神山地がある。こ このブナの原始林が注目を集めたらしい。本来なら青森県側から登山道を登って行くのが普通だが、足での登山が苦手な我々は、秋田県の日本海側の八森から真瀬川の渓谷に沿って進む林道を、車で登った。林道をアスファルトで固めただけの狭い道だから、登るにつれて中心線もなくなり、車の幅と道路の幅が同じような感じになる。だからすれ違いが大変で、対向車があったら、お手上げのドライブ。しかもカーブにつぐカーブだ。でも、あたりは静かで、対向車もなく、窓から吹き込んでくる山風は心地よい。道の両側には低い潅木の壁が続き、その向こうにあまり太くない白い幹が緑の中にチラホラと光る。はじめはそれを白樺かと思ったのだが、どうもそれがブナのようだ。葉っぱのつき方や幹の伸び方が白樺とはちょっと違う。やがて周りを取り囲んでいたブナの林が切れて、車は視界が開けた場所に出る。見渡すと、谷の向こうにいくつも山々が連なっている。その山肌には、やはりこんもりとしたブナの林が、巨大な緑の雲を山肌に貼り付けたように、その斜面を飾る。山の峰の向こうには、うす青い日本海が広がっている。更に車を進めると、無人のログハウスがある小さな広場に出た。その先に道はない。もう1台車がある。見ると老人のカップルが登山姿で、まさにブナ林へアタック開始というところである。我々が上がってくる途中で見た「クマ出没、注意!」の看板が頭をよぎる。でもこの天気、この空気、この景色、ここでこのまま帰る臆病者め、と言われているようでもある。向こう見ずでもあるけど、なかなか勇気のある人たちだ。 このブナの原始林が注目を集めたらしい。本来なら青森県側から登山道を登って行くのが普通だが、足での登山が苦手な我々は、秋田県の日本海側の八森から真瀬川の渓谷に沿って進む林道を、車で登った。林道をアスファルトで固めただけの狭い道だから、登るにつれて中心線もなくなり、車の幅と道路の幅が同じような感じになる。だからすれ違いが大変で、対向車があったら、お手上げのドライブ。しかもカーブにつぐカーブだ。でも、あたりは静かで、対向車もなく、窓から吹き込んでくる山風は心地よい。道の両側には低い潅木の壁が続き、その向こうにあまり太くない白い幹が緑の中にチラホラと光る。はじめはそれを白樺かと思ったのだが、どうもそれがブナのようだ。葉っぱのつき方や幹の伸び方が白樺とはちょっと違う。やがて周りを取り囲んでいたブナの林が切れて、車は視界が開けた場所に出る。見渡すと、谷の向こうにいくつも山々が連なっている。その山肌には、やはりこんもりとしたブナの林が、巨大な緑の雲を山肌に貼り付けたように、その斜面を飾る。山の峰の向こうには、うす青い日本海が広がっている。更に車を進めると、無人のログハウスがある小さな広場に出た。その先に道はない。もう1台車がある。見ると老人のカップルが登山姿で、まさにブナ林へアタック開始というところである。我々が上がってくる途中で見た「クマ出没、注意!」の看板が頭をよぎる。でもこの天気、この空気、この景色、ここでこのまま帰る臆病者め、と言われているようでもある。向こう見ずでもあるけど、なかなか勇気のある人たちだ。
我々は引き返した。しかし帰りの道は、太陽の光の方向が逆になるので、全く違った印象になる。再びブナの林を通り抜けると、その先には、秋田杉に埋め尽くされた見事な森が長々と続く。50mにもなりそうに見える秋田杉が規則正し く、まっすぐに伸びて、昼でも暗い森林を形成している。その中を割るようにアスファルトの林道が1本だけまっすぐに走る。両側から視界の中にせり出す杉の森が大きな黒い三角形を作り、その先はだんだん小さくなって前方の1点に集まる。幾何学的な遠近画法が前方に展開する。その透視図の上方から視界を切り取る三角形は鮮やかな空の青だ。一方下方は陰になって黒ずんだ道路がまっすぐに続き、だんだん狭くなって前方の1点に集中するように見える。ふとアメリカ、オレゴン州のクレーターレイク国立公園に通じる道を思い出す。道の両側のセコイアか何かの巨木の森を抜けるときに、車の前方に見えた壮大な遠近画法の光景と重なる。両側の森は太陽をさえぎり、道路は、時たま森をすり抜けてきた薄い光を除いて、一面黒の帯だ。でも、周りの杉の木の上の方は、太陽を浴びて、緑や黄緑に輝く。杉の先端は、筆の先のように丸みを帯びた尖塔になって青空に食い込む。下草の手入れをした形跡も見えないので、ツタやツルの類が下から絡み付いている樹木も多いが、全体として自然が創り出す調和・均衡美とでもいうものがある。車にも人にもほとんど出会うことがない。熊ならその辺から飛び出してきても不思議はないが…。見とれているうちに車の左右は、稲穂を抱えた黄緑が輝く「あきたこまち」の風景に変っていた。目の前には再び日本海の深い青が迫ってくる。 く、まっすぐに伸びて、昼でも暗い森林を形成している。その中を割るようにアスファルトの林道が1本だけまっすぐに走る。両側から視界の中にせり出す杉の森が大きな黒い三角形を作り、その先はだんだん小さくなって前方の1点に集まる。幾何学的な遠近画法が前方に展開する。その透視図の上方から視界を切り取る三角形は鮮やかな空の青だ。一方下方は陰になって黒ずんだ道路がまっすぐに続き、だんだん狭くなって前方の1点に集中するように見える。ふとアメリカ、オレゴン州のクレーターレイク国立公園に通じる道を思い出す。道の両側のセコイアか何かの巨木の森を抜けるときに、車の前方に見えた壮大な遠近画法の光景と重なる。両側の森は太陽をさえぎり、道路は、時たま森をすり抜けてきた薄い光を除いて、一面黒の帯だ。でも、周りの杉の木の上の方は、太陽を浴びて、緑や黄緑に輝く。杉の先端は、筆の先のように丸みを帯びた尖塔になって青空に食い込む。下草の手入れをした形跡も見えないので、ツタやツルの類が下から絡み付いている樹木も多いが、全体として自然が創り出す調和・均衡美とでもいうものがある。車にも人にもほとんど出会うことがない。熊ならその辺から飛び出してきても不思議はないが…。見とれているうちに車の左右は、稲穂を抱えた黄緑が輝く「あきたこまち」の風景に変っていた。目の前には再び日本海の深い青が迫ってくる。
最近注目されるようになった東北の京都と言われる角館(かくのだて)に寄ってみた。先祖が400年前に移り住んで、つい20年前までは実際に当主が住んでいたという「青柳家」などが公開されている。この地方は、12世紀頃から芦名領主の支配のもとにあり、芦名家は常陸国の佐竹領主の下にあった。ところが、関が原の戦で中立の立場を取った佐竹に不満の幕府は佐竹を秋田に左遷した。当然、芦名家も佐竹について行き、芦名家の忠臣である「青柳家」は他の武家とともに角館を任されることになったらしい。
島流し同然の処遇を受けたはずの「青柳家」だが、経済的にも、文化的にも、かなり充実した生活をしていたことが、そこにある展示品からうかがい知ることができる。武家だから、武器が豊富なことは当然のことだが、胸が2重になった鎧、冑などは黒い漆でコーティングしてあり、日本刀ばかりでなく、早くから火縄銃を使用していたことがわかる。それも、銃身が3連になった「最新式」のものまである。
 刀や銃に囲まれた世界は、いつ命を失うかもしれないという極度の緊張感が伴うのだろうか。それを和らげるためか、やさしい顔の人形のコレクションが際立つ。雛祭りのようだが、決してカラフルではなく、どれも顔の表情がひどく穏やかなのが印象的だ。内裏と姫という組み合わせでは、内裏が清楚に正面を向いて毅然としているのに、姫はやや小さく、うつむき加減で、時代の世相を映しているようでもある。素朴な童人形や、独特の「押絵」なども目を引く。押絵はボール紙で型を作り、綿を使ってふくらみを持たせながら表面を鮮やかな絹で覆った3Dの芸術だ。当時は武家の妻や子供の内職でもあったようだ。 刀や銃に囲まれた世界は、いつ命を失うかもしれないという極度の緊張感が伴うのだろうか。それを和らげるためか、やさしい顔の人形のコレクションが際立つ。雛祭りのようだが、決してカラフルではなく、どれも顔の表情がひどく穏やかなのが印象的だ。内裏と姫という組み合わせでは、内裏が清楚に正面を向いて毅然としているのに、姫はやや小さく、うつむき加減で、時代の世相を映しているようでもある。素朴な童人形や、独特の「押絵」なども目を引く。押絵はボール紙で型を作り、綿を使ってふくらみを持たせながら表面を鮮やかな絹で覆った3Dの芸術だ。当時は武家の妻や子供の内職でもあったようだ。
田舎とは言っても、東北は米、木材の宝庫でもある。それに、中尊寺の金色堂などでも象徴されているように、昔は砂金が大量に出た。だから、都市の武家と違って、この地の「青柳家」は経済的にも豊かな生活であったことがうかがえる。鎖国時代にこれだけのものをどのように「輸入」したのだろうか。アメリカ人でさえ、入手するのが難しかったはずの、アメリカ・ビクター社のラッパ型蓄音機の実物、エジソン蓄音機、フランスやドイツから輸入した手動プレーヤーもある。またカメラ店が開けるほどのカメラのコレクション。ドイツのライカやコンタフレックスなど2眼レフカメラがずらり。更には「おじいさんの古時計」で有名になったアメリカ製Grandfather’s  clock。夢のバイクと言われる1917年製のIndian Light Twinの実物がある。今のHarley-Davidson社の前身であるIndian社製で、今では、昔のポスターでしかお目にかかれない骨董品だが、そのスタイルは今とほとんど違わない。 clock。夢のバイクと言われる1917年製のIndian Light Twinの実物がある。今のHarley-Davidson社の前身であるIndian社製で、今では、昔のポスターでしかお目にかかれない骨董品だが、そのスタイルは今とほとんど違わない。
この背景で育った青柳家の親戚の1人に小田野直武がいる。彼は、その像が庭にあるが、平賀源内に教えを受けて、西洋画法を習い、杉田玄白訳の「解体新書」の挿絵を描いた人物だ。奥行きの出し難い日本画の伝統から離れて、遠近法や影の技法を取り入れた立体感覚の解体図を描くというのは当時としては画期的なことであったことだろう。実際、彼の挿し絵入りの「解体新書」の初版本やその伝統を引く洋画もここに展示されているが、この田舎が文化的にも当時、日本の最先端を走っていたことを示している。
屋敷内に秋田民族博物館があるが、これはダムで水没する秋田の古い農家を移築したものだ。秋田杉を贅沢に使い、太い木材で豪雪にも耐えられるように頑丈に出来ている。入口には50年位前によく田舎で見かけた手動の脱穀機がある。その2階は日中戦争、太平洋戦争の遺品が並べられている。「祝、出征、脇坂善一君」と墨で書かれた巨大な文字の入ったバナーが天上から吊り下げられている。金糸で編まれているようで、飾りの房まで丁寧に付けられてい る。不安な気持ちで戦場に出て行く若い出征兵士を、いい加減な気持ちでは戻れないように仕向けたのだろう。わずかな飯を入れて炊いたかもしれない鉄兜、上意下達を徹底させるための虚飾だらけの仕官用軍服。戦死者の家族の気持ちを慰めたとも思えない勲章の数々。どう美化してみても、やはり大きな国家規模の虚偽を隠すための虚構だ。でも、時間をおいて、こういうものを見せられてこそ、その背後にある戦争の真実が見えてくる気がする。 る。不安な気持ちで戦場に出て行く若い出征兵士を、いい加減な気持ちでは戻れないように仕向けたのだろう。わずかな飯を入れて炊いたかもしれない鉄兜、上意下達を徹底させるための虚飾だらけの仕官用軍服。戦死者の家族の気持ちを慰めたとも思えない勲章の数々。どう美化してみても、やはり大きな国家規模の虚偽を隠すための虚構だ。でも、時間をおいて、こういうものを見せられてこそ、その背後にある戦争の真実が見えてくる気がする。
長くなるので、特に印象に残った上の3ヶ所にしぼったが、今回の旅では上記の他に田沢湖、男鹿半島・入道崎、野辺地(下北半島付根)、八戸、雫石(小岩井)、龍泉洞、浄土ヶ浜(陸中海岸)、気仙沼、松島、仙台、裏磐梯などを回ったので、全部で7泊8日になった。日本の国内個人旅行だと、行き当たりばったりで宿を探すのは、高値を吹っかけられたり、条件の交渉が不利になることが多いので、インターネットの「じゃらん」で全部予約しておいた。以下、宿泊関係で気付いたことを率直にまとめてみたい。
「観光」というのは、よく言われるように、その場所の人や物、生活、歴史、文化などが、かもし出す「光」を「観る」ことのようだ。辞書によれば「光」とは「目を刺激して視覚をおこさせるもの」で「輝くばかりの美しさ」も言うこともあるという。しかし、日本での「観光旅行」の多くは、まず「団体旅行」でなければならず、「生活の光を観る」より、温泉地に出かけて酒と料理と歌などで大いに羽目をはずす機会になるか、ある特定集団の人間関係作り、ということになっている。これを受け入れる旅館側でも、押し寄せる集団の一人一人の好みを聞く余裕などなく、お客からの不満がでないように、必要以上の量と質の料理を用意して、当然のように高い料金を取る。玄関に入ると案内係が部屋まで荷物を持って付き添い、部屋に入ると別の部屋係が挨拶に来るというのだから、人件費もかさむのは当然だ。しかし自分のカバンを自分で運べないようでは旅行など出来ないわけだし、目が見えている人間を盲導犬のように連れまわす役割の人を雇って、宿賃をつりあげる必要がどこにあるのだろうか。
今回の旅は7泊8日であった。毎晩20皿も出され、しかも何処へ行ってもほとんど同じメニュである。オードブル、刺身、天ぷら、肉、煮付け、酢の物、吸い物、漬物それに必ず卓上で熱を加える土鍋料理が付く。それにご飯やビール、デザートなど、いかに多く出されても「残すのは罪悪」と叩き込まれた世代の悲しさで、無理をしても胃に押し入れる。これも2,3日なら楽しめるかもしれないけれど、1週間も続くと、本当にうんざりしてくる。確かに、その地方独特の産物が出されたりすると、好奇心が騒ぐ。田沢湖の近くの宿で出された「イワナの炭火焼」、気仙沼で出されて馬刺しと間違えた「サメの心臓」やイカの刺身かと思った「マンボー」など、面白い経験だった。でも、お客の好みを無視して、20皿も押し付けられるのではなく、値段を半分にして、なぜお客が食べたいものだけを少しだけ味わって食べさせてくれないのか。今の世の中、地球の3分の2の人は飢えていて、一方食事制限をしている人だって少なくないのに。多くの人が食べ残すことが分かっているほどの料理を1日がかりで作り、お客の数の20倍もの食器を洗って整理する無意味さに、そろそろ経営者が気付いてもいい頃だと思うのだが…。勿論お客の側も、この虚飾の負担をさせられることなどまっぴらだと思う。
この押し付けは、安い宿といわれているペンションにもあてはまる。今回、小岩井農場の近く、雫石のペンションで、 小岩井農場入場券付きで1泊2食8,200円というのをインターネットで見つけて試してみた。築24年にもなるというログハウスなのに、こぎれいな宿だった。山好きらしい50代の夫婦が、「家庭的に」経営している。残飯を与えられすぎたのか、太りすぎて階段も下りられなくなったラブラドール・レッドリバーが、ベランダに寝そべっている。もう20年以上も料理を一人で担当している奥さんは、週末で20人も入ったお客に、手際よく手の込んだ料理を作る。白髪まじりのご主人がもっぱら給仕役。そして、一生懸命やってもらっているのだから「贅沢」なのかもしれないが、お客の好みは一切聞かれることはない。肉のステーキは常に血が薄くにじむMedium、卵はオムレツ、紅茶はなくて、いやでも全員にコーヒーが出される。つまり、ペンションというのは、外見は洋風だが、極めて日本的なやり方で西洋料理とベッドを出す民宿なのだ。お風呂も多分十分な大きさがないと思われたので、車で近くの温泉に出かけた。ログハウスだから独特の雰囲気はあるが、窓は小さく、ベッドも狭く、部屋は暗い上に、洗面台はおろかトイレも付いてないし、室内テレビさえ有料だ。昔は、ペンションは安いのだから、トイレ共用、タオルや浴衣は持ち込みと了解されていた。しかし、今では8,000円も出せば、田舎の温泉付きのホテルや旅館でも2食付いて、バストイレつきで浴衣を借りてゆったりと過ごすことができる。一般の旅館が値下げする中で、ペンションだけがどういうわけか安いことになっていて値下げしない。基本的な生活が快適とは言えないだけに、割高感が残る。 小岩井農場入場券付きで1泊2食8,200円というのをインターネットで見つけて試してみた。築24年にもなるというログハウスなのに、こぎれいな宿だった。山好きらしい50代の夫婦が、「家庭的に」経営している。残飯を与えられすぎたのか、太りすぎて階段も下りられなくなったラブラドール・レッドリバーが、ベランダに寝そべっている。もう20年以上も料理を一人で担当している奥さんは、週末で20人も入ったお客に、手際よく手の込んだ料理を作る。白髪まじりのご主人がもっぱら給仕役。そして、一生懸命やってもらっているのだから「贅沢」なのかもしれないが、お客の好みは一切聞かれることはない。肉のステーキは常に血が薄くにじむMedium、卵はオムレツ、紅茶はなくて、いやでも全員にコーヒーが出される。つまり、ペンションというのは、外見は洋風だが、極めて日本的なやり方で西洋料理とベッドを出す民宿なのだ。お風呂も多分十分な大きさがないと思われたので、車で近くの温泉に出かけた。ログハウスだから独特の雰囲気はあるが、窓は小さく、ベッドも狭く、部屋は暗い上に、洗面台はおろかトイレも付いてないし、室内テレビさえ有料だ。昔は、ペンションは安いのだから、トイレ共用、タオルや浴衣は持ち込みと了解されていた。しかし、今では8,000円も出せば、田舎の温泉付きのホテルや旅館でも2食付いて、バストイレつきで浴衣を借りてゆったりと過ごすことができる。一般の旅館が値下げする中で、ペンションだけがどういうわけか安いことになっていて値下げしない。基本的な生活が快適とは言えないだけに、割高感が残る。
大きな冷蔵庫にキッチンや調理用具まで完備された外国のホテルを経験した後で、日本の宿の客室でよく見かける、飲み物のビンがギッシリと固定された自動課金式の小さな冷蔵庫を見ると、何というみみっちい根性なのかと不愉快になる。あんなことをするくらいなら、廊下に大きな自動販売機を置いておけば、資本もかからず、維持も簡単だし、トラブルも少ないはずだ。折角、部屋に置くのにお客が持ち込んだものは絶対に入れさせないぞ、とばかりに隙間は一切作らないようにしてある。ちょっと果物を冷やそうとしてもダメだし、小さな冷凍コーナーが付いているのに氷一つ作れない。我々はたまたまクーラーボックスを持っていたので付属の冷凍剤を凍らせたかったのだが、大きすぎて入らない。そこで小さなビニール袋に水を入れて凍らせることにした。次の朝見てみると、カチンカチンに凍った氷を入れたビニール袋が冷凍コーナーの壁にくっついて取れない。仕方がないから電源を切って少し溶かすことにした。が、しばらくして再度電源を入れても、今度は冷蔵庫のドアが開かない。フロントに事情を言って遠隔操作でドアを開けてもらったが、つまらぬ騒動になった。お客に自由に快適に過ごしてもらうことより、少しでも儲けてやろうという根性だけが露骨に出た最悪の仕掛けという気がする。
最後の裏磐梯では、素泊まり3,650円というプチホテルを試してみた。素泊まりを宣伝しているからには、外国のように、 近くにレストランなどがあるだろうと考えたが、間違いだった。檜原湖の近くの静かなところなのだが、隣にはオートキャンプ場があり、自炊が当たり前の空気がある。着いたのが4時過ぎで、まだ明るいし、五色沼の方まで降りてみることにした。しかし、ちょっと豪華そうに見える「裏磐梯高原ホテル」は夕食1人8,000円からと言うし、2時間も待たなければならない。湖畔の、レストランが集まったところはすでにシャッターを降ろしたり、室内の電気を消していたりして、閑散としている。団体客がバスで到着するときは華やぐようだが、個人客は旅行者にあらず、という感じである。台風が近づいていたことは確かだったが、青空が残り、夕焼け雲も控えめに輝いていた。夕方の湖は、汚いところも見えなくなり、静かで、神秘的な雰囲気が漂う。向こうの方に1軒コンビニらしいのが目に入ったので、そこで好みにあったものを暖めてもらったりして湖畔でピクニックをした。湖面を流れてくる微風が気持ちよく、日中の暑さも消えて、連日の旅館食のあとでもあり、快適な食事であった。プチホテルに戻った頃はすっかり日も暮れていた。ここはその名のように、5,6室しかなく、ペンションとさして違いはなかったが、はるかに快適だった。まず、部屋の広さにゆとりがあり、大きなツインベッドにテーブルや椅子も置かれて、自由に使える冷蔵庫、洗面やトイレつきで、もちろんテレビも無料、蛇口からは暑い湯がすぐに出る。窓からの景色も磐梯山腹が緑一色に広がっていた。しかも、大きな岩風呂の温泉付きで、湯船からはガラス越しに大きな水車が回っていてびっくり。これで全て込みで3,650円だから、近くにレストランさえあれば、世界に通用するので、外国人「観光」客も喜んで来るだろうという気がする。 近くにレストランなどがあるだろうと考えたが、間違いだった。檜原湖の近くの静かなところなのだが、隣にはオートキャンプ場があり、自炊が当たり前の空気がある。着いたのが4時過ぎで、まだ明るいし、五色沼の方まで降りてみることにした。しかし、ちょっと豪華そうに見える「裏磐梯高原ホテル」は夕食1人8,000円からと言うし、2時間も待たなければならない。湖畔の、レストランが集まったところはすでにシャッターを降ろしたり、室内の電気を消していたりして、閑散としている。団体客がバスで到着するときは華やぐようだが、個人客は旅行者にあらず、という感じである。台風が近づいていたことは確かだったが、青空が残り、夕焼け雲も控えめに輝いていた。夕方の湖は、汚いところも見えなくなり、静かで、神秘的な雰囲気が漂う。向こうの方に1軒コンビニらしいのが目に入ったので、そこで好みにあったものを暖めてもらったりして湖畔でピクニックをした。湖面を流れてくる微風が気持ちよく、日中の暑さも消えて、連日の旅館食のあとでもあり、快適な食事であった。プチホテルに戻った頃はすっかり日も暮れていた。ここはその名のように、5,6室しかなく、ペンションとさして違いはなかったが、はるかに快適だった。まず、部屋の広さにゆとりがあり、大きなツインベッドにテーブルや椅子も置かれて、自由に使える冷蔵庫、洗面やトイレつきで、もちろんテレビも無料、蛇口からは暑い湯がすぐに出る。窓からの景色も磐梯山腹が緑一色に広がっていた。しかも、大きな岩風呂の温泉付きで、湯船からはガラス越しに大きな水車が回っていてびっくり。これで全て込みで3,650円だから、近くにレストランさえあれば、世界に通用するので、外国人「観光」客も喜んで来るだろうという気がする。
青森の東、野辺地にある「まかど温泉富士屋ホテル」という山の上の大きなホテルに泊まった。ロビーなども吹き抜けの 白壁とガラス作りで高い天井に太い柱がそびえて、豪華に見える。しかしここでは3人で泊まって一人1泊2食すべて込みで7,440円であった。夕食は赤いローソクの灯る、きれいなクロスのかかったテーブルでの中華料理のコースであった。値段には生ビールも含まれていて、品よく正装した若い女性が説明しながら食事を運んでくれる。部屋のガラス越しに、水中照明の光を浴びた魚が、外の池の中で泳いでいるのが見える。その向こうには先ほどまで陸奥湾が望まれた方角だ。個人の好みを全く尊重しない日本料理と違って、中華料理は大きな器に入れて出されるので、いやなら食べなくていいし、個人が好きなだけ取り分けられるのがいい。大きな器に残したものが再利用出来る(?)利点は、人口過剰な中国人の優れた知恵なのだろう。温泉は広い湯船が底板も回りも分厚いヒバ材で出来ていた。独特の感触と色は記憶に残る。 白壁とガラス作りで高い天井に太い柱がそびえて、豪華に見える。しかしここでは3人で泊まって一人1泊2食すべて込みで7,440円であった。夕食は赤いローソクの灯る、きれいなクロスのかかったテーブルでの中華料理のコースであった。値段には生ビールも含まれていて、品よく正装した若い女性が説明しながら食事を運んでくれる。部屋のガラス越しに、水中照明の光を浴びた魚が、外の池の中で泳いでいるのが見える。その向こうには先ほどまで陸奥湾が望まれた方角だ。個人の好みを全く尊重しない日本料理と違って、中華料理は大きな器に入れて出されるので、いやなら食べなくていいし、個人が好きなだけ取り分けられるのがいい。大きな器に残したものが再利用出来る(?)利点は、人口過剰な中国人の優れた知恵なのだろう。温泉は広い湯船が底板も回りも分厚いヒバ材で出来ていた。独特の感触と色は記憶に残る。
インターネットで宿を比較しながら自分で予約できるようになって、日本の宿泊施設にも変化が起きているような気がする。立派な建物で、多くの世話係を雇って、食器だらけの食べきれないご馳走を出し、何万もの費用を取って儲ける形が依然として存在する一方で、裏磐梯のプチホテルのように、団体旅行の面倒をみるのではなく、ややこしい食事は他に任せて、ほとんど個人経営で、安い快適な宿を提供するようなスタイルも見えてきた。大きなホテルでも、中国料理を取り入れるなど、発想の転換で経営を合理化して、イメージを変えようとする努力も見える。真の「観光」を求める世界の旅行者が日本に来る時代になったのだから、慰安旅行中心の宿も脱皮していくとは思われるのだが...。
 ←これをクリック ←これをクリック
●ビデオをご覧になる場合はWindows Media Player 9が必要です。必要ならDownloadをクリックしてダウンロードして下さい。無料です。
●ビデオは全部で40分かかりますが、「早送り」「巻戻し」「ジャンプ」などが可能です。


|